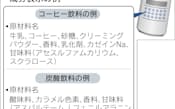食事量の基準、カロリーからBMIへ 国が変更
2015年から 体力差を反映
[会員限定記事]
健康維持のために必要な食事摂取基準が来年から大きく変わる。厚生労働省はこれまで年齢や性別ごとに1日あたりで必要なエネルギー量の目安を一律に定めてきたが、体格の違いによって必要なエネルギー量は違うなどの課題があり、来年から身長と体重から肥満度を算出する体格指数「BMI」の目標値を示すことにした。BMIを保ち生活習慣病などを減らす狙い。目標値を長く保つには自分で食生活を詳しく把握することが大切になりそうだ。...
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。