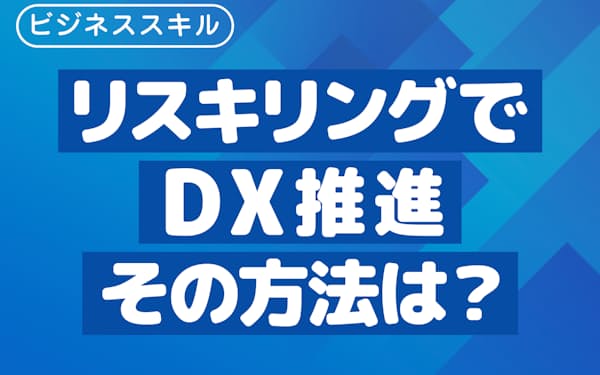生きたお金の使い方 我が子も学べる「家計の三分法」
子どものお金

前回の「『お金持ちになりたい!』 子どもの質問どう答える?」でお伝えしたように、6人の子を育ててきた我が家では月に1度、家族全員が参加する「家族マネー会議」を開いています。この会議では私たち夫婦から家計の収支報告をします。子どもたちが欲しいもののプレゼンなどをすることもあります。
1つ特徴があるとするなら、支出を報告する際に「食費」「日用品代」などといった費目以上に注目しているポイントがあるということです。それは、ひとつひとつの支出について「消費」「浪費」「投資」のどれに該当するのかを考えるということです。発表する側も聞く側も、その判断に注目しながら話し合っています。
家計管理の考え方でもあるのですが、支出が上の3つのどれに当てはまるかを考えるのは、実はとても大切なことです。これを子どもの頃から意識していると、お子さんのお金の使い方が良い方向に変わっていきます。
得られるプラスが多いので、私は支出管理におけるこの手法を「家計の三分法」と名付け、10数年前からおすすめしてきました。ありがたいことに今では多くの方々がご活用くださり、少しは認知が広がったように思います。家計にまつわる記事や情報サイトなどでこの手法の紹介を見かけることも増えました。
今回は、この家計の三分法について、改めて基本となる内容をご紹介したいと思います。
支出の意味を考えることを習慣化する
家計の三分法とは、支出を「価格」ではなく「価値」でみよう、というものです。別の言い方をすれば、生きたお金の使い方をするための支出管理法です。
というのも、暮らしの中では、「安い、今がチャンス」と思って買ったものでも、後になって、さほど必要ではなかったと気づくことがあります。食費を減らすために安売りで大量に食材を買っても、食べきれずに結局腐らせてしまうといったこともあるでしょう。これらを家計の三分法に照らし合わせてみると、始めは「投資」や「消費」だと思ってお金を払ったのに、実は「浪費」になってしまっているというわけです。この手法はそうした失敗に気付き、ムダを省くための支出管理法でもあります。
ポイントは、買い物やサービス利用などでお金を使った後、2週間など、ある程度時間を置いたうえで、自分の判断が適切だったかどうかを振り返ることにあります。そうすることで、自分にとっての支出の意味を考えることが習慣化し、お金を上手に使えるようになります。
意識してお金を使うための3つのキーワード
それでは、家計の三分法で使う3つのキーワードの意味を改めて確認しておきましょう。
まずは「消費」です。消費は生きるため、生活するために欠かせない支出で、普段の買い物や交通費、スマートフォンの利用料などが該当します。
次に「浪費」です。これはいわゆる無駄遣いのことを指します。私の考えでは、ギャンブルで使ったお金や借金の利息、使わないのに支払い続けている何かの会費のようなものも含みます。過剰な消費も浪費に含める場合があります。
最後に「投資」です。これは将来的に自分に返ってくるような支出やお金の動きです。「お金の動き」と書きましたのは、貯金もここに入るからです。株式などへの文字通りの投資も入ります。それだけではありません。たとえば、仕事の幅を広げるために始めた通信教育の費用や何かを学ぶための参考書代などの「自己投資」も該当します。
まずは出費する際、この3つのキーワードを念頭に置くようにしましょう。大人も子どもも、これを意識すると、お金の使い方が変わってきます。
小遣い帳を活用、子に出費を判定させる
子育て中の方は、この「家計の三分法」をお子さんによる小遣いの管理で取り入れてみてください。我が家の家族マネー会議のように、お金の使い方についてお子さんと定期的に話し合っているご家庭では、お子さんが支出を報告した際、「3つのどれに当てはまるか」を親子で一緒に考えることも有効です。
お子さんの小遣い管理で取り入れる場合は、小遣い帳を活用しましょう。使うのは「小遣い帳」と銘打った市販の専用商品でなく、普通のノートなどでもOKです。やり方はとても簡単です。以下をその都度、お子さんに書いてもらいましょう。
・いつ、いくら小遣いをもらったか
・買った日、買ったもの、金額、残高
これを記入できれば上出来です。上には便宜的に「買った日、買ったもの」と書きました。ただ、ここには「○○の動画配信の視聴費用」のような、「(サービスを)利用した日、利用した内容」といったことも書いてもらいます。お子さんの手元のお金に動きがあった場合、たとえば「お年玉をもらって貯金した」など小遣い以外に「入り」があったなら、それらも書けるとなおよいです。
継続が難しそうな場合は、日付と買ったもの・利用したサービスなど、支出額だけの記録でもOKです。そして、買い物などで支出したその日のうちに、買ったものや利用したサービスの隣に「消費」「浪費」「投資」のどれに該当するか、判定も書かせましょう。この判定は、「自分にとってどうか」というお子さんの視点によるもので十分です。
そして次の小遣いを渡す日、もしくは出費した日から少し時間が空いた日に機会を設けて、親子で話し合う場を持ちましょう。ここでは、お子さんにお金を使った時の判定から何か変わったかどうかを尋ね、変化があった場合はその理由も一緒に振り返るようにします。これを繰り返すことで、子どもなりの「軸」ができてきます。
この「軸」が育ってくると、お子さんは「お金を払うべきだ」というものと「支払わなくてもよいだろう」というものを自身で判断できるようになります。つまり、両者を分けるお金の使い方の軸になるのです。言い換えれば、金額の高い、安いではなく、自分にとって本当に必要なものかどうかを判断できるようになります。
「ゲームが欲しい」「パソコンが欲しい」……。子どもたちにも子どもたちなりに、いろいろ欲しいものがあり、それを親に伝えてくることがあるでしょう。そういう機会をとらえて、それは消費なのか、浪費なのか、投資なのか、ぜひ、その出費の意味をお子さんと話し合ってみてください。せっかく買ったゲームでも1カ月もしないうちに飽きてしまったら、それは浪費になってしまいます。こうした身近な例を挙げながら話をしていくと、子どもの判断力が養われますし、話し合いを通じて大人とはまた違う、お子さんなりの考え方があることが分かるかもしれません。
支出とは「価値」にお金を払うこと
今はモノを買わせようとする様々な誘惑があります。それでも、この三分法の感覚で支出を振り返る習慣を身につけられると、子どもも大人も後悔するお金の使い方をかなり減らすことができます。
皆さんに知っていただきたいのは、お金を使うときは出費の大きい・小さい以上に大切な注視すべきポイントがあるということです。なぜなら、モノを買うにせよサービスを利用するにせよ、支出とは、それによって得られる「価値」にお金を払うことだからです。
確かに「より安いものを」と節約を重視すべき場合もあるでしょう。しかし、豊かな人生を送るうえでは、思い入れのある何かを買うことや大事な人との会食、習い事の費用など、出費はある程度かさむとしても、そのときにしておきたい大切な体験もあるからです。何かの支出をする際は、できるだけ「『価値』にお金を払う」ということを意識するようにしてみてください。そうすることで、後悔することが少ないお金の使い方が自然と身についていきます。
我が子にみるお金の使い方、成功例と失敗例
「それだけで本当にお金の使い方が身につくの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。ここで、我が家の子どもたちの例をちょっとご紹介したいと思います。
ある子は真面目に小遣い帳を付けるタイプで、お金の使い方も堅実。比較的節約家です。支出の際は消費か、浪費か、投資かを真面目に考えて、ムダな支出はほとんどしません。
そんな彼女はプロレスファン。試合を見に行くのが夢ですが、小学生時代はなかなか試合観戦に行けませんでした。そこで自分の満足度を上げるために、月額300円ほどの動画配信の会員となって試合はそこで「消費」として視聴。毎月数百円ずつお金をためていき、あこがれの選手がデザインしたパーカーを購入することにしました。自分でコツコツとためたお金で手に入れたそのパーカーは、彼女の中では価値のある「投資」となり、長い間、彼女がここぞと思う時に着る大事な一着となりました。
一方、別の娘は、小遣い帳をつけず家族マネー会議の時以外は三分法も実行しません。彼女はある日、急に「バイオリンが弾きたい」と言い出しました。ほどなく安く手に入るからと、ネットショッピングで見つけた1万円のバイオリンを自分で購入。数日弾いていましたが音もうまく出せず、あっという間にネットオークションで売却しました。結果的に購入時との差額となる8000円ほどの損をしました。これは支出の意味をきちんと考えずに、「安いから」と価格だけで買い物をしたことで起きた失敗例の1つです。
このような失敗を避けるためにも、支出を「価値」で見る習慣を作ることは、非常に有効だと思います。特に子どものうちから習慣化できると、金銭感覚もしっかり育ちます。とはいえ、難しく考える必要はありません。まずは子どもに支出の記録をつけさせ、三分法で判定させることを習慣化させていきましょう。
時には「浪費」もあっていい
なお、大人にも伝えていることですが「浪費」をゼロにする必要はない、と考えています。お金は頑張って稼ぐのですから、仮にどれだけ貯金がたまっていくとしても、自由気ままに使える余地が少しもないとしたら、果たしてそれが望ましい暮らしだろうか、との思いが根底にあるからです。
家計の三分法では理想の割合を唱えています。消費70%、浪費5%、投資25%というのがそれです。上記のような思いも踏まえて、少しですが浪費にも好ましい割合を設定した次第です。小学生くらいまでなら、子どものこづかいの5%というと、10円の駄菓子をいくつかという程度でしょう。それなら親が買ってあげればいいというご意見もあるかもしれません。けれど自由に、時には無計画にお金を使う体験もしておいてほしいと思うのです。もちろん、お子様本人がそれは嫌だというなら、無理に使わせる必要はありません。
子どもであろうと「時には浪費もまたよし」とあえてお伝えするのには理由があります。様々な経験は、気づきや成長を与えてくれるもの。浪費を含めたお金の使い方も、子ども時代の「練習」は後できっと役に立つはずです。
やがて大人になったとき、「節約、節約」の一辺倒で日々、暮らしを切り詰めることにだけ注力する。そうなっては切ないと思うのです。気持ちのゆとり部分として、たまには自分自身でそれと認識したうえで、節度ある「浪費」をする。そんなこともあっていいのではないでしょうか。一度しかない人生を豊かに過ごしていくうえで、ゆとりの大切さも子どもたちに分かっていてほしいと思っています。

関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。