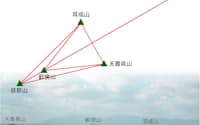弥生の息吹呼び覚ます西播磨の里人
新宮宮内遺跡(兵庫県たつの市) 古きを歩けば(29)
西播磨地方を南北に流れる揖保川。中流域に開けた盆地に弥生中期、大集落が営まれていた。その跡は現在は新宮宮内遺跡と呼ばれ、歴史公園として整備が進んでいる。地域史を子供たちに伝えようと、このほど住民らの手で竪穴住居が復元された。
■「茅の確保が一苦労」
「屋根を葺(ふ)いたのは45年ぶり。こつを思い出しながら作業したけど、できばえはいまひとつやな」。屋根葺き職人だった経験を生かし、住居復元に参加した...
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。