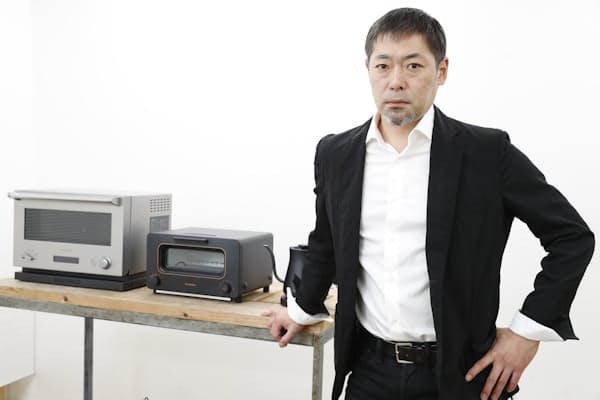変革も信頼構築もゆっくりと 正解なき時代の社会参加
Slow Innovation代表 野村恭彦さん

Slow Innovation代表 野村恭彦さん
次代を担う「旗手」は何を感じ、何を考えているのか――。日本経済新聞社が運営する投稿プラットフォーム「COMEMO」から、「キーオピニオンリーダー」が執筆したビジネスパーソンにも役立つ記事を紹介します。今回は、行政、企業、市民など地域の関係者をつないで社会課題の解決を目指すコンサルティング会社、Slow Innovation(スローイノベーション、東京・渋谷)の代表取締役で、KIT虎ノ門大学院(金沢工業大学大学院虎ノ門キャンパス)の教授も務める野村恭彦さんに、「スローイノベーション」について語ってもらいます。
◇ ◇ ◇
「スローイノベーションの時代」とは、一人ひとりの行動が社会を決める時代です。この時代に生きる私たちがどのように働き、消費し、投票するのか。そのすべての行動が、未来を決める力をもっています。それは、本当にワクワクする時代であり、今後「スローイノベーション」がますます重要になると、私は考えています。
カーボンニュートラルの時代へ
地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」。その目標実現に向けて昨年9月以降、日本と韓国は2050年に、中国は2060年に、温暖化ガス排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの達成をめざすことを相次いで発表しました。二酸化炭素(CO2)排出実質ゼロと言っても、本当に私たちはCO2を出した分だけ植樹などでオフセットしながら生きていくことができるのでしょうか。
また昨今、企業のSDGs(持続可能な開発目標)への注目はたいへん高まっており、環境や社会問題、企業統治に対する取り組みを重視する「ESG投資」が広がりを見せています。
SDGsへの投資は勢いを増し、企業はSDGsのインパクトを無視できなくなってきているのです。投資家がCO2排出量の多い企業から投資を引き揚げる「ダイベストメント」に加え、脱炭素に有効な技術をもつ企業に投資が集中するなど、上場企業はSDGsへの取り組みなしには、世界から投資を集められなくなってきています。
そのため、現状の企業のSDGsへの取り組みは、どうしても「株主対策」になりやすく、社員一人ひとりの自分ごとの取り組みになってはいません。この状況を変えるには、もう一つの企業の駆動要因である「市場の動き」を生み出す必要があります。つまり、企業にとって「責任ある消費者」の市場が無視できない状況を、私たち自らがつくり上げることです。
「責任ある消費者」として生きるということは、例えば身近なところでは、レジ袋をエコバッグに代えること、使い捨てプラスチックを使った商品を選ばないこと、地産地消の食材を選ぶこと。そして、生ゴミはコンポストを使って土に戻すことで焼却するゴミを減らしたり、使う電気は自然エネルギーを選んだり、簡単にできることも多いのです。
しかし、いくら私たちがエシカル(倫理的な)消費によってカーボンニュートラル生活をしようとしても、流通する商品やサービスがカーボンニュートラルの選択肢を提供していなければ始まりません。