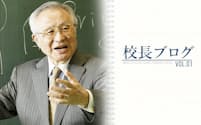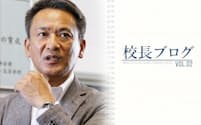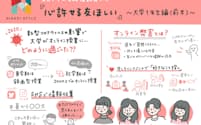夫婦同姓は当たり前かな? 学校で真の民主主義を学ぶ
横浜創英中学・高校の工藤勇一校長(4)
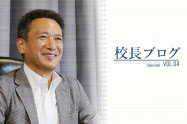
(先生への質問を募集します。詳細は文末ご覧ください)
夫婦別姓問題も進展せず、本当に対話して合意している?
2021年は横浜創英中学・高校を舞台に「自律した生徒を育てる」教育に本腰を入れていきたいと思います。新型コロナウイルス感染が拡大する中、20年4月に校長に着任しましたが、すでに100人以上いる教職員たちとも目指す教育目標をほぼ共有し、プロジェクトチームも発足。各教科のカリキュラムづくりもスタートしました。自律した生徒の育成には、教職員や生徒たちが様々なテーマについて徹底的に対話して合意し、生徒が主体の学校に生まれ変わる必要があります。
「対話して合意する」、日本は民主主義国家だからそんなことぐらい当たり前じゃないかと思うでしょうが、私たちは、本当に対話して合意することができているでしょうか。例えば、時々メディアでも取り上げられている「夫婦別姓問題」について考えてみましょう。国会等では夫婦が別姓のまま婚姻することが選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入の是非が議論されていますが、なかなか進展しません。多くの国民に関係する問題ですが、「夫婦同姓は昔からの日本の伝統」などと根拠の不明確な理由で否定的だったり、議論自体に無関心だったりする人もいます。
現在、世界の主要国の中で、法的に夫婦同姓が規定されているのは実は日本ぐらいだそうですが、そもそも夫婦別姓の方が日本の伝統だったことを知っている人は少ないかもしれません。先日、歴史に詳しい立命館アジア太平洋大学の出口治明学長と対談したのですが、「日本でも明治維新までは夫婦同姓という概念はなかった。源頼朝は北条政子と結婚して鎌倉幕府を開いたわけですが、別姓ですよ」と指摘されました。日本の場合、明治から名字使用が広く一般に許され、明治期の法律で夫婦同姓が定められたそうです。これは当時、欧州のキリスト教国では夫婦同姓が一般的だったからという説もあります。日本の近代化は欧米のマネから始まりましたが、欧州でも現在は夫婦別姓が認められています。
「対話して合意する」ということから話がそれてしまったので、本題に戻したいと思います。夫婦別姓問題は一つの事例に過ぎませんが、私たちはこのような問題に対してしっかりと向き合い、国民全ての人々の利害について、真剣に話し合って物事を決めているのでしょうか。
民主主義とは何か、教師は教えられる?
「対話して合意する」。この民主的なプロセスが本当の意味では日本の文化にまだ根付いていないのだと私は思います。
西欧の多くの国では市民革命などを経て、近代社会を実現し、民主化に移行してきましたが、日本の場合は明治期に政府が西欧のルールや慣習を模倣して、近代国家の基盤をつくりました。さらに言えば、真の意味での民主主義は、自分たちで勝ち取ったというよりも、第二次世界大戦に敗れた結果として、他国に与えてもらったものにすぎないのかもしれません。

「民主主義=多数決で決定すること」などと安易に考えている人がたくさんいるのが、残念ながら日本社会の現実です。このことの責任の中心は学校教育にありますが、「対話して合意する」プロセスを真の意味で経験をしたことがほとんどない私たちが、民主主義を学ばせていくのですから、難しいのは当たり前かもしれません。事実、学校の教師でさえ、「民主主義って何?」と問いかけても、誰もがわかるように説明できるものはほとんどいません。私自身、若い頃の自分を考えれば同じようなものす。
民主主義を私なりに説明してみようと思います。一言で言えば、可能な限り個人の自由を尊重する中で、全ての人々の幸福を実現するという、簡単には実現できないこの答えを全員の対話を通して探し出し、合意するプロセスということになるのでしょうが、やはりこれではわかりづらいですよね(笑)。
一人一人の考え方、価値観はもちろんのこと、それぞれが持っている社会的な背景や立場はみんな違います。当然、あらゆる場面で利害の対立が生まれます。「夫婦がどちらの姓を名乗るか」ということで言えば、例えば「夫婦別姓」を統一ルールとして定めてしまった場合、同姓を名乗りたいという人の利益を損ねることになるわけです。多数決で数の多い方に一方的に物事を決めるということは、当然ですが、こうしたことが頻繁に起こることになります。
でも、どちらを名乗るかを個人それぞれが決めることができるようにすれば、どうでしょうか。少なくとも、自分が選びたい姓を名乗るという個々の利益については損ねることはありません。もちろん、「自分の価値観をそうは考えていない人々に押し付けたいという自由」は損ねることにはなります。つまり、「自分の自由を尊重してほしい」と主張することは、他者の自由を尊重する方向で妥協点を探し出していく作業とセットでなければいけないということです。
日本の学校、倫理観で物事を解決 腹落ちする?
日本がより民主的な国へと成長していくためには、一人一人がこうした対話の経験を積み重ねていくことこそが大切ですが、日本中の大半の学校では生徒が主体的に話し合って、合意してルールを決めたりする学校運営の仕組みがほとんどありません。
例えば、AくんとBくんがケンカになり、殴り合いになる際、多くの教師は「暴力は倫理上許されない」と一方的に制止し、道徳観で物事を解決しようとするでしょう。なぜ暴力はダメなのか、納得行くまでみんなで話し合い、解決策を考えようという教師はどれだけいるでしょうか。「殴れば、大けがをし、命の問題につながる。では、どんな解決法があるのか」という議論があってもいいでしょう。
ただ、一方的に暴力はダメと言われても、AくんとBくんは、腹落ちしないと思います。日本は「心の教育」という道徳教育を重視してきました。しかし、そのお題目を唱えるだけでは、民主主義国家を担う人材は育つとは思えません。
学校は民主主義を支える自律型の人材を育てる場所でなければいけません。もちろん、横浜創英もそうした場所として成長していきたいと考えています。直近の話だと、コロナ禍で海外への修学旅行が中止に追い込まれ、その代替策を高2の生徒約40人が協議しています。500人あまりの高2のうちの希望者で構成していますが、様々な課題について議論し、それを全生徒の合意形成につなげるため、議論のプロセスも随時公開しています。(詳細は前回記事「学校経営は生徒の手で 修学旅行も制服も自分で決める」)
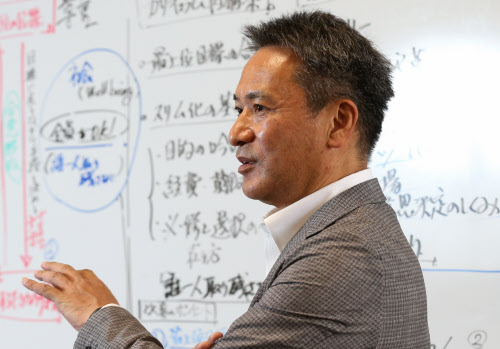
教師はティーチャーではなく、コーチャーに
生徒たちは目的や場所、費用のみならず、各地のコロナの感染状況を調べ、「宿泊を伴う旅行は難しいのでは」とか、「そもそも旅行を希望しない人もいる場合は、選択制を導入しよう」など様々な議論をしているようです。全生徒がOKになるには確かに修学旅行の選択制もありでしょう。国の「選択的夫婦別姓制度」の導入は遅々として進みませんが、横浜創英ではそうした選択制が実現できるようになるかもしれません。
大事なことは生徒1人1人が当事者意識を持ち、自分たちで考え、話し合い、利害の対立を自覚し、全員の自由を尊重する方向で妥協点を見つけ出す、そして合意することです。学校運営に関することは、教師が指導するのではなく、生徒たちが主体になって決めることが大事です。教師はティーチャーではなく、コーチャーでいいと私は考えています。一斉型の授業で、教師が一方的に知識を教えるのではなく、生徒が自分にとって最適の学習方法を選択し、学ぶことが効果的です。必要に応じて自由にICT(情報通信技術)を活用してもいいでしょう。
効果的な学習方法は教科ごとに異なります。すでに横浜創英の先生たちはプロジェクトチームを発足しており、21年には個別最適な学習のための各科目のカリキュラムづくりを進め、様々なトライアルをやっていく予定です。自分が主体的に学ぶことで、時間を効率的に使えるようになります。日本の普通の中高は平日6時間制です。しかし、結構ムダな時間が多いのではないでしょうか。それぞれの生徒が効果的に時間を使えば、もっと部活や余暇に割けるでしょう。自分が何をしたいのか、社会に役立つために何をすればいいのか、考えたり、みんなと対話したりする時間も生まれるでしょう。横浜創英から真の民主国家を担える自律型の人材を1人でも多く育てていきたいと思います。
1960年、山形県生まれ。東京理科大学理学部卒。1984年から山形県の公立中学校で教えた後、1989年から東京都の公立中学校で教鞭をとる。東京都教育委員会などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校の校長に就任。宿題や定期テスト、学級担任制などを次々廃止するなど独自の改革を推進。2020年4月から現職。
質問を募集します
読者の皆様から、「校長ブログ」の先生方への質問を募集します。n22_info@nex.nikkei.co.jpにメールでお送りください。メールの件名に【校長ブログ】、本文に質問内容とハンドルネーム、年齢をお書きください。たくさんの質問、お待ちしております。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。