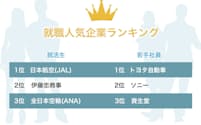就活は足を運んで会話して 後輩たちへ体験的心得
内定者座談会(下)

2020年が「就活イヤー」となる後輩たちに役立ててもらおうと、春の入社を待つばかりの内定者4人が語り合った座談会の後編。前編で語られた多くの体験から導き出される教訓は何か。「受け身でなく、自分から動いてみよう」「1人で考え込まないで」――。就活生の「お守り」になるようなメッセージがこもる言葉が次々飛び出した。(司会はU22編集長・安田亜紀代)
Aさん 明治大学4年の女子学生。広告制作会社へ就職予定。
Bさん 都内私立大学院2年の男子学生。大手メーカーへ就職予定。
Cさん お茶の水女子大学4年。金融系へ就職予定。
Dさん 法政大学4年の男子学生。証券会社へ就職予定。
――大企業かベンチャーか、迷う学生が多いけれど、皆さんはどう考えましたか。
Aさん 私はベンチャー企業でインターンをして、事業内容が変わるケースがよくあることを知りました。お金になる事業をしなければならないのはわかるのですが、ころころ変わるのも嫌だったので、自分にはベンチャーは合わないと思った。でも大手にも行きたくなかったんです。自分に存在意義がある会社に行きたい。何千人の中の1人ではなく、Aさんとちゃんと認識してもらえる会社がいい。替えがきかない存在でいたいと思い、今の内定先を選びました。
Dさん 僕は大企業派でした。そもそもなんのために勉強をがんばって、今の大学に入ったのか。自分の中に「学歴主義」みたいなところがあるんです。ベンチャーだと学歴による(有利不利の)違いがあまり顕著に出てきませんよね。だったら、大学名を最大限に生かして、大企業に行こうと思っていました。
「学歴」実感、でも最後は…
――学歴や学部間格差を感じたことはありましたか。
Dさん 金融系は顕著だったと思いますよ。業界1位の企業ともなると、早稲田、慶応、上智がメインだったなあ。GMARCH(学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政)は、そこにどれだけ食いついていけるかという状況でした。でも、(面接に進めた会社では)とりあえずスタートラインには立たせてもらえたわけだから、そこから先は早慶に負けないようにしようと思ってました。門前払いされなければ、そこからは自分次第です。
Bさん 文系で大学院に進んだので、違う意味ですごく気にしました。文系で大学院に進んだのはなぜ? と聞かれるだろうと思いましたから。理系なら専門分野の研究を深めるという目的がはっきりしてますけど「文系だと、学部生とあまり変わらないよね」とか「大学院の研究とうちの会社の仕事となにか関係ある?」と聞かれることもあった。不安でした。
Cさん お茶の水女子大は学校の規模が小さいから「企業と私大の学生だけの懇親会があったらしい」なんて話を聞くと不安でした。でも、本選考が始まってからは、結局は実力だなと思えました。
――就活がうまくいった学生ってどんな人たちが多かった?
Bさん ざっくりしてるんですけど、気持ちよくがんばれて、ちゃんと話を聞ける人かなあ。何社も内定をもらった人はみんな、とても気持ちがいい人なんですよ。
Cさん 就活での「成功」って人それぞれでとらえ方が違うでしょうけれど、就活を楽しめる人かな。
Dさん そうかも。僕は楽しかったです。就活はゲームだなと思ったら、落ちるのも当たり前だと思えたし、ゲームでレベルアップするためにスキルをつけようって考えていました。
――就活を始める時期はいつごろがいいと思う? 学生時代をどう過ごすかも含めてアドバイスはありますか。
Dさん 僕が就活を始めたのは大学3年の6月でしたが、もう少し早く始めていたらよかったと思っています。というのも、3年生の冬ごろになってコンサル業界とか外資系企業という選択肢に初めて気づいたんですよ。もっと早く知っていれば受けられたかなあと思うこともありました。
Cさん 私は3年生の4月スタートでした。やはり、企業側も3年生に対しては本腰を入れてインターンなどを開催してくれます。比較的早くから活動したことで、早めに自分はベンチャー向きではないことにも気づきましたし。実は2年生のときにも合同説明会にもぐりこんでみたりしましたが、そこまでしなくてもよかったかなと思っています。
Bさん 僕が感じているのは、就活を始める時期というより、自分の考え方とかどんな仕事をするかといった方向性を、いつごろ固められるかが大事ということです。僕は大学院1年生の秋から10カ月間くらい就活しましたが、それだけの時間を使って自分の方向性を固めました。学部卒で就職した友人はいま、社会人2年目なんですよ。自分の方向性をちゃんと決めずに、ふわっと就活してしまった友人からいろいろ聞いていたのも、よかったかもしれないです。

――ひと足先に社会人になった友人が、反面教師になったということ?
Bさん そうなんです。なんとなく有名な企業に就職した友人が、今になって葛藤している様子を見て、自分の方向性を考えました。友人から「この会社はやめておいたほうがいいよ」とか「CSR(企業の社会的責任)の分厚い本を読むと、いろんな企業の評価が書いてあるから参考になる」と教えてもらいました。「企業ごとに市場シェアを調べておくといいよ」って教えてくれたのも友人です。シェアが高い会社は自然と面白い仕事ができるチャンスが多いんじゃないかな、というアドバイスでした。僕が結局、ニッチな分野のメーカーに就職することに決めたのも、こうしたアドバイスがあったからです。
――後輩たちにエールを。
Bさん 学生時代はいろいろチャレンジできるので、(就活は)それをやり切ってみてからでもいいのかな、と。自分が楽しめるものを知って、それに近い仕事ができればいい。あと、いろんな社会人に話を聞いた方がいい。ネット上の情報だけではわからないところがあるので、手間はかかるけど、自分で足を運んで取った情報は間違いないと思う。3つ目は自分の方向性、軸をつかむこと。これは反省を込めて。
Dさん 僕が伝えたいのは、多少なりとも興味をもったことは足を運んで話を聞く現場主義。興味を持ったら即行動というスタンスですね。僕は最初、不動産業界に興味があったのですが、業界に勤める人に会って話を聞いたら、思い描いたのとは違うことがわかって、志望度が下がりました。
Cさん 就活中って、どうしてもヒートアップしがちです。セミナーなどに行くと「これからがんばるぞ」みたいになって、乗せられちゃう。企業を選ぶ段階で兄に言われたんです。「その選択は今だけじゃなくて、20代、30代を通じた自分の姿を落ち着いて考えたものなの」と。それは確かにそうだなと。
Aさん いろんな人と話すのが大事かな。自分と違う考えを持っている人と話す中で「自分はこうだな」と気づける。(就職先の条件も)「お金でしょ」とか「福利厚生でしょ」とか「やりたいことでしょ」とか、わちゃわちゃ話していると、自分一人で考えるより頭の中がすっきりしてきますよ。
今回の座談会で印象的だったのは「自分が何をしたいのか」をもっと考えておけばよかったという、少し後悔を含んだ感想が目立ったことだ。そこがあいまいだったから、内定は得られても自分が納得できる決断へ至るのに時間がかかってしまったという苦い体験から出たものだった。
この反省の声は、これから就活にのぞむ学生にも記憶しておいてほしい。その上で、大切なことがもう一つあると思う。それは「自分が何をしたいのか」を考え抜いたうえで、それに縛られすぎないでほしいということ。答えはその後の経験で変わることもある。関心をもつことのなかったことに興味をひかれたり、自分らしさだと信じていたことが、案外そうでもないと思い知らされたりすることだって、きっとある。
最初に思い描いた通りの就活ができた出席者はいなかった。だけど「失敗」とも口にしなかった。就活で行き詰まることがあったら、そんな先輩たちが残してくれたメッセージを思い出してほしい。
(文・構成 藤原仁美、安田亜紀代)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。