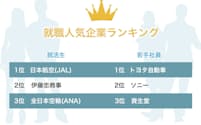就活本番の後輩へ私が伝えたいこと 体験談のお年玉
内定者座談会(上)

2020年が就職活動の本番となる後輩たちに、これだけは伝えておきたい――。春の入社を待つばかりの内定者4人が、自分の経験から得た気づきや反省を語り合った。決して順風満帆とは言えないストーリーは、就職を考えるU22世代一人ひとりへのヒントが詰まった「お年玉」だ。前編は数カ月前に終えたばかりの就活の実体験を中心にお届けする。(司会はU22編集長・安田亜紀代)
Aさん 明治大学4年の女子学生。広告制作会社へ就職予定。
Bさん 都内私立大学院2年の男子学生。大手メーカーへ就職予定。
Cさん お茶の水女子大学4年。金融系へ就職予定。
Dさん 法政大学4年の男子学生。証券会社へ就職予定。
――皆さん受けた企業数は多い方ですよね。たくさん受けた方がいいのでしょうか。
Cさん 私は50~60社にエントリーして、約30社で面接し、内定は8ついただきました。幅広くみたうえで考えるのが私の性格にあっていたので、たくさん受けたのは間違いではなかったと思います。ですが、最終的に働く会社はバイキング料理のように色々選べるというわけではないんですよね。私の企業選びの軸足は業界ではなかったので、内定先はメーカーからIT、金融まで様々。どこを優先順位にしておくかをもう少し考えておくべきだったなと思っています。
Bさん 僕の就活は長くて、10カ月ぐらいずるずるとやってしまって、結果的に約40社にエントリーし、6社から内定をもらいました。やはりバイキングではなくて「この1品」を選ばないといけないのが就活。グローバルとか社会貢献とか色々考えましたが、具体的にどう優先順位をつけていくか、最初は考えが足りなかった。漫然と説明会に行って、いい企業だなあと思って帰るけれども、結局は自分に何ができるんだろうって悩んでしまう時期がありました。
Dさん 僕は50社くらい受けて、選考まで進んだのは30~40社。金融・不動産・人材の3本柱でした。これまで何のために勉強を頑張ってきたのかと、思いっきり大企業をめざしました。
Aさん 私はたくさん受けて悩むのが嫌だったので、広告系を中心に10社くらい受けて、内定は3つ。大きな説明会には行ったことがないし、大学のキャリアセンターにも1回も行っていない。でも納得度は高くて、内定先と心の中の条件が合っていたんだと思います。
心の中の優先順位を明確に
――「心の中の条件」というのは。
Aさん 会社の人には言わないですけど、給料も平均より少し高くて、東京で働けるし、福利厚生も最低限は担保されていて、かつ、やりたい仕事ができる、というようなことですね。
Cさん 私は大学3年の4月から就活を始めて、比較的長かったので色々な情報が入ってきて、その結果、心の中の条件を作りすぎちゃいました。欲しいものがどんどん増えていった。最初は内定が欲しいということから始まって、次は転勤したくない、給与は高い方がいいとか。そのうち海外にも行ってみたいとか、海外研修制度っていいなとか。どんどんぶれてしまいました。
――心の中の条件を作りすぎるとどんなデメリットが?
Cさん 内定先を選べなくなってしまったのが最大のデメリット。たくさん条件があると、それをどう点数化したらいいのかわからなくなって、企業を絞れなくなったのです。
――結果的には働く環境を重視したんですね。
Cさん そこにはワナがあって、企業側は働く環境について本当のことを言ってくれるわけじゃないんですよね。転勤がないと人事が説明会で話していても、先輩からは「転勤あるよ」と言われたり。私は(転勤を想定しない)エリア総合職と、普通の総合職で迷っていて、金融の会社はどこも「両者は給与も仕事内容も同じ」って説明しているのですが、実際に社員から話を聞いてみると違うことがわかって驚きました。会社側が用意した座談会で社員の本音を聞けたつもりになっていると危ないなと思ったので、自分から社員の方にアポイントをとって、味方になって話してくれる人を見つけるようにしていました。
Bさん 説明会の内容って、自分で足を動かしてOBに確認してみないとわからないところがあります。
――選考で違和感を覚えたことありましたか。
Dさん 金融関連の会社から「質問会」という名目で呼ばれたのですが、実は選考だったことありました。1回目はリクルーター面談で、2回目は人事の方に質問をする会。選考とは言われなかったのですが、明らかに選考だなっていう雰囲気を感じ取ったので、自分をアピールできるような質問の仕方をしましたね。
――企業もあの手この手ですね。逆に皆さんは面接でウソをついたり話を盛ったりしたことありますか。
Cさん 鉄道関連企業の選考で同業他社も受けているかって聞かれたときに、本当はあまり受けてなかったのですが、たくさん受けていて今選考中ですって言ってました。正直に第1志望ではないと言ったところ落とされたことがあったので、それ以来、内定をもらうためにはウソも必要だと考えるようになりました。
Dさん 僕もまだ内定をもらった会社はなかったのに、他社の内定を持ってますって言ったことはありますね。あとは学生時代の実績で、少し数値を盛りました。本音だけでは社会でも生きていけないと思うので、相手に迷惑をかけない程度なら多少のウソはあってもいいんじゃないかと思います。
最後の最後は思い入れ
――納得できないこと、例えばなぜ落ちたのかわからないとかってありましたか。
Bさん わからないことの方が多かったですね。今思えば、何かを得ようとする、お客さん側の目線だったのかな。OB訪問で言われて気づいたのですが、仕事は誰かに何かを提供することなんだと。何かを提供したいと思える意欲があるのが大事なのかな。それがないと、ただ会社に何かを求めているだけの人間に見えてしまうのかもしれないですね。
Aさん 私は落とされたところについては全部納得できています。例えばウェブ系人気企業で「賢い人しか行けない会社。ここ受かったらかっこいいな、給与も高いし」って思って受けた。広告代理店も受けましたが、やりたいのは広告の制作だから、業務内容はやりたいこととちょっと違うなと思っていました。どっちもあまり思い入れがなくて、ウソがつけなくてばれちゃった感じです。
――色々なウソがある。そんななかで実際の就職先にどうやってたどり着くんでしょうか。
Bさん 最終的に通った就職予定のメーカーには、思い入れがありました。実は最後の最後に受けて8月に内定したんです。その前に内定が出ていたところに行こうと半ば決めつつ、でもまだ少し納得がいかないなとモヤモヤしていたところに、逆求人型のスカウトサイトからメールが届いた。話を聞くと、海外で働けるし、製品が環境に配慮されていたり、意外な用途を見いだしていたり、こんなに世の中の役立てる仕事があるんだと、心から思えた。他社の内定承諾期限もあったし、これからまた選考に進んでもしだめだったらリスクも高いし、ぎりぎりのところですごく迷ったのですが。すごくいい会社に巡り合えたという直感を信じて、踏み切って、そしたらとんとん拍子に決まった。思い入れというか、愛があったってことなんですかね。
(文・構成 安田亜紀代、藤原仁美)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。