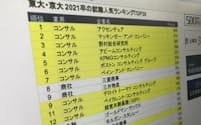大学での成長、カギは2年でギアチェンジ 先輩の経験
通年採用時代の就活のトリセツ(4)

法政大学キャリアデザイン学部でキャリア論を教えている田中研之輔です。今年は東京五輪が開かれる節目の年。日本の歴史に刻まれる瞬間となるでしょう。私は10年以上教員をしているなかで、皆さんの大学生活においても「節目」というものはあると思っています。言い換えると成長の瞬間です。今回特に読んでほしいのは、大学1~2年生の皆さんです。
私のゼミの初期メンバーは、もう大学を卒業して10年が経過しています。若手から中堅の時期に差し掛かり、それぞれの業界で活躍しています。皆さんの先輩たちが大学で出会い、学び、成長し、社会に出て活躍する姿を見てきて、今、どうしても伝えたいことがあるのです。
大学2年生の1年間の過ごし方が、その後の成長において極めて重要である、ということです。
大学の1年目は、横一線です。入試経路が同じであれば、学力は似通っています。しかし、4年後の「結果」が全く違ったものになります。
なぜだと思いますか? 大学生活をどう過ごしたのか、どう生かしたのか、が違うのです。
大学の「入り口」である「入試」や、「出口」である「就職」は、よく話題に上がりますが、大学での4年間の過ごし方や生かし方は、あまり触れられません。その理由は、外からは見えにくいですし、結果として現れにくいからです。
その過程を捉えるべく、「大学でどう過ごすと、いかに成長するのか」について、卒業を控えた4年生2人にインタビューを行い、振り返ってもらいました。この2人は、大学1年生の時から知っていて、学びの過程をみてきました。4年間で見事に成長して、それぞれ第1志望の企業から内定をもらい、今卒論執筆に打ち込んでいます。
2人を選んだ理由は、顕著に成長した学生のモデルになるからです。教員の立場からすると、この2人のように成長していく学生を1人でも多く輩出していきたいのです。
大学2年で「自分の市場価値」を知ろうとした
1人目は、松尾和哉さんです。「他の学生と同じで、強みがなかった」と振り返る松尾さんは、大学入学当初、時給1000円程度で塾講師をしていました。
しかし、4年生になった今では、インターンで培ったWEBマーケティングスキルを生かして時給換算で3000~4000円の仕事をしています。また、在学中に、独学でTOEICのスコアを400点以上向上させています。
松尾さんがまず考えたのは「自らの市場価値を知る」ということでした。時給1000円ではなく、時給1500円稼ぐには、何が足りないのか。それがうまくいくのか、いかないのかは、学生時代は失敗が許されますから、気にしなくていいのです。

「4年間、学んでみて思うのは、大学2年時に始めたインターンシップ経験が転機でした。インターン先では、主にWEBマーケティング業に従事し、WEBメディアの運営戦略立案と社内エンジニアと共同で立案した戦略を実行していきました。その仕事を始めた当初は、マーケティングなんてさっぱり分からなかったのですが、社員の方にマーケティング的思考の神髄のようなものを伝授していただき、その職種の面白さを実感することができました」
またそれと同時に、マーケティングや戦略立案の仕事は、あらゆる仕事の上流にあたるものなので、誤った戦略を立案し、実行の指示を与えてしまうと、社内の多くの人間に多大な影響を与えてしまうという責任感も感じました。実際に、まだその責任感を理解できていなかった頃、浅はかな企画を立案したところ、エンジニアの方に「仕事の指示をするということは、なぜその作業をする意味があるのか、何が優先すべき点なのかなど、全ての質問に答えられるようにしなさい」とアドバイスをもらいました。
「学生の間に、特定の職種のやりがいや責任感を知れるのは大きな経験となりました。その経験を基に将来的にはより大きな組織で、日本だけでなく世界的に影響を与えるようなマーケティング業務がしたいと思うようになり、就職活動の軸が決まりました。アルバイトの経験のみで、卒業後を決めてしまうのは、リスクだと思います」
松尾さんが、かなり実践的にビジネススキルを習得されてきた様子がわかりますよね。これを読んでみて、「自分にはできないなあ」と思った人に向けて、4年生の森千晶さんのエピソードをお話しします。
視点の転換で大学の授業への取り組み方も変わる
森さんは、大学入学直後から居酒屋でアルバイトをしていました。目的は、アルバイトでお金を稼ぐことでした。しかし、あるとき「このままアルバイトを続けていてもいいのか? 自分のためにならないかもしれない」と感じたようです。
そこでまず選んだ行動は、「アルバイトを辞めること」でした。それから、「自分は何に興味があるのか、何をやりたいのか」をじっくりと考える時間を持ったそうです。そこで自分のためにインターンに挑戦することを決めたと言います。
「何もわからないから、なんでも吸収してみる。なんでもやってみる、ということで、インターンをスタートしました。広告代理店のインターンでは、制作と企画に携わり、商品購入ページの作成も行ったり、その都度、社員からフィードバックをもらったりして経験値をあげていった」
そこで大きな学びとなったのが、「ユーザーの生の声を聞く」ことの大切さでした。それに気が付いてから、森さんが、大学の学びが180度変わったと話してくれます。
その言葉を私が言い換えるなら、森さんに起きたことは、「視点の転換」だと言えるでしょう。講義をただ座って聞くのではなく、自分ならどのような講義をするだろうか、と考える。グループワークに参加するだけではなく、どうしたらより良く議論を展開できるだろうか。大学に通う毎日も、発見の連続になるのです。
卒業を前にした松尾さんと森さんが教えてくれるのは、次の3点です。
(1)やりたいことが何も決まっていないから、悩み立ち止まるのではなくて、まずは、動き出してみることの大切さ。
(2)インターンでフィードバックをもらいながら、自分には何が向いているのか。どんな仕事が好きなのか、没頭できるのかを現場で学び続ける。
(3)ビジネスシーンで必要なことが明確になり、知識や情報が不足していることを痛感することで、大学での学びに、より真剣に向き合うことができるようになる。
なんとなくアルバイトなどを継続して、そのまま就活を迎える学生よりも、松尾さんや森さんが2歩も3歩もリードしていることがよくわかるでしょう。
私が伝えたいことは、2年生のうちにインターンをしましょう!ということではありません。高校生までの「受け手」の学びの延長に大学生活を位置付けるのではなくて、答えのない問いにも果敢に挑戦していく、「作り手」側へと変身する経験を自ら選びとってほしい、ということです。
大学2年生のときにこうしたギアチェンジができているかどうかが、その後に大きな影響を及ぼしているのです。大学3年生になると、どうしても卒業後の就職先のことをリアルに考えるようになります。就職活動を全く無視して何かに挑戦するというわけにはいきません。
別々に実施したインタビューでしたが、2人が共に口にした言葉があります。「大学2年生が、転機だった」と。
1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を14社歴任。著書に『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(日経BP社)など。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。