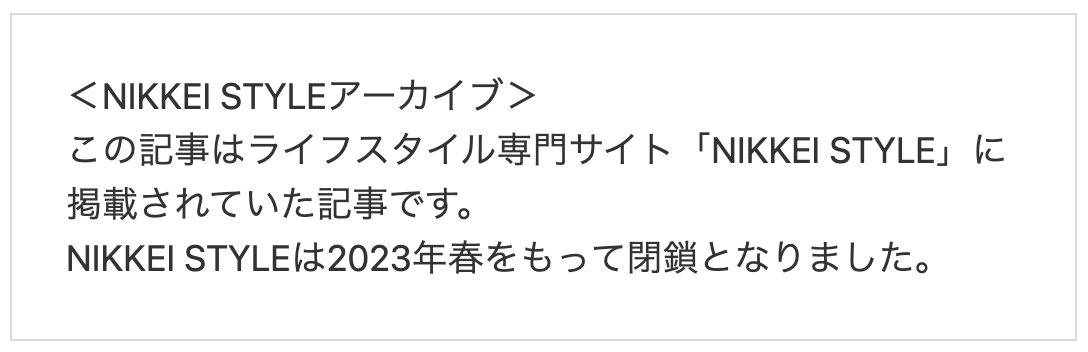男の鉱物、女のジュエル。
by Takanori Nakamura Volume 9
男と石と宝石。その関係を抜きにしたら、服飾史が成り立たないほど、男にとって鉱物は重要な存在である。その極みは、16世紀に遡る。当時の欧州は、宝石の効能をといた著作「鉱物誌」が広く流布していたことで護符としての価値も加わり、宮廷男子が身につける宝石は絢爛(けんらん)を極めた。
文=中村孝則 写真=藤田一浩 スタイリング=石川英治
(10)箱入りだから、こだわりも出る。>>
<<(8)ミッドナイト・サングラス。
■ダンディズムの象徴として輝き増す宝石
中でも、フランソワ1世とヘンリー8世は、その両雄である。川北稔著「洒落者たちのイギリス史」(平凡社)によると、ヘンリー8世は戴冠式に「白テンの毛皮の着いた深紅のローブ、金、ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、真珠その他の宝石類をちりばめたジャケットといういでたちで臨んだ」とある。
19世紀以降、装飾としての男の宝石はかなり控えめになったものの、ボー・ブランメルの登場以降、ダンディズムの象徴として、その輝きの存在感を進化させてきた。英国のエドワード7世(1841~1910)が皇太子であった時代、ロシアの有名な宝飾師のピーター・カール・ファベルジェに注文を出し、宝石をあしらった特製のカフ・リンクスを作らせたという。

出石尚三著「スーツの百科事典」(万来舎)によると、「これは一例で、19世紀のカフ・リンクスには、ダイヤモンドをはじめ、ルビー、サファイアなどの宝石をあしらい、主としてゴールドで仕上げられた」のだという。
■胸元の装飾としてロザリオに注目
キリスト教徒の護符であるロザリオのネックレスが、男性モードのアイテムとしてはやり始めたのは、ここ15年くらいからだろうか。粋なイタリア男性が、夏場にシャツのボタンを外すことをヒントに、胸元の装飾としてロザリオが注目されるようになった。

時を同じくして、シャツの台襟を高くして、第一ボタンが2つあるデザインが登場。ロザリオというエクスキューズは、ボタンを外して心もとない胸元を飾るための、格好のアイテムというわけだ。各宝飾ブランドが、ダイヤモンドをちりばめた男性用のロザリオをリリースした背景は、そのあたりにあるのだと思う。
ちなみにダイヤモンド・ジュエリーは、18世紀の半ばの欧州のあらゆる宮廷で、絶対的な地位を確立したが、この頃は女性のそれに劣らず男性用宝飾は耽(たん)美と粋を競ったという。
クレア・フィリップス著「V&Aの名品でみるヨーロッパの宝飾芸術」(東京美術)によると、その当時の最高峰と呼び名が高いのが、ドイツのトゥルン・ウント・タクシス侯カール・アンゼルムが1775年に作った、45個のダイヤモンドで壮麗に飾ったボタンのセットであるという。これは、今でもミュンヘンのバイエルン国立博物館に所蔵されている。
■洋の東西を問わず男に欠かせない真珠

厳密には鉱物ではないが、ジュエリーとしての真珠の存在も忘れてはならないだろう。先のヘンリー8世の装束にも多くの真珠が飾られたが、洋の東西に限らず真珠は男性の装飾品に欠かせない存在である。
仏教宝具から派生した数珠にも、ヒスイや水晶やラピスラズリといった石の他に、最近は真珠が使われるようになった。中でも紫系の真珠は、仏教的に高貴な色であることから、僧侶たちの間でもひそかな人気だという。宗教的な意味合いを超えて、男のジュエリーとして見立てるのも面白いアイデアだと思う。
■「海の泡」の鉱物
ダンディーな石は、何も装飾品に限らない。例えばメシャム・パイプである。僕が、初めてメシャム・パイプを買ったのは、2004年の夏のイスタンブールだった。有名なグランバザールの一番奥にあるメシャムの専門店で見つけた。
メシャムとは日本語で海泡石という。この石は、セピオライトという多孔質鉱物で、含水ケイ酸マグネシウムが主成分である。世にも不思議な鉱物で、磨くと象牙のように美しいマットな乳白色で輝き、目に見えない小さな穴が空いていて、一説によると水に浮くほど軽いことから、ドイツ語の海の泡(Meer Schaum)と呼ばれるようになったとか。

門外漢には全くピンとこないだろうが、このメシャムは放熱性が良く加工しやすいことから、高級パイプの材料として珍重され、今も昔もパイプ愛好家の垂ぜんの的である。良質なメシャムは主にトルコで産出されて、有名なトルコ人作家のものは、コレクターズアイテムになっている。
面白いことに、メシャムのパイプは使い込むと煙が染み込んで、べっ甲のようなトロリとしたあめ色に変化する。欧州の貴族たちは、まるで唐津のぐい飲みを愛玩するように、メシャムの味だしを競ったという。
これもパイプ愛好家にしか分かち合えない特権だが、メシャムのパイプで吸う煙は、ひんやりとして何とも言えずうまいのである。ある意味で、男にとって最もフェティッシュな石が、メシャムではないだろうか。
■紳士が持つべき象徴、万年筆
最後に、男の定番的なアイテムにダイヤモンドが飾られたストーリーで締めくくろう。1924年生まれのモンブラン「マイスターシュテュック」といえば、万年筆という機能を超えて、紳士が持つべき象徴として愛され続けている。キャップトップのホワイトスターが、差したポケットからも、すぐに分かるのが特徴だ。

ポケモン探しなんて言ったら、ファンに叱られるかもしれないが、実際にポケットのモンブラン探しが歴史的なエピソードになったことがある。1963年、ドイツのケルン市で、ゴールデンブック(芳名録)に、時のドイツ首相アデナウアーが署名する際、自分の万年筆が見つからないという珍事が起こった。その時、同席したジョン・F・ケネディがポケットからさりげなく「マイスターシュテュック」を差し出したという。
2010年、そのモンブランのキャップトップにダイヤモンドを飾った「マイスターシュテュック モンブランダイヤモンド」が登場した。43面体のホワイトスターにカットされたダイヤモンドは、未来のダンディーたちに、どんな物語を綴っていくのであろうか。
コラムニスト。ファッションからカルチャー、旅や食をテーマに、雑誌やテレビで活躍中。近著に広見護との共著「ザ・シガーライフ」(ヒロミエンタープライズ)など。
[日経回廊 9 2016年9月発行号の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。