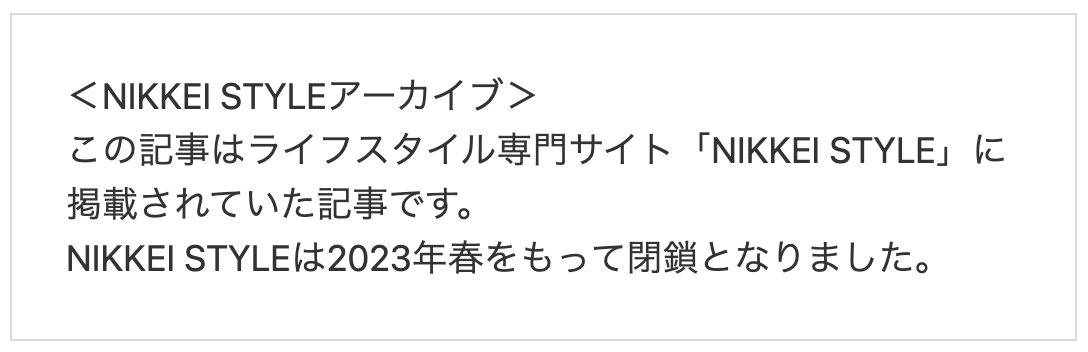実力派パティシエが福祉施設とタッグ お菓子で笑顔に

東京・銀座7丁目のビル1階にあるフランス菓子店「パティスリーカメリア銀座」。そのシェフパティシエ、遠藤泰介さん(35)は国内外のコンクールでの受賞歴など菓子職人としての実力で知られる一方、都内の2つの障がい者福祉施設とタッグを組んで新たな菓子作りに取り組む。「おいしいお菓子でみんなを笑顔に」をモットーとするパティシエは少なくないが、「どうすれば笑顔にできるか」を愚直に追求。一流の菓子作りを通じて障がい者たちに笑顔をもたらす挑戦は、それを地で行く職人といえるだろう。
2018年11月、銀座の一等地の画廊跡地に開業した「パティスリーカメリア銀座」は、コロナ禍にあっても元気な店の1つだ。今年4月に伊勢丹新宿店、6月には東京・渋谷の東急フードショーにも出店した。
銀座の店舗には常時、100種類を超す商品とともに、季節ごとの旬の洋菓子が加わる。10月初旬には目玉の1つとして新作の「ブールドネージュ」(フランス語で「雪の玉」の意味)が登場した。フランスの伝統菓子で、抹茶、フランボワーズ、ショコラ、ナチュールの全部で4種類。実はこのお菓子、レシピやパッケージデザインは遠藤さんが担当し、製造を担ったのは都内2カ所の障がい者自立支援施設。「調布を耕す会」(東京・調布)と、「ふれあい工房ゆめま~る」(東京・江東)だ。

時計の針を少し戻そう。昨年12月8日の夜。「調布を耕す会」の厨房で、遠藤さんによるブールドネージュの商品化に向けた初の講習会が開かれた。「丸めるなど工程がシンプルで、障がい者にもハードルが低く、誰でもおいしい味と感じられるから」。数あるお菓子の中から遠藤さんがこれを選んだのも、ちゃんとしたワケがある。

「いいですか。よく見ていてください」。ボウルに無塩バター、グラニュー糖、塩、薄力粉を入れ、ハンドミキサーで遠藤さんは手際よく攪拌(かくはん)していく。「ここであまり練り過ぎないでください。粘りが強いとサクサク感が出ませんから」
「えーっ!?」。何人もが驚いた。やはりプロの世界とは手法が違うのだ。練り加減やオーブンでの焼き具合……。施設の職員は熱心にメモを取り、施設長がハンディーカメラを回す。約2時間の講習で、4種類のお菓子を作り上げ、参加者全員で試食した。遠藤さんの熱意とやさしさに対する感動に、コロナ禍の暗闇にポッと灯った希望。それらが混ざり合い、スタッフらの心を温かく満たし、厨房内で笑顔がはじけた。「とってもおいしい」
きっかけは、その2か月ほど前。50年以上の歴史を持つ社会福祉法人「木下財団」(東京・中央)の東光篤子さんとの出会いだった。この財団は小規模な障がい者福祉施設への助成などを行っている。コロナ禍は社会に深刻な打撃を与えているが、福祉施設もその例外ではない。地域イベントが軒並み中止に追い込まれ、お菓子作りとその販売を通じた障がい者の社会参加の機会が激減。売り上げが減ったことで障がい者に工賃すら支払えない施設も急増している。
SDGsや企業の社会貢献が今、キーワードになっているが、「善意」だけでは限界がある厳しさも一方の現実。普通のお菓子を作るのでなく、各施設が品質を市販品と遜色ないレベルに高めないと。そのためにはプロの指導を仰ぐ必要がある。そう考えた東光さんが、打診した相手が遠藤さんだった。
頑張った分だけ利益が出るように
「やりましょう」。即断した遠藤さんにも戦略があった。「やる以上はとことん品質にこだわり、この取り組みを全国へ広げていきたい」。そのためには福祉をあまり前面に出さず、ひたすら品質で勝負する。「福祉のお菓子」では色眼鏡で見られ、逆に買いたたかれてしまうケースがあることを懸念したからだ。
「原材料の仕入れ先をできるだけ共通化し、ロットを増やす。そうやって原価率を下げ、一級品に仕上げられれば、障がい者も頑張った分だけ利益が出る仕組みができるはず」。そんな冷静な分析が根底にはある。カメリア銀座の店頭に「福祉のお菓子」をうたった広告類が一切ないのは、「品質で勝負」にこだわったからに他ならない。
なぜパティシエの道を選んだのかーー。遠藤さんは横浜市出身。父親が東京・平和島の道場で剣道師範をやっていた影響で、幼稚園から中学までは「剣道少年」で、剣道3段の腕前だ。パティシエを志すきっかけは、神奈川県立の高校時代。「ある洋食店でアルバイトした際、シェフが包丁でキャベツを刻んだり、フライパンでオムレツをひっくり返す職人芸を見て、『カッコイイなあ』と」
高校卒業後は東京・町田市の調理師専門学校で、和洋などあらゆるジャンルを一通り経験。その後、イタリア料理店などで修業したり、調理師学校や製菓学校で教えたり……。自分の「現場」が欲しくなり、「フランス菓子業界のピカソ」の異名を持つピエール・エルメの門をたたいたのが一大転機となった。剣道少年の時代から負けず嫌いで、「休日にも出勤し、菓子作りを重ね、あきれられた」こともある。

パティシエは誰とでもつながれる
パティシエの登竜門であるハンガリーでの菓子の世界大会で準優勝したことで、「ピエール・エルメ・パリ サロン・ド・テ イクスピアリ店」(千葉県浦安市、現在は閉店)のシェフを任された。その後も都内の有名ホテルで菓子職人としての腕を磨き、本場のパリで通用する菓子を作りたいと、自分の店を構えたのが3年前だ。
福祉施設とタッグを組んで誕生したブールドネージュ。お菓子作りを通じて仕事の舞台が広がり、「パティシエは誰とでもつながれる」と遠藤さんは実感する。カメリア銀座でのブールドネージュの出足も好調で、4種類・計120袋の最初の納品分は発売から約2週間でほぼ完売。月末までに計280袋分を追加発注し、施設側もうれしい悲鳴を上げた。
遠藤さんが監修したブールドネージュと、他の福祉施設の焼き菓子、高級コーヒー豆などをセットにした商品は、東光さんが立ち上げた「スイートハートプロジェクト(SHP)」でも既に販売している。SHPは福祉施設を応援する有志の会だ。様々な企業に呼びかけ、直接販売したり、ネット通販で新たな販路を開拓したり。そんな努力が実を結び、ジワジワとブールドネージュの評判も広がりつつある。軌道に乗れば他の福祉施設にも広げ、遠藤さんも次の菓子のレシピに着手する考えだ。
印象深いエピソードがある。遠藤さんの店で取材中、女性パティシエがケーキを手に「シェフ、これでどうですか?」と恐る恐るやってきた。遠藤さんはマスクを外し、ケーキの一片を口に運び、厳粛な面持ちで吟味した後、黙ってうなずいた。その瞬間、彼女の表情が一気に緩んだのを覚えている。

今年10月初旬、カメリア銀座へ再度取材に行くと、くだんの女性パティシエを呼び出し、「よかったら彼女の写真を1枚、撮ってもらえませんか?」と遠藤さん。一切の妥協が許されないパティシエの世界。叱責もつきものだが、「後輩たちが独立してやっていけるよう指導するのが、僕の役割でもあるのです」。
画廊の1枚ガラスをそのまま生かしてショーケースに見立て、店内の菓子やパティシエの仕事ぶりが見える「お菓子のテーマパーク」。それが遠藤さんの理想の店という。その言葉通り、ガラス窓の前には、テーマパークの舞台装置のごとく金色の飴細工のオブジェと、マカロンを飾ったケーキタワーがそびえている。
(ジャーナリスト 嶋沢裕志 、写真 遠藤 宏)
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。