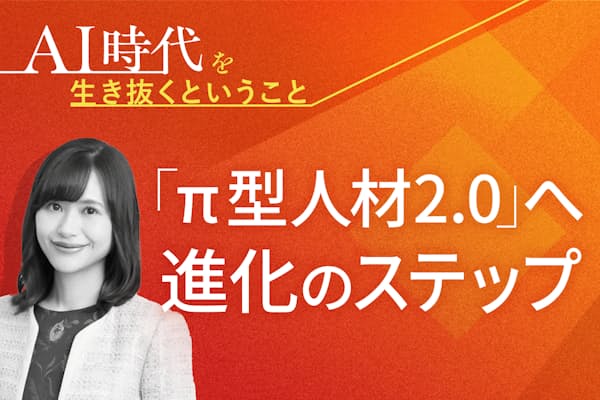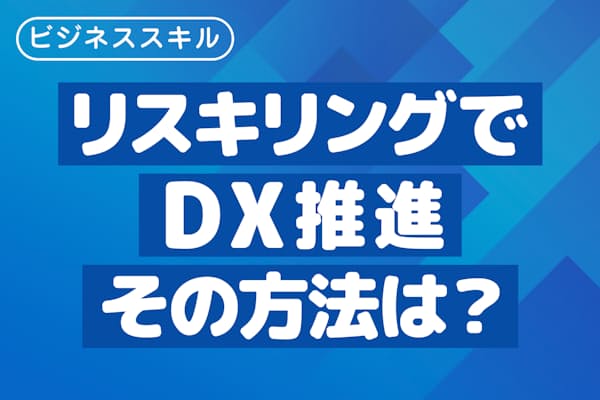副業促す動きが活発化、国もガイドライン改定 背景は
人生100年時代のキャリアとワークスタイル
働き方近年、副業・兼業への関心が高まりを見せています。2022年7月には、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定され、企業に副業を認めているかどうかなどの情報を公表することを促しています。副業・兼業を推進する背景には何があるのでしょうか。
副業に積極的な姿勢示す企業も続々
かつて副業と言えば、情報漏洩のリスクなどを恐れ慎重な姿勢を示す企業が多く、ネガティブなイメージが持たれがちでした。しかし、それはもう過去の話。パーソル総合研究所が21年に実施した調査(第二回 副業の実態・意識に関する定量調査)によると、副業を全面容認している企業が23.7%、条件付き容認が31.3%となり、合わせて55%の企業が副業を容認しています。
むしろ、企業側が従業員の副業を後押ししているケースも出てきています。例えば、社員の副業を推奨している三井住友海上火災保険は、副業を含む社外経験を30年には課長昇格の条件に据える方針を打ち出しています。一方、JTBはもともと副業を禁止していませんでしたが、コロナ禍以降に社内のガイドラインを整備、21年4月には柔軟に働く日を決められる「勤務日数短縮制度」を設け、増えた休日を副業に充てる働き方を可能としています。また、ライフネット生命保険では、同社に勤務しつつ自身が希望する事業・活動を前提とした働き方を認める「パラレル(複業)イノベーター採用」を18年から行っています。
副業人材の受け入れでも動きがあります。たとえば、創業以来、従業員の副業・兼業を可能とし奨励しているヤフーがその一例です。同社は20年7月、「ギグパートナー」という名称で年齢制限を設けない副業人材の受け入れを開始。20年10月には10歳から80歳までの104名と業務を始めたと発表し、大規模な受け入れが注目を集めました。このように労働市場における副業の状況は、ここ数年で一変しつつあります。
働き手の意識に大きな変化
リクルートが22年1月に実施した「兼業・副業に関する動向調査2021」によると、兼業・副業を「実施中」は9.4%です。現在していないが過去に経験ありという人は全体の8.8%と、経験のない人が多数派です。ただし、今後実施したい人(過去に副業経験なし)は40.9%と関心の高さがうかがえます。
特筆すべきは副業の仕事内容と本業との関係に、ここ1年で相当な変化が見られることです。20年版と比較すると「兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容とまったく関係がない」という回答が大幅に減り、「兼業・副業の内容は、主たる職業の仕事内容と非常によく関係している」もしくは「よく関係している」と答えた人(双方の合計)が20%から45.1%へ倍増しています。
おそらく新型コロナによる影響で、20年版は収入確保を目的とした副業が多かったのではないでしょうか。それが本業の経験を生かし、よりキャリアを意識したものへとシフトしているものと考えられます。
それを裏付けるように、「兼業・副業を実施して感じたこと」(対象は実施中もしくは経験者で今後も意向がある人、複数回答)を見ると、「本業から収入に追加して副収入が得られた」は20年版の43%が21年版では33.7%に低下しました。一方、「新しい知識やスキルを獲得できた」は20年版の25.4%から21年版は30.6%へと増加しています。
リモートワークの定着が進むなか、都市圏で働く人が地方の企業で副業を行う、いわゆる「ふるさと副業」が新しい働き方として注目されています。働き手からすれば、地方振興に貢献しながら働きがいを得られるメリットがあり、人材不足に悩む地方自治体にとっても即戦力を確保できるとあって、まさにWin-Winな関係と言えるでしょう。
副業・兼業は収入補塡の手段にとどまるばかりでなく、キャリア形成の手段として捉える向きが急速に広がっていると考えられます。そして、柔軟な働き方の選択肢の1つとして認知されつつあるのです。

写真はイメージ=PIXTA