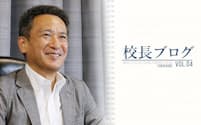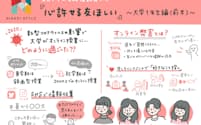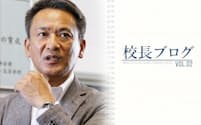先生ではなく「さん」で呼ぼう 人権意識は日常から
工藤勇一・横浜創英中学・高校校長
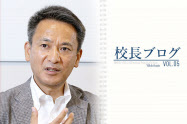
(質問を募集します。詳細は文末ご覧ください)
東京五輪・パラリンピック大会組織委員会会長だった森喜朗さんが女性蔑視発言問題で国内外から批判を受け、辞任に追い込まれました。差別問題で私が思い起こすのが米大リーグで活躍している投手のダルビッシュ有さんだ。
「パーフェクトな人間など誰もいない。彼もそうだし、あなたも、そして僕もそうだ。彼がやったことは決して正しいことではないが、僕は彼を非難するよりも、学ぶように努力すべきだと思う。ここから何かを得ることができれば、人類にとって大きな一歩だ。(後略)」。
2017年10月、ワールドシリーズ、ドジャーズ対アストロズ、第3戦、ドジャーズの投手だったダルビッシュ選手はアストロズの内野手ユリエスキ・グリエル選手にホームランを打たれた。ダイヤモンドを1周し、ベンチに戻ったグリエル選手が、目尻を指で横に引っ張りながら、スペイン語でアジア人の蔑称を口にした行為が大問題となった。
上記は、ダルビッシュさんが、試合後ツイッターに英語で投稿したコメントです。彼の対応に感心し、当時、千代田区立麹町中学校長だった私は全校集会でダルビッシュさんのこの話を例に人権問題について語りました。差別問題に対して世界のスポーツ界は非常に厳しい。実際、グリエル選手は来季5試合の出場停止処分を受けているし、NBAなどでは、オーナーが永久追放された例もある。その理由について考えてもらった後、話の終わりに次のように私は付け加えました。
「人を差別する心は、誰も簡単に消せるものではないかもしれない。また、消せたとしてもいつかまた生まれてきてしまうのかもしれない。長く生きた私でさえも自信を持って差別する心がないと言えないと思う。でも、ある行為が誰かにとっては差別になるということを知識として知ることさえできれば、そうした行為は誰でも止めることができる。みんなにもそうあってほしいし、私もそうありたい。人間は成長できるすてきな生き物だ」。
差別というか、人権の問題は簡単ではない。特に日本語は尊敬語が多く、本人はそう意識しなくても自然と目上、目下の上下関係をつくりがちです。歴史的に日本は縦社会でフラットな社会ではありませんでした。今も政治家や医師、弁護士、そして教師は「先生」と呼ばれ、互いに「先生」と呼び合うことも少なくありません。教師も生徒に対して「先生はね」と自分のことをいう人もいますが、私は新米教師の頃からこれに違和感を覚えていました。

この校長ブログの読者の方からも私の「さん」付けに関するお問い合わせをいただきましたが、教壇に立って以来、生徒には「僕はね」と語りかけ、今では先輩や後輩教師に対して「○さん」と呼ぶようにしています。もちろん給食や用務などの職員や、校外の業者など関係者にも同じく「さん」付けで統一しています。教師というのは、若い時から「先生」と呼ばれているので、知らぬ間に偉そうになっている人もいます。そういう私もレストランで食事したり、コンビニで買い物したりした際、「ごちそうさま」や「ありがとう」の一言を忘れてしまうこともあります。
後になって気づいて反省するのですが、まさに感性がさび付いている証拠。忙しかったとか、疲れていたからと言い訳をしがちですが、相手に対する尊重の姿勢がかけていたり、自分は客で相手よりは上だという意識が根底にあったりするからかもしれません。言語に対する感性、感覚は一度身につけたら、その後もずっとあるものではなく、常に磨き続けないと鈍ってしまうものなのだと私は思います。
「感性を磨く」をテーマに麹町中の「学校便り」に新聞の投書欄に載っていたエピソードを紹介したことがあります。ある初老の男性が電車のなかで小学生の少女に「お席いかがですか」と声をかけてもらったそうです。
「お席どうぞ」ではなく、「いかがですか」という表現に少女の思いやり、この言葉を選んだ感性がうかがえます。男性は初老ですから、「どうぞ」と単純に席を譲られそうなれば、「自分は元気だ。そんな年じゃない」と不快に思う懸念もあります。しかし、「いかがですか」であれば、「いや、ありがとう。大丈夫です」と断りやすいかもしれない。この言葉には相手を気遣う繊細な思いが込められています。
学校内の人権意識のフラット化も進めてきました。2020年まで6年間、麹町中の校長を務めましたが、その間に職員室の雰囲気は変わり、教師たちは年齢に関係なく、自由に発言する空間になっていきました。20代の若手教師が40~50代の先輩教師にはなかなか自分の意見は言いづらいという学校は少なくありません。しかし、そんなモノの言えない教師が「自律した生徒」を育てられるでしょうか。主体的な生徒の育成にはまず教師がそうならなくてはいけません。
着任後すぐに私は「教職員心得」を作成しました。(1)全員が当事者たれ(2)常に尊い命を預かっていることを忘れない(3)社会人、公務員として「幅広い常識をもって、円滑な対人関係を築くことができる」ことが大事――。など、まだまだ続く心得ですが、この(3)のなかに、教師同士の互いの呼び方は、「さん」で、生徒の前でも互いに「さん」で呼び合う、とういう項目を入れました。実際、浸透するのに3年ほどかかりましたが、麹町中の職員室は各教師が活発に自分の意見を言い合える場になりました。
「さん」付けで呼び合うなどは、小さな習慣に過ぎませんが、常に意識をしていかないと、いつの間にか差別を容認する社会になってしまうかもしれません。人権感覚と言語感覚は切っても切り離せないものだと私は考えます。人権感覚を磨くためには、言語感覚を磨いていかねばなりません。私自身これからも肝に銘じて努力していきたいと思っています。
1960年、山形県生まれ。東京理科大学理学部卒。1984年から山形県の公立中学校で教えた後、1989年から東京都の公立中学校で教鞭をとる。東京都教育委員会などを経て、2014年から千代田区立麹町中学校の校長に就任。宿題や定期テスト、学級担任制などを次々廃止するなど独自の改革を推進。2020年4月から現職。
質問を募集します
読者の皆様から、「校長ブログ」の先生方への質問を募集します。n22_info@nex.nikkei.co.jpにメールでお送りください。メールの件名に【校長ブログ】、本文に質問内容とハンドルネーム、年齢をお書きください。たくさんの質問、お待ちしております。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。