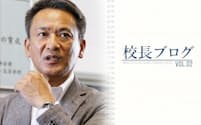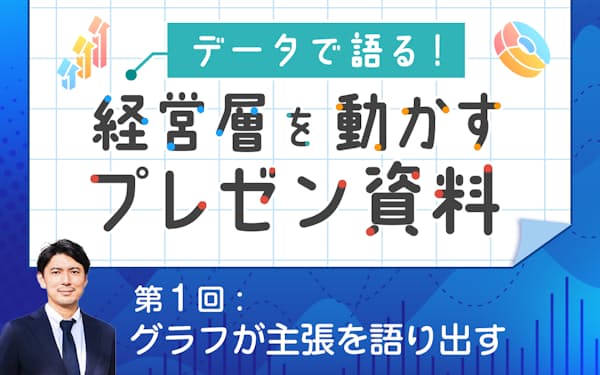渋幕・渋渋校長が説くキャリア教育 舞台はグローバル
田村哲夫・渋谷教育学園幕張中高兼同渋谷中高校長
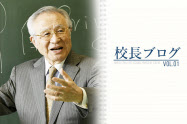
JAXA、レノボも渋渋、渋幕の生徒に国際的な評価
新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、渋渋や渋幕からビックリするような生徒が次々誕生しています。宇宙航空研究開発機構(JAXA)がアメリカ航空宇宙局(NASA)の協力を得て開催する国際的なロボットプログラミング競技会で、渋渋の中学3年生、佐藤裕成アレックスくんが率いるチームが優勝しました。国際宇宙ステーション「きぼう」で、ドローンを使って、ステーションの不具合を解消するためのプログラミングを競うという大会。2020年6月に日本代表に選ばれ、同年秋の国際大会で勝利しました。
もう一人は渋幕の高校1年生の立崎乃衣さん。同年10月にパソコン世界大手のレノボ・グループから世界を変える若手女性10人のうちの1人に選出されました。世界の主要10カ国で1万5千人以上を対象に国際調査を実施、女子高生は立崎さんだけだそうです。コロナ禍の医療機関を支援するため、3Dプリンターを使って800人分のフェイスシールドを設計、製作して医療機関に提供した活動が評価されました。
もちろん両校でプログラミングなどを教えているわけではありません。自主的に学び、身につけた知識を生かし、成果を上げたのです。これは学業で優秀な成績をとるのとは根本的に違います。個人として自己成長を遂げ、実際に社会課題の解決につながる成果を上げたのです。
変わる出世の階段 キャリアを意識し、自己を磨く
これは彼らが明確なキャリアに対する意識を持ち、自己を磨き上げているからだと思います。ミュージカル「レ・ミゼラブル」に出演する女優の熊谷彩春さんも渋幕出身。在学中に史上最年少でコゼット役に抜擢されて話題になりました。将来的には海外も視野に入れたグローバルな女優を目指しているようです。一般の中高生は、大学受験を目標に国英数など既存の教科を学ぶ生徒が大半でしょう。いい大学に進み、いい企業に入社し、努力して出世の階段を歩む。しかし、それで本当のトップリーダーになれるでしょうか。
昨年、化学メーカーの国内最大手、三菱ケミカルホールディングスの次期社長にベルギー出身の経営者が内定したというニュースが流れました。名門企業がわざわざ外部から招聘するわけです。もはや終身雇用の時代ではなく、日本も昔ながらの出世の階段を黙々と歩んでいればいいという時代ではありません。そのことを生徒たちは気づいています。
校長講話で「自調自考」を身につけた生徒づくり
明らかに今、日本の教育界は変革期にあると思います。グローバル化やデジタル化が加速度的に進む中、従来の詰め込み教育は限界に来ています。渋幕や渋渋は、東大合格者を飛躍的に伸ばした学校としてメディアに取り上げられますが、単純に受験校をつくりたかったのではありません。
グローバルな舞台で活躍できる人材を育てたかったのです。そのために教育理念として、自分で調べ、考える「自調自考」を掲げました。学校側が一方的に知識を教えるのではなく、自立的に学ぶ姿勢を身につけて欲しいと考えたのです。同様の理念の学校は他にもありますが、私は創立以来、全生徒に対する「校長講話」を続けています。中1から高3までの成長過程に応じたシラバス(授業計画)を綿密に設計した教養講座的な授業で、いわゆる欧米の学校で重視しているリベラル・アーツ教育です。古今東西の哲学や思想、文学などを題材にし、生徒たちに語っています。人生や自由などついて生徒側は考え、論文も真剣に書いています。

「自調自考」を身につけた生徒は、将来のキャリアを考え、様々な進学の選択肢を求めます。東大もいい大学ですが、米欧やアジアの有力大も選択肢の一つになります。その入試対策や準備のため渋幕、渋渋には外国人スタッフも常勤しています。米欧に生徒を送るには国内進学と異なる負担が学校にも生徒・保護者にもかかりますが、両校では毎年それぞれ10~20人が海外の有力大学に進んでいます。半分の生徒は帰国子女ではなく、普通の一般生です。
コロナ禍でも海外大がオンライン説明会
好循環が生まれたのは、ロールモデルになる人材が出てきたからです。渋幕は4期生に日本マイクロソフト社長を務めた平野拓也くんがいます。渋幕で初めてダンスパーティを開催した積極的な生徒でしたが、米国の大学に進みました。渋渋では6期生にハーバード大学に進み、フェイスブックの米本社に入社した内山慧人くんがいます。東日本大震災などの災害対策に対応した画期的なソフトを開発、それが創業者のザッカーバーグ氏の目に留まったそうです。
毎年6月になると、渋渋、渋幕の卒業生が進学している米欧の大学6~7校の関係者が学校説明会に来てくれます。彼らはアジアツアーを組んで優秀な生徒を確保しようとしているのです。必ず卒業生が付き添い、100人以上の在学生や保護者の前で大学のメリットや苦労話をしてくれます。結果、海外大に挑戦したいという生徒が増えます。留学には多額の費用がかかりますが、「柳井正財団」など留学支援の奨学金も充実してきました。20年は柳井財団から両校の各2人が助成の対象に選ばれました。感謝なことに有力大に合格すれば、相当の奨学金が支給されます。
コロナ禍の中、20年は説明会がすべてオンラインになりました。米国の大学でも入試対応の事務処理が大変になっているようで、「成績書を再発行して欲しい」など異例の要請をしてくる大学もあります。しかし、生徒たちはめげません。コロナ禍を理由に海外大の志望を変えた生徒はいません。彼らは明確なキャリアを考え、志望先を決めているからです。キャリアを意識して自己成長を目指す生徒は強い。今年もアッと驚くような生徒が飛び出すでしょう。
麻布高校を経て東京大学法学部卒、1958年に住友銀行(現三井住友銀行)に入行。62年に退職し、父親が運営していた渋谷女子高校を引き継ぐ。70年から渋谷教育学園理事長。校長兼理事長として83年に同幕張高校、86年に同幕張中学をそれぞれ新設。96年に渋谷女子高を改組し、渋谷教育学園渋谷中学・高校を設立。日本私立中学高等学校連合会会長も務めた。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界