大学に入った意味って何? 新入生の自問自答と気づき
コロナ下のU22座談会(2)

新型コロナウイルスの感染拡大によって授業がオンライン化、課外活動も制限されてきた大学1年生4人に座談会で2020年の大学生活を振り返ってもらった。後編では、コロナ下で感じた大学の意味、今後やりたいこと、高校生へのアドバイスを聞いた。(司会はU22編集長・安田亜紀代)
【前回記事】心許せる友ほしい 大学1年「オンラインだけでは…」
Aさん 東京都内にある国立大商学部に在籍する女性。体育会応援部に所属。
Bさん 都内私大の国際系学部に入った女性。多様性に関心。
Cさん 都内の私大経済学部の男性。就活相互支援の学生団体でリーダー役。
Dさん 九州にある国立大法文学部の女性。学生向けメディアの運営団体に所属。
――座談会前半では、制約された環境のなかで大変だったこと、そのなかでも自分の得意なことや興味のあることを見いだしてきたお話を聞きました。今の状況が長く続くことについては率直にどう思いますか。
Bさん すごく嫌なわけでも、うれしいわけでもないのが本音です。人に会えないのはさみしいですが、時間を自由に使えるメリットもあります。今は夜型の生活リズムになっていて、電車にも全然乗ってないですし、普通の通学生活に慣れるためにはちょっと時間が必要ですね。
Cさん 実はあまり不安はないです。大学には多くを求めていないので。オンラインのイベントなどで、普段は会えないような人たちや社会人と関われるので、そういうチャンスに飛びつける環境だと捉えています。ただ、そこで飛びつける人とそうでない人で、格差が生まれそうだなとは思います。
海外へのハードル下がった
――Cさんの言うとおり、今までにない機会もありそうですね。実際、意外とプラスだなと思ったことはありますか。
Bさん 私の高校に通っていた留学生の日系ブラジル人の友達と、お互いの言語をオンラインで教え合っています。日本語を教える日とポルトガル語を教える日をそれぞれ週に1回ずつ、5月から続けています。もしコロナ下じゃなかったら、海外の人と一緒に何かをしようとはならなかったと思います。ブラジルの子と語学を教え合うということはすごく大ごとのように捉えていた気がします。
Aさん 確かに海外に対するハードルは下がった気がします。最近、たまたまサイトで見つけた仕事で、ベトナム人に日本語をオンラインで教えるプロジェクトがあって、そういうところにもあまり抵抗なく参加できるようになりました。
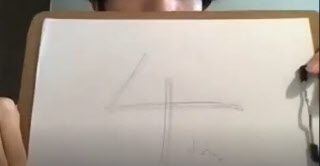
――不安や不満もありつつ、それぞれ成長機会があったようです。1年目の大学生活、5段階で評価するとどうなりますか(以下、カッコ内の数字はそれぞれの評価)。
Bさん 「4」 前半でお話しした通り、マイナスのスタートだったのでよくここまでやってこれたなという思いもこめて。人に会えないからこそ、自分のことを振り返る機会になりました。1つのことを極めている人に対して劣等感があったのですが、色々なところにつながりがあるのが私の強みだなと思えるようになって。これまでのネットワークを生かし、大学で障害についてのイベントも企画できたので、その実現は自分のなかで大きかったです。
Cさん 「4」 大学以外のところで、就活(の相互支援)に取り組む学生団体やインターンなど、やりがいのあることを見つけられたので比較的満足しています。5じゃなかったのは、レンタカーを借りて友達と旅行するなど、もうちょっと大学生らしいことができたらよかったなというぐらいです。
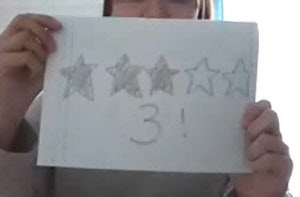
Dさん「3」 旅行はしたかったですね。(大都市に比べて感染者が少ない)地方は、少しでも感染者が出ると(特定しようと)大騒ぎになる。万が一、自分がコロナに感染したらと思うと、怖くて旅行には行けませんでした。
Aさん 「3」 私が中高で通った女子校は良くもあしくも似たもの同士が多かったので、大学ではいろんなタイプの学生と切磋琢磨(せっさたくま)しあえるかなと期待していたんです。でも大学もわりと似た人が多いかなというのが正直なところ。「こんな人がいるのか」と驚くほどヤバい人にはまだ出会えてないです。
――もし高校生に戻ったら、今の大学・学部を選ぶと思いますか(カッコ内は回答)。
Aさん 「選ぶ」 比較的少人数の大学で、学部間の垣根も低く、他学部の科目もたくさん受けられるので楽しいです。コロナ禍を前提に大学を選ぶなら、少人数であることをひとつの基準にするのもありだと思います。(多数が集まるのを避けるためオンライン主体になりがちな)規模の大きい大学に比べたら、対面や双方向の授業はやりやすいですから。
Bさん 「選ぶ」 私が入った学部も必修が少なく、他学部の授業が色々とれます。高校の頃から(芸術の力で医療現場を快適にする)ホスピタルアートや人権問題、教育、メディアなど興味のあることが本当にたくさんあって大学選びも悩んだのですが、ここは教育学部の授業も受けられるので、学びたいことは学べているなと思います。
Cさん 「選ばない」 経済学部なんですが、全然自分のやりたいことと違うなって感じています。より実践的なことが学べる経営学部や心理学やコミュニティー論を学べる社会学部がよかったかなと。ただこれは学生団体やインターンなどの活動をやってきた今だから思えることなので、高校生の自分に言えるとしたら、志望を考える際は学校の外にも目を向けてみようという感じですね。
Dさん 「選ばない」 第1志望の大学じゃなかったというのもありますが、関東と地方では全然違うんですよね。関東の学生と話すとやはりキャリアなどへの意識が高くて活動的な人が多いので。地方の高校生にアドバイスするなら、コロナの影響で関東の大学を目指す人が少なくなっていると思うんですけど、コロナだけに惑わされて決めないで、と言いたいです。
――コロナ禍によって大学の選び方も変わってきそうですよね。皆さんは大学の意味や価値について、どう考えていますか。
Bさん 正直よくわからなくなりました。新たな視点を得るという意味では、オンライン授業でも、打ち解け合うまではいかなくても議論は成立するので、自分と違う考え方も学べる。友達関係も広ければいいというものでもないと考えると、大学に通うって一体どんないいことがあるんだろう? 普通に通えるようになったら見つけていきたいなと思います。
Aさん 私はさらに専門的な知識を学ぶ場だと思って受験していましたけど、思ったよりも課外活動が占める割合が多くて驚きました。人との出会いが大学の価値かなと今は思っていますが、一方で勉強もおざなりにはしたくないとも思ってます。
Cさん 4年間の自由な時間がある大学生の身分をもらうための場所です。コロナ前は好きな学問を学ぶ場所、人に出会える場所、と思っていましたが、今はそれを大学に求めてないです。学んだり、出会ったりは、大学でなくてもできるとわかりましたから。
Dさん 私は高校のとき、大学での研究が職業と結びつくものだと思っていたんですね。でもゼミの説明会で「将来やりたいこととは切り離して考えてください」と書いてあって、少し驚きました。学生団体の先輩の就職先を見ても、あまり研究と直結してなくて。大学生活って勉強のためというよりは、暇な時間を確保して自分探しをするみたいな感じなのかな、と今は思っていますね。
コロナ下で感じたことも大事に
――これから入学してくる学生へのアドバイスはありますか。
Cさん 課外活動も探せば色々あります。Facebookのイベント検索がオススメで、無料で参加できるものが結構ヒットします。イベント会場に早めに入って運営の方と話すとさらに面白いですよ。セッティングを手伝いながら、「将来何をしたいか」といった相談もできました。
Aさん 大学生活の前に、1つ具体的な目標をつくった方がいいと思います。モチベーションがそがれがちなオンライン授業でも、目標を持てている人は強い。それに大学は思った以上に自由で、その状態にのみ込まれてしまうと、あっという間に時が流れてしまうと感じたからです。
Dさん 1年生のうちからネット上にアンテナを張って、自分が成長するためのチャンスを探してください。コロナ下では学校や友達から情報を仕入れることが難しいからです。自分と向き合う時間は増えるので、ぜひ日記でもスマホのメモでもなんでもいいので、自分の性格や特徴を記録してみてください。自分のやりたいことを見つけるのに役立つはずです。
Bさん 友達をつくりにくい環境かもしれませんが、その分、友達に気をつかったり流されたりせず、興味のある授業、やりたい課外活動に取り組めると思います。SNSには依存しすぎず、必要な情報を得られるよう活用するのが大切かと思います。そして、コロナ下で自分が何を感じ、何に気づいたのか、そういうことも大事にしてほしいです。新たな自分を知り、その後の大学生活に生かせることもあるように思います。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














