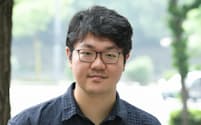自分で考え、やってみる ノーベル賞の土台は「経験」
ノーベル物理学賞 天野浩さん(上)

明るくて省エネルギーにもなる白色光源を実現した青色発光ダイオード(LED)。その発明によって2014年にノーベル物理学賞を共同受賞した名古屋大学教授の天野浩(あまの・ひろし)さん(60)は、成否のカギだった窒化ガリウム(GaN)の結晶づくりなどで1500回を超す実験を繰り返したサイエンスアスリートだ。インタビュー前編では、そのエネルギーの源をさぐる。
深紫外線LEDでコロナに挑む
――新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。ご自身の考えなどに変化をもたらしていませんか。
「大学で講義ができない、実験できないつらさを、身をもって知りました。そして長いスパンの研究ではなく、いきなり突きつけられた課題の解決に貢献できないか、頭がぐるぐる回るような体験もしています」
「ちょうど私たちはウイルスを不活化する光源である深紫外線(しんしがいせん)LEDの開発に取り組んでいたので、それを使用した感染対策ができないか検討しています。最前線で戦う医療従事者が安心して医療できる仕組みを、できるだけ早くつくりたい。そのうえで、その仕組みを飛行機や列車、人が集まる劇場などにも応用できたらと考えています」
――ノーベル賞がもたらしたご自身の変化で大きなものは。
「自分の技術をいかに磨いていくかという発想から、世界とか社会のために、どう貢献すべきかという考え方に180度変わりましたね。受賞前までは、自分の強みをもとにして研究テーマを考えていたのですが、やっぱりそれだけでは不十分だな、足りないなと。研究者といっても、もっと社会に貢献するというところから考えないといけないんじゃないかと、考えが変わりました」
――1960年(昭和35年)に製造業の盛んな浜松市にお生まれです。教育熱心な家庭でしたか。
「まったくそんなことはなくて、勉強しろと言われた記憶がないですね。父は仕事人間だったんですけど、日曜日にはよく外で遊んでくれました。小学校時代は地区大会のあったソフトボールや、小学校に部活のあったサッカーに熱中していましたね。サッカーのポジションはキーパーでした」
――通知表の成績はよかったのでは。
「全然記憶がないんですよ。成績は算数だけが『5』だったほかは覚えてない。遊びが好きな普通の子どもでしたよ。(算数好きの理由は)何だろうなあ……。きちんと答えがひとつに決まるみたいなところがわかりやすかったんでしょうねぇ、きっと」
――本などで科学者に憧れることは。
「まったくないですね。われわれの時代の憧れは(プロ野球の巨人で活躍した)王選手と長嶋選手ですよ。本で読んだのはまず『怪人二十面相』『怪盗ルパン』『シャーロック・ホームズ』の推理小説。あとはマンガばっかり。小沢さとるさんの『サブマリン707』『青の6号』とか。一番感動したのは、ちばあきおさんの『キャプテン』ですね」
――中学で力を入れたのは。
「中1のときにアマチュア無線で電話級(現在の第四級)の免許を取ったんです。上空にスポラディックE層という電離層が発生すると、電波が遠くまで飛ぶんですね。それで北海道の人と話せたりするのが、すごく楽しかった。始めたきっかけは友人に誘われたからかなぁ……。父がテレビで見ていた海外ドラマの『コンバット!』に、でっかい無線機が出てきたんですが、それをかっこいいと思ったことも、つながっているかもしれない」
――地元の公立小中から進学した高校、大学はいずれも第1志望ではなかったというのは本当ですか。
「本当ですが、進学した県立浜松西高校では、数学の楽しさをより深く教えてくれた恩師に出会うことができました。振り返ってみても、西高がよかったと思っています」
「大学は京都大学の数学科をめざしました。フィールズ賞を受賞していた広中平祐先生が京大にいて、かっこいいなと。ですが共通1次試験が全然できなくて、京大は無理と考えました。アマチュア無線をやっていたし、数学より工学の方が就職に困らないとも思って、名古屋大の工学部に志望を変えました。極めて現実的な判断です。夢のない話に聞こえてしまうかもしれませんが」
――中高時代、将来の夢を聞かれたら何と答えていたのですか。
「小説家になりたい、と言っていたかな。本はよく読んでいて、中学のころは(多くのショートショート作品を残した)星新一さんが一番。高校ではいろいろ読みましたが、最も記憶にあるのは庄司薫さんの『赤頭巾ちゃん気をつけて』(1969年芥川賞)です。数学が苦手だったら文系に行っていたと思います。文系科目が得意というわけではないですけど」
大学で気づいた「何のために学ぶのか」

――大学生になって学問への姿勢は変わりましたか。
「本当に勉強が面白いと思うようになったのは大学に入ってからです。それまでは何のために学ぶんだろうとずっと考えているだけだったのですが、工学部の講義で年配の先生が『世の中の役に立つ、人の役に立つためにやるのが学問なんだ』と話されたのを聞いて、初めてわかった気がしたんです」
「実験は自分で考えて、自分でやる。装置も自分で組み立てる。それがこれほど楽しいものだとは、思いも寄らなかった。これはやってみないとわからなかったと思います」
――もし他者から「何が楽しいのかわからない」と言われたら、どう答えますか。
「正直に言うとですね、自分が楽しいのだからいいじゃん、です。他人の迷惑になったらいけませんけど、楽しいかどうかに他人は関係ない。石英管(=ガラス管)をきれいに曲げる手法を発見しながら加工したり、コイルをぐるぐる巻いたり、私にはそういうことが面白かったんです」
――面白いと思える何かに出合うには何が必要でしょうか。
「『経験』がすごく大事だと思うんですよね。面白いと感じるものは人それぞれだから、大学生になったら最初からいろいろ経験してみてほしい。何かを経験して『これ詰まらないや』とわかるのも発見ですから、無駄なことなんて全然ない」
「経験(を意義あるものにする)にはある程度、自分で考える力がないといけません。高校までに自分で考える力をつけておくことができればいいなと思うんですよね」
(聞き手 天野豊文、撮影 上間孝司)
1960年、静岡県浜松市生まれ。83年名古屋大学工学部卒。88年に同大院工学研究科博士課程単位取得満期退学。同大助手の89年に工学博士号を取得。名城大教授などを経て2010年から名古屋大教授。14年、青色LED発明の功績で、赤崎勇、中村修二両博士と共にノーベル物理学賞を受賞。同年、文化勲章。現在は名古屋大の未来エレクトロニクス集積研究センター長も務める。著書に「次世代半導体素材GaNの挑戦」(講談社)など。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。