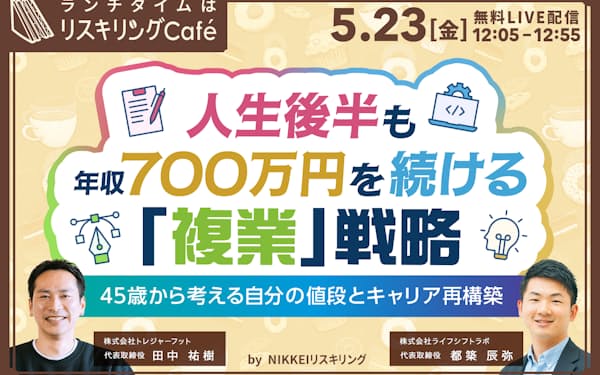89年ぶり気温54.4度を記録 地球はどこまで暑くなる?

2020年8月16日、米国西部を熱波が襲い、カリフォルニア州デスバレーの気温は摂氏54.4度に達した。これは1931年以来の最高記録で、世界の観測史上で3番目に高い。
だが、地球の歴史をさかのぼれば、もっと暑い時代はあった。そして将来、再びそういう時代がくるだろう。その暑い時代は「温室期(ホットハウス・ピリオド)」と呼ばれる。現在の南極にあるような氷床が地球になかった時代で、大気中に温室効果ガスが過剰に供給され、地球の気温は現在よりもはるかに高かった。
今のところそこまでは達していないが、人間が排出する炭素は地球の気候を変え、熱波はその頻度と激しさを増している。つまり、デスバレーの高温記録がずっと塗り替えられない可能性は低いということだ。
灼熱の過去
意外に感じる人もいるだろうが、地質学者に言わせれば、地球は現在「氷河時代(氷室期)」にある。その中で、極地の氷床が増えたり減ったりという「氷期/間氷期」のサイクルを繰り返している(今のところ、北半球の氷床は、グリーンランドまで後退している)。今よりはるかに暑い世界とはどのようなものなのか、それを垣間見るためには、少なくとも5000万年前の始新世初期にさかのぼる必要がある。
「それは、地球が本当に温室化していた最後の時期です」と、米アリゾナ大学の古気候学者ジェシカ・ティアニー氏は話す。
現在、地球の平均気温は15.6度前後だが、始新世初期には21.1度ほどだった。地球は、別世界だった。極地に氷はなく、熱帯の海は35度もあり、まるで温泉のようだった。北極にはヤシの木が生い茂り、ワニがうろついていた。
さらに過去へさかのぼれば、より極端な温室期もあった。9200万年前、白亜紀の超温室期には、地球の表面温度は約29.4度に上昇した。この高温の時期は数百万年も続き、南極の近くには温帯雨林が繁茂していた。
米スミソニアン協会の予備研究によれば、2億5000万年ほど前、ペルム紀と三畳紀の境には、極端な地球温暖化現象が発生し、地球の平均気温は32.2度前後を推移する期間が数百万年も続いた。
その地獄のような時代に、地球は史上最悪の大量絶滅を経験した。熱帯の海は熱い風呂のようだった。ペルム紀の日々の気象データは知る由もないが、超大陸パンゲアの乾燥した内陸部では、先日デスバレーを襲ったような熱波は日常茶飯事だった可能性が高い。
「平均気温が高いほど、極端な熱波がより頻発するようになります」と、ティアニー氏は話す。
温室化する未来
地球の温室期には、どうやら1つの共通点がある。温室化に先立ち、膨大な量の温室効果ガスが大気中に放出されていたことだ。それは、火山の噴火で吐き出される二酸化炭素だったり、海底下から噴き出すメタンだったりした。
現在、人間は、これと同じことを地球規模で実験しているようなものだ。私たちは、埋蔵されていた膨大な量の化石炭素を燃やし、大気中の二酸化炭素濃度を上昇させている。そのペースは、恐竜が絶滅した6500万年前以降、いや、おそらくそのはるか昔からでも、見たことのない速さだ。
「過去の急激な気候変動を見ると、たいてい、私たちが今日行っているのと同様のメカニズムで起きています」と、米マサチューセッツ工科大学の地球科学者クリスティン・バーグマン氏は言う。「温室効果ガスの濃度が、かなり急速に変化しているのです」
近年の記録的な気温は、人の影響なしでは、ほぼ起こり得なかったと結論づける研究が相次いでいる。私たちが大気中に炭素を排出し続けると、地球はどこまで暑くなるのか。
正確に予測することは難しいと、専門家は言う。「将来の熱波の気温の上昇幅は、どれほど遠い未来を予測するか、どれだけ多くの二酸化炭素を私たちが排出するかに大きく左右されます」と、米ローレンス・バークレー国立研究所の異常気象の研究者マイケル・ウェーナー氏はメールで回答した。
しかし、ウェーナー氏らのチームによる最近の研究で、私たちが炭素排出量をまったく削減しない場合に将来の熱波がどのようなものになるのかを、のぞき見ることができる。今世紀の終わりまでに、米カリフォルニア州の熱波の最高気温は、現在よりも約5.6~7.8度も高くなる可能性がある。
先日のデスバレーの気温の記録は、100年に1度しか起きないレベルのものだったのだろうか? 「私の予測では、起きる頻度としては現在と同じくまれなものの、今は54.4度で済んでいる気温は、温室効果ガスを大量に排出した未来においては約60度になることでしょう」とウェーナー氏は話す。
金星と同じ運命をたどるのか?
だが、はるか未来の地球の運命に比べれば、5度や10度の上昇は取るに足りないことかもしれない。
太陽は歳をとるにつれ明るくなる。地球の表面は熱くなり、やがて海はストーブの上に置いた水みたいに煮えたぎるようになると、惑星科学者が昔から予測している。強力な温室効果ガスである水蒸気が大気中に流入し、「暴走温室効果」の引き金となる。そうなれば10億年後、地球は、隣の金星と大して変わらない姿に変わってしまうかもしれない。金星は、硫黄を含む有毒な厚い大気に覆われていて、表面の温度は摂氏475度程度だ。
「太陽が明るくなり続けると仮定すれば、同じことが地球でも起こるだろう」と、米ノースカロライナ州立大学の惑星科学者ポール・バーン氏は話す。さらに彼は、数十億年前には、金星にも快適な気候や海があったのかもしれないと付け加えた。
金星が不毛の地となったのは、太陽と関係がなかった可能性もある。最近の研究で、高温化の原因は一連の火山噴火であり、これが「大気中への二酸化炭素の途方もない大放出」を引き起こした可能性があることが示唆された。いずれにせよ、私たちの手には負えない現象により、未来の地球の気候は悲惨なほど高温になり、制御不能に陥る可能性を示している。
地球が金星のような運命をどうにか逃れたとしても、約50億年で火を噴くことは避けようもない。その時、太陽は膨張して赤色巨星になり、地球は灼熱の炎に包まれる。
「太陽が地球をのみ込んでしまうというのが、定説です」とバーン氏は語る。
(文 MADELEINE STONE、訳 牧野建志、日経ナショナル ジオグラフィック社)
[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2020年8月24日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。