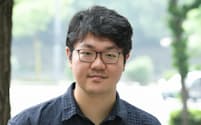社会に欠かせぬ「問う力」、SNSで衰退 炎上で知る
「Tehu」こと張惺さんに聞く(下)

かつて「Tehu(てふ)」として「バズる=ネット上で大きな話題となる」ことを求めていた張惺(ちょう・さとる)さん(25)へのインタビュー後編。2014年の「小4なりすまし事件」が批判を浴びて「Tehu」からひとりの大学生に戻った張さんが何を思い、今はどんな未来を描いているのかを聞く。(前編は「『小4なりすまし事件』大炎上6年、いまSNSに思う」)
心地いい情報で自らを囲む危険
――慶応義塾大学1年生の秋に友人と起こした「小4なりすまし事件」の後、2年間の休学を経て復学しました。どんな時期でしたか。
「大学に入学はしたものの、実は自分が何をしたいのか分からなくなっていました。それで1年生も終わりの3月から休学したんです。大学に戻ったときに入ったのが鈴木寛教授(現在は東大教授を兼任)の研究室で、演劇やオペラをテーマに学びました。卒論は19~20世紀のオペラの中に現代社会と同じ問題をあぶりだせるのではないかとの意識で執筆したのですが、考えているうちに現代は『何かを伝えたい』ということがもはや機能しない時代なんだ、と思い当たりました」
「SNS(交流サイト)にある『フォロー』という非常に基本的な機能は、自分が興味あるものの情報を画面上にまとめる仕組みです。人は自分の見たいものしか見ないところがあるので、その限られた情報の中でも心地いいもののみを取り入れ、自分と異なる考えは『偏向している』と切り捨てる。そうなると人は自分が興味のないことについて問うことがだんだんできなくなり、(聞く耳をもたない相手に)異論を示して問いかけることも意味を失います。つまり『問いは死んだ』のだ、と」
――何かを「伝える」ということは「私はこう思うが、それであなたはどうか」という問いにつながっています。それが機能不全になっていると感じた事例はありますか。
「『小4なりすまし事件』がまさにそうだったと気づきました。衆院解散の目的を問うサイトを開設するだけでは注目されないと考え、サイトの作者を明らかにしないまま、小学4年生になりすましてしまいました。その手法に非があったのは間違いなく、本当に反省しています。ただ、あの当時、最も残念だったのは、小4は誰かという点だけが取りざたされ、解散の是非についての建設的な議論がまったく起こらなかったことでした。我々が提起したかった問題は問われなかったのです」
――SNSの中とはいえ「問いは死んだ」という状況では、議論そのものが成立しなくなる可能性がありませんか。
「社会変革は、考えの違う人がいることを前提に、互いに問いかけ、説得したり、されたりしながら進展するものだと思います。過去を否定せずに、うまく内包しながら、新しい考えをつくり、浸透させていく。だから問いが機能しない状況下で社会を変えていくのは難しいですよね」
「僕は小4事件のあと休学し、モヤモヤした思いを抱える中で(リーダー育成研修を手掛ける)チームボックスという会社に携わるようになりました。そのときはどうしてこの会社の仕事に興味を持ったのか、自分でも分かっていませんでした。でも、改めて考えてみると、リーダー育成という事業は、問う側と問われる側が1対1で向き合い、考え続けることなんです。思い返すと、自分は問いが機能する場所を探していたんだと思います」
――問うことの大切さは、リーダー育成に限りません。問いが機能する社会を守る方法はありますか。
「今は『1対1』の問いを『1対多』でもできないか、それを人間ではなく何らかのシステムによって生み出せないかと、ずっと考え続けています。例えばコンピューターから『こういう選択肢もあるのでは』と問いを投げかけられることで視野が広がり、人間がよりよい判断ができる仕組みを作りたい。あくまでコンピューターが人間を補助する形で」
――人工知能(AI)ならできませんか。
「現状では難しいと思います。そもそも(問答によって)人間の視野や選択肢が広がったのかどうか見極める方法をAIに学ばせることができないんですよ。人間が意見交換するときのように、相手の思考を理解しながら、ちょっとずらした考え方を示して『こういうのはどう?』と問うのは、すごく高度な知的営みで、まだコンピューターに扱える代物ではないと思います」

「最近ずっと考えているのは『ヒューマニティー』という言葉についてです。『人間らしさ』というか、ピッタリな訳語がまだ見つからないんですけれど、僕はAIの対義語としてとらえています。むしろAIが出てくることによってヒューマニティーがより顕在化しているように感じています。ヒューマニティーを構成する要素が何なのか、まだまだ分かっていませんが、AIではなく、そこにこそ僕の探し求めるものがあるような気がすごくするんですよね」
「別人格」で挑む
――長期的にはどんな事業をするつもりですか。
「あまり長期的にこれをやろうという意志はありません。起業家の友達は、めざす社会に向けて10年で事業をこうしますっていう話をするけれど、僕はそれがない。僕は起業家じゃないな、と思います。『ものづくり』そのものが好きなんです」
「いまプロデューサーやCTO(最高技術責任者)として8社の事業に関わっていますが、それぞれ人々の生活をよりよく変えるサービスや製品をつくろうとしているので、そこで一緒に質の高いものを創り出したい。将来、何か成し遂げたいものができたときのピースになり得るものを集めている時期なんだと思います。30歳になったら、そこでいったん意識的に別人格をつくり、その人格で10年ぐらい別のことをしてみたい。40代になってまた元の人格に戻ってきたときには、本気で『問いかけ生成システム』みたいなものに取り組めれば本当はいいな」
――「Tehu」という人格を卒業して、また別人格ですか。
「人は誰でも相手のことや、自分自身のことさえも『こういう人』とラベリングしていると思います。そうすると、どうしてもしがらみが生まれます。(別人格という)新しい枠組み、箱を作って何か新しいことにチャレンジしていけば、隠れた自分の要素を見つける機会になる。自分の可能性を狭めずに済むんじゃないかと思うんです」
「(30代の別人格で)何をやるか、まだ決めていませんが、1つ可能性があるのは演劇。卒論では、劇場という空間は人への問いかけが機能する場としてまだまだ希望がある、ということを結論に書きました。いずれにしても、コロナ禍で『不要不急』とされているような分野に挑戦してみたいです。そこに40代以降のヒントが隠れているんじゃないかな、と思っています」

――「具体的にやりたいことが見つからない」という学生は少なくありません。彼らへのアドバイスはありますか。
「無理に意志を持たないことじゃないですか。それから『その意志は本当に自分の持ちたいものなのか、それとも周りが意志を持った方がいいと言っているから持ったのか』と常に自分に問いかけた方がいい。長期的な意志って、そんなに簡単に持てるものではないと思うし、どこかで見つかるものだと思うんですよ」
「(米アップル創業者の)スティーブ・ジョブズが言った『コネクティング・ザ・ドッツ(点と点をつなぐこと)』ではないですが、とにかくまず点を打つしかない。そして打った点と点を無理に結んでビジネスを作ろうとしなくても、どこかで線が浮かび上がってきて、あっと気づく。意志を持って何かを成し遂げるというよりは、何らかの意志を持ったとき、それに合わせるように、それまで打ってきた点がつながって、走りだしたくなるように準備されている。そんな瞬間がいつかやってくることを目指して頑張る。僕らが生きる価値って、こういうことなんじゃないかなと思っています」
(聞き手はライター 高橋恵里)
1995年、兵庫県生まれ。灘中学校に入学後にプログラミングを独学し、中3のときにiphoneアプリを開発して注目された。「Tehu(てふ)」のハンドルネームで活動し、「AERA」(朝日新聞出版)の「日本を突破する100人」や「東洋経済オンライン」の「新世代リーダー50人」にも選ばれた。2014年に慶応義塾大学環境情報学部に入学し、休学を経て20年に卒業。現在はチームボックスCCO(チーフ・クリエーティブ・オフィサー)などを務め、コミュニケーションに関わるサービス開発を中心に取り組んでいる。7月に「『バズりたい』をやめてみた。」(CCCメディアハウス)を出版した。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。