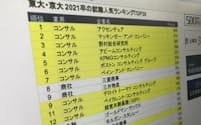商社の組合も改革中 就活で考えたい「働き方の変化」
通年採用時代の就活のトリセツ(6)

こんにちは、法政大学キャリアデザイン学部教授の田中研之輔です。
新型コロナウイルスの影響で、働き方は急速に変わっていますね。コロナ危機の以前から、すでに働き方改革や脱・一括採用の動きで、日本型雇用というものは崩れつつありました。それが今後はより一層、早く進む可能性があります。ところで学生の皆さんは、その日本型雇用の「三種の神器」って知っていますか? 「終身雇用」と「年功賃金」については聞いたことがあると思います。もう一つは何でしょうか?
答えは「企業別組合」です。それが今回のテーマです。
「企業別組合」とは、企業に所属する従業員によって形成される労働組合のことです。労働組合法により、企業別組合の運営や活動が保障されているので、労働条件の改善や賃金交渉などもできるのです。
就活に関係があるのか?と思いますよね。就活生にとって一番遠いところにあるのが、「企業別組合」といっても過言ではないでしょう。

しかし賃金交渉のイメージの強かった、組合の仕事も変わってきています。最近の働き方改革のなかで、組織や制度をも動かしていける仕事になってきているのです。先駆的な取り組みをしている「企業別組合」の話を通じて学生の皆さんに、働き方の変化や働きがいについて、普段とは少し違った角度から考えてもらいたいと思います。
お話を伺ったのは、三井物産労働組合で働く太田友典さん、葛西信太郎さん、高橋絵里香さんです。三井物産労働組合は1962年に設立。2015年には、従業員全員が組合に加入する「ユニオンショップ制」を導入し、新生・三井物産労働組合が立ち上がりました。この新生・三井物産労働組合で、「みんなで創る、未来の会社」をスローガンに、新たな取り組みを始めているのが、太田さん、葛西さん、高橋さんたちです。
ここからは3人のインタビューをもとにまとめています。新生・三井物産労働組合で取り組んでいること、働きがいや学生へのメッセージについて伺いました。
◇ ◇ ◇
――学生には、そもそも商社というビジネスモデルが、わかりにくいかもしれません。まずは商社で働く魅力について教えてください。
葛西 2点あると思います。1点目は、様々な業界の様々な立ち位置で、自分の強みを生かした活躍の機会に恵まれているということです。総合商社は、あらゆる業界や国にまたがる仕事を手掛けていて、それらを俯瞰(ふかん)し、重要な部分に最大のリソースを投下できるように常に変革を続けている企業体です。
2点目は、社内外での学びの機会が多く、制度も充実しているという点です。新入社員には全員メンターがつき、1年間ビジネスの現場でのフィードバックを行います。数年単位で部門を異動しながら幅広い経験を積みつつ、専門性を身につけていくこともできます。また、研修制度も充実していて、海外研修制度やMBA留学制度といった海外で学ぶ制度や社内研修プログラムではファイナンス、アカウンティングなどを学ぶことも可能です。
――商社は体育会系というイメージが強かったですが、働いている人や働き方は変わってきていますか?
太田 商社で働く人材も、かつてあった、体育系の人が活躍するというイメージは、今や相当に薄れています。文系、理系、キャリア採用、帰国子女、院卒など、多様な人材が集まっています。
組合がキャリア相談に乗る

葛西 業務内容も貿易主体から投資の割合が増えてきました。エネルギーや食品など業界別で部門が分かれていますが、縦割りも薄れてきています。「ブリテンボード」という社内公募制度があり、入社3年以上の社員であれば他の部署への異動を希望でき、実際に年間で数十人が異動できています。
自律的であれば、縦横無尽に働き方を選べるということです。逆に言えば、「キャリアアンカー」を見つけるまでは、自分が何に向いているのか、何をやりたいのかと悩むかもしれません。「投資をやってみたいがいきなりできるか不安」など。そういうとき、我々のキャリアカウンセリングで少しでも力になれればと思っています。
――組合の仕事を通じて学んだこと、やりがいは何ですか?
高橋 多角的な視点で物事を捉えることです。例えば会社との交渉の中では、意見がぶつかることもあります。長期的な目指すべき姿は「社員がよりイキイキと働ける会社にしたい」という方向で一致しているのですが、見ている側面が違うが故に、短期的な視点では意見が合致しないということもあります。自分たちから見える世界だけではなく、他の人から何が見えているのか、そうした観点からも物事を捉えることで交渉がスムーズに進むこともあるのです。
葛西 MPUでは人事評価の納得度向上に取り組んでいます。昨年、一年間の活動結果をみると、前年対比で5-10%改善しています。組合員は約4500人なので、数百人のインパクトになります。また、個別にこれからのキャリア形成について相談に乗るケースも増えてきて、結果的に社内の公募制度等を通じて本人が希望するキャリアの実現を支援できたときもやりがいを感じます。
全員がキャリアコンサルタント 新生・三井物産労働組合の取り組み
ここで葛西さんが述べているMPUというのが、新生・三井物産労働組合の通称名称にあります。MPUとは、Mitsui People Unionの略称です。このMPUを立ち上げた中心的なメンバーが太田さんです。太田さん、葛西さん、高橋さんを含め、計6名の専従職員によってMPUは、様々な成果をあげています。以下はMPUの取り組みの一部です。
(1)社員のキャリア形成支援(社内公募制度拡充の提案、キャリアコンサルティングの実施)
(2)働き方改革推進(テレワーク制度導入の提案)
(3)調査を通じたデータ分析(独自のエンゲージメント調査や人事施策に関するサーベイ実施・分析)
ポイントは、より良い働き方と社員の自律的なキャリア形成に取り組んでいる点です。それも、社員の声を反映して、経営層に提案していくボトムアップ型の「働き方改革」なのです。これまで組合というと、経営層と「対峙」するというイメージがありましたが、MPUの取り組みは、社員と経営層をつなぐ「共創型」の取り組みです。
社員一人ひとりの生の声に寄り添うという姿勢も貫かれています。具体的には、MPUの取り組みとして、会社に対して社員一人一人の適性に合わせたキャリアパスの導入を会社に働きかけ、そのために、MPU専従職員は、キャリアコンサルティングの国家資格を取得するという徹底ぶり。
このように社員に寄り添い、総合的に取り組むMPUに、企業内組合の新たな胎動をみることができます。
学生時代に習慣化の機会を
――キャリア形成について様々な知見を持つ皆さんから見て、学生時代にやっておいた方がいいと思うことはありますか?
葛西 まずは習慣を身に着けることです。「学びから得た気づきを習慣として定着させなければ、成果には結びつかない。」と元副社長に言われたことがあります。学生時代は、リポート、試験、論文にしろ、ある程度一時的な頑張りで乗り切れた部分もあると思います。それに対して、社会人は超長期戦なので、短距離走の考えだと息切れするし、伸び悩むものです。社会人になるまでに、何か新しい習慣を身に着け、「習慣を変えられる」ようにしておくといいスタートが切れるのではないかと思います。
もう一つは決断の機会を増やすこと。仕事とは、意見の分かれる課題に対して「意思決定」を行うことです。「意思決定」のスピードと精度を高めていくと、任される規模と数が増し、いいサイクルに入ります。「意思決定」はとにかく場数なので、どんな小さなプロジェクトでもいいので、企画のリーダーから飲み会の幹事まで、意思決定の機会をどん欲に得て、周囲をうまく巻き込む練習を重ねておくと良いのではないかと思います。

高橋 私の学生時代は、省エネで単位を取得して卒業することしか考えておらず、必要最小限の授業しか取っていませんでした。しかし社会人になり、「学習」する時間が減ってから当時のシラバスを見てみるとおもしろそうな授業がたくさんありました。
スティーブ・ジョブズの"Connecting dots"という言葉は有名ですが、就活や卒業と直結しなくても、学生のうちに「点」をひとつでも増やしてください。社会人になっても「点」は増やせますが、学生時代にしか増やせない「点」も多いのです。時間は有限です。学生時代の豊かな時間を存分に使って、色々な世界に足を運んでみてください。
◇ ◇ ◇
これから就活に向き合う皆さんの中には、「社会人として働くこととは、与えられた業務をこなすことだ」というようなイメージを抱いている人も少なくないですよね。太田さん、葛西さん、高橋さんに、そのような働き方は、みられません。自ら考え、同僚と協力しながら、目の前の職場環境や働き方そのものをより良くつくり変えていこうと取り組まれているのです。
葛西さん、高橋さんは、この4月から社会人大学院生として、研究活動にも取り組んでいるそうです。働きながら、学びを深める先輩たちです。これから就活に向き合う皆さんも、自ら主体的に働いていく姿を常に頭に思い浮かべておいてください。
1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を14社歴任。著書に『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(日経BP社)など。
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。