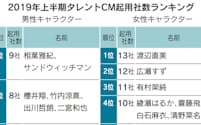女性の目で農業に新風 異業種経験がヒット商品を生む

食の多様化が進むなか、女性が経営する農家が存在感を高めている。異業種で培った視点を存分に生かしているのが特徴で、農業界の風土や働き方に新しさをもたらしている。女性の参入が増えることで、生産者が加工から販売まで一貫して手がける「6次産業化」も広がりそうだ。
JR常磐線の赤塚駅から車で約20分走ると、赤や黄色のつややかなフルーツトマトを生産するドロップ(水戸市)に到着する。広さ5千平方メートル、12棟のハウスで年約40トンを生産する。主力の「ドロップファームの美容トマト」のトマトやジュースは三越日本橋本店(東京・中央)など大手百貨店やネットなどの販路で毎シーズン売り切れる人気商品だ。
経営するのは5歳の娘をもつ三浦綾佳社長(30)。出産を機に未知の農業界に飛び込んだ。前職で身に付けたノウハウを生かし、ミニトマトを上回る糖度を持つトマトをブランディングする。女性目線の商品企画が強みで、百貨店向けとスーパー向けでパッケージを区別するなど徹底的にこだわる。

従業員は三浦社長の夫以外全員女性で、8人が子育て中だ。朝9時から働いて夕飯準備前の15時に切り上げるパート女性や、朝6時から15時まで働き、その後を自分の時間に充てる独身女性もいる。
家族との時間を大切にしながら自身も成長できる働き方を模索し、出合ったのが農業だった。夫と起業した広告代理店では、夜の電話で翌朝までの作業が必要になることも多く、子どもが寝た後も働いた。農業は人が相手ではないため時間の融通が利き、今は18時に仕事を終える。
同社はハウス栽培で、未経験者でも糖度の高いトマトを作りやすい特殊なフィルムを使った農法を採用する。温度や湿度、日射量をあらかじめ設定し、スマートフォンを使い遠隔で確認する。「環境制御を機械に任せられる分、肝になる品質管理や商品開発に時間を割ける」(三浦社長)
ブランディングなどをSNSなどで発信するうち、男性農家から女性採用の相談を受ける機会も増えた。「子ども連れで面接に呼ぶといいですよ。子どもを前に母親は本性を隠せません」。自らの体験を踏まえて助言すると、採用成功の報告が入った。21年にもハウスを2倍に広げるなど事業も拡大基調にある。
農林水産省の「2015年農林業センサス」によると、女性が経営者の農家は全体の6.7%だ。一方で販売額が大きかったり、多角化に取り組んだりする農家ほど女性の経営参加が多い。農産物販売額が300万円未満の農家で女性が経営に参加しているのは43%だが、1000万円以上だと65%を超える。
食用バラ農園「バラの学校」(千葉県館山市)の中井結未衣代表取締役も、会社勤めから農業に転じた。無農薬の食用バラ約300種類を作る農園を運営し、ジェラートやお茶など加工品を大手百貨店や自社のサイトで販売する。

不動産会社時代にフラワーデザイナーの学校に通い、花にのめり込んだ。プリザーブドフラワーの販売・スクール会社として独立後、食用バラの生産・加工とスクールを手掛ける農園を11年に設立した。東日本大震災の被災地に持ち込んだ花が予想以上に喜んでもらえたことが、転身の決め手になった。
最初の2年間は収入ゼロだったが、品ぞろえを増やし、18年には業界でも珍しいバラの葉を使ったお茶も開発した。東京・広尾でバラがテーマのカフェも運営するなど、「他の人がやらないことに挑戦し続けたい」と話す。
バラを起点に事業を広げる取り組みを見て「昔ほど市場で売れなくなっている」と相談してきた熊本県や山形県のバラ農家に、加工品で使うバラの生産を委託した。バラの葉が落ちる塩害などのリスク分散になっているという。
金融や不動産の仕事からUターンしたのが、千葉県南房総市で「大紺屋農園」を営む足達智子さん(42)だ。6600平方メートルの農地でタイ野菜や1個500円を超えるイタリア野菜チコリーなどを年80種類、無農薬で少量生産する。
海外原産の野菜を日本の土地で試行錯誤しながら生産してきた。一般のタイ野菜より1~2割ほど高い価格でも大手タイ料理レストランなどから引き合いがある。タイ人シェフの「味が濃くて日持ちがする」という言葉が励みだ。
実家は大規模な民宿と農業の兼業農家だった。友達に誘われたタイ旅行でタイ料理の魅力にとりつかれたものの、当時はタイ野菜の大半が空輸で入手が難しかった。自ら作ろうと農家を継ぎ、高付加価値農業に転じた。
異業種から飛び込んだ女性農家はSNSも駆使する。足達さんは写真好きを生かして積極的に発信し、レストランなどの顧客を広げている。三浦社長は「家庭では妻が食材を選ぶことが多く、安全性や見た目など同性が発信した情報が刺さることも多いようだ」と手応えを感じている。
次世代農業に詳しい、日本総合研究所創発戦略センターの前田佳栄コンサルタントは「昔は内部だけでつながっていた農家が、SNSの普及で顧客や取引先と直接つながる機会が増えた。データを活用した新技術と相まって、農業は新たな段階に入ってきた」と話す。女性らが新しい農業を追求できる機会はさらに増えていきそうだ。
多角化で災害備えも ~取材を終えて~
「大変な作業が多くても幸せ」――。農家として丹念に農作物と向き合う幸福感と顧客へ届けたときの喜びは大きい。半面、自然災害と向き合う農業ならではの困難もある。9月上旬に上陸した台風15号は千葉県を中心に多くの農家に被害をもたらした。
足達さんが育てる野菜のほとんどが被害を受けた。SNSで実情を伝えると、「知り合いもそうでない人も復旧を手伝いに飛んできてくれて、涙がでた」。加工品などで収入源を多様化していたのも幸いしたという。今回取材した女性農家は皆、リスクを分散しながら独自の農業ビジネスを営んでいた。自然災害が多い日本だけに、柔軟な農業経営が一層必要になると感じた。
(西岡杏)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。