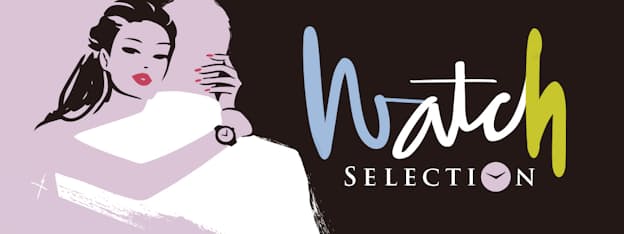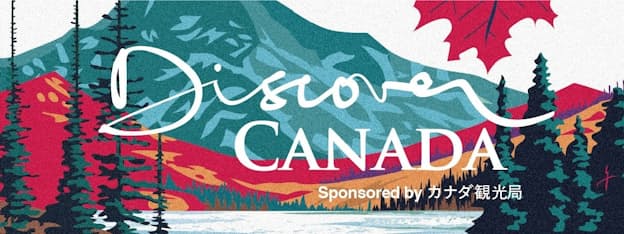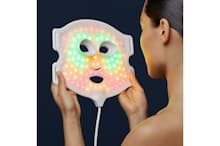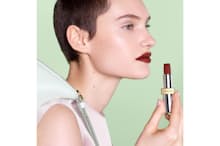19世紀の英国からフランスへと広がったダンディズムとは、表面的なおしゃれとは異なる、洗練された身だしなみや教養、生活様式へのこだわりを表します。服飾評論家、出石尚三氏が、著名人の奥深いダンディズムについて考察します。
ピーター・フォーク演じる「刑事コロンボ」は2018年、放送開始50年を迎え、昨年は多くの名作が再放送されました。
「刑事コロンボ」で個人的な思い入れがある作品は1973年の「偶像のレクイエム」です。これには往年の名女優であるアン・バクスターが出演していますが、それとは別に、衣装デザイナーのイーディス・ヘッドが、一瞬顔を出しているのです。撮影所の中という設定なので、リアル感を出すためだったのでしょう。
■衣装はピーター・フォークが自前で用意
イーディス・ヘッドは今や伝説的な存在です。「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンの衣装をデザインしたのも、イーディス・ヘッド。ヒッチコックの「裏窓」の衣装もそう。アカデミー衣装デザイン賞を8回受賞してもいます。
イーディス・ヘッドは小柄で控えめな性格といわれており、瞬時とはいえ、よくもまあ「偶像のレクイエム」に出たなあという思いがあります。その意味でも貴重な映像でしょう。
イーディス・ヘッドの存在からも分かるように、映画の作品にはすべて衣装担当がいます。テレビドラマもそう。68年に「刑事コロンボ」が始まるときにも、コロンボ刑事用の衣装がそろえられていました。でも、ピーター・フォーク自身はそれがお気に召さなかったのです。なにか、わざとらしい衣裳だと思ったのでしょう。
「ふと家の2階のクローゼットにあったレインコートを思い出したんだ。勘が働いたとしかいいようがない」