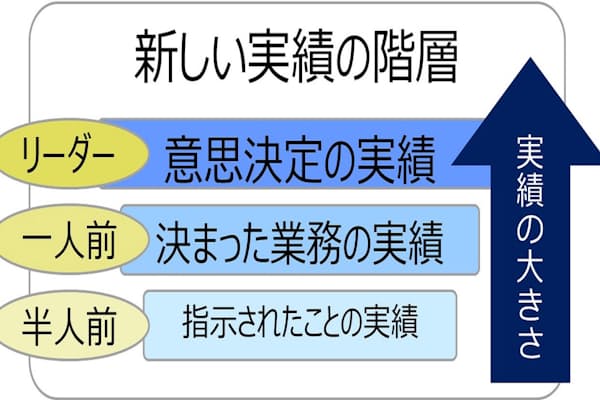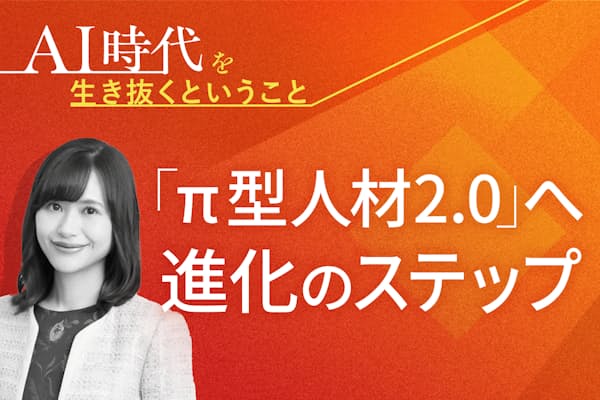よい人事評価、カギは期初にあり 組織目標で協力を
20代から考える出世戦略(55)

画像はイメージ =PIXTA
3月から4月にかけて、多くの会社で人事評価が行われます。その結果について一喜一憂する人も多いのではないでしょうか。ただ、結果が出てしまった後で上司と交渉しても後の祭りになることが多いのも事実です。人事評価を使いこなそうとするなら、むしろ4月からの期初の対応が重要です。
人事評価の不満は期待とのズレが理由
期末の人事評価面談で、上司から評価を提示されます。
その結果について、皆さんは納得されたでしょうか?
統計的に見た場合、納得する人と納得しない人の割合は、ある割合と強く相関しています。
それは、良い評価と悪い評価の割合です。つまり、良い評価の人は評価結果には納得しやすいし、悪い評価の人は納得しないということです。
これはあたりまえのように思うかもしれませんが、人事制度を設計した会社側の意図とは大きく異なります。
会社側は、良い評価の人には継続的に頑張ってほしいのはもちろんですが、悪い評価の人にも、上司との面談を通じて自分に足りない点を理解して、改善してほしいと思っています。だから良い評価の人にも、悪い評価の人にもしっかり納得してもらうための人事制度を作っているのです。
けれども、人の心はそうは動かない、ということが近年の評価の現場でわかってきています。
どんな理由があっても、仮に自分が怠けていたせいだったとしても、悪い評価を示されたとき、人は「納得できない」「上司は私のことをわかっていない」「人事評価なんて意味がない」というように思う、ということがわかってきました。