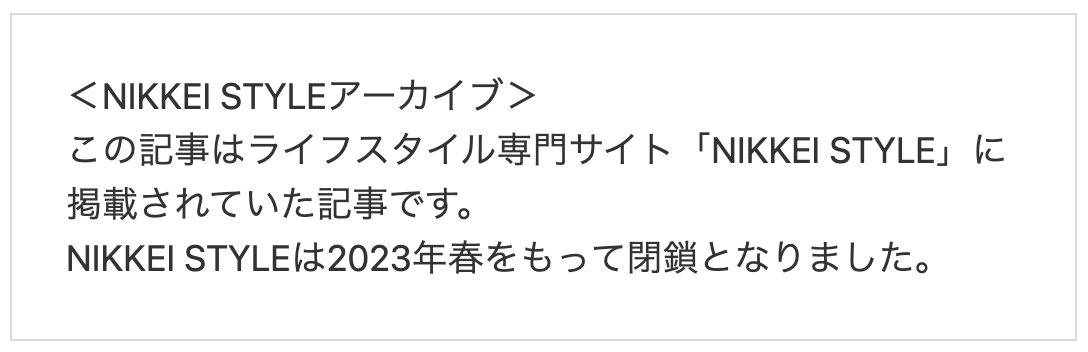和食で飲みたいマデラ酒 酢やしょうゆ、味噌と呼応

ポルトガルの首都リスボンから南西に約1000キロメートル、大西洋に浮かぶ火山列島のマデラ諸島は、世界自然遺産を擁する高級リゾート地。また、サッカー界のスター、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手の出身地としても知られている。そこで造られているのがマデラ酒。スペインのシェリー酒、ポルトガルのポルト酒と並ぶ、世界3大酒精強化ワインの一つだ。
マデラ酒というと、フランス料理のフォアグラや牛肉料理などに使われるマデラソースなどを思い浮かべる向きも多いだろう。料理酒としての知名度はあるものの、ワインとしては、後述するがシェリー酒やポルト酒に比べて生産量が少なく、日本で接する機会は少ないようだ。
以前、本欄で芝浦工業大学の古川修特任教授が、ポルトガルのスティルワインが和食に合うと紹介した(「ポルトガルワインは日本料理にぴったり? なぜなら…」参照)。実は、マデラ酒も和食に合うのだ。かんぴょう巻きに、イカの塩辛、生ウニ……。いったいどうしたら、これらがワインが合うのか。びっくり仰天、知られざるマデラ酒の魅惑の世界にご案内する。

まずは、由来から。
そもそも、マデラ島は大航海時代の黄金期、1419年にポルトガル・エンリケ王の領土獲得の大号令を受けてアフリカを目指した船団が、嵐で漂着した無人島。全島が木に覆われていたこから、ポルトガル語で木を意味するマデラが島名になったという。
偶然漂着したとはいえ、温暖な気候であったことから、ポルトガル領として開墾が進んだ。当時、ヨーロッパで高価だったサトウキビをはじめ、小麦などのほか、キリスト教徒の必需品、ワインのためにブドウの栽培も始まった。
その後、ヨーロッパから北米大陸やアフリカ、アジアへ向かう航路の中継地として栄える。ヨーロッパを出た帆船はマデラ島に寄港し、その後は赤道まで南下、そこからは海流に乗って北米大陸へと向かった。航海は、暑い赤道付近を何カ月も航行することから、ヨーロッパで積んだワインは劣化してまずくなり、飲めなくなってしまう。
ところが、同島で積んだワインはそもそも酸度が高いため航海中に劣化せず、逆になぜだかものすごくおいしくなっていた。ヨーロッパとの気候の違いからブドウ本来の酸味が多く含まれていたのだ。しかも、航海が長いほどおいしくなるものだから、どれだけ長く船に積まれたかがワインの値打ちとなり、船の名前がワインの名前にもなったほど。
これが新しいスタイルのワインとして知られることとなったマデラ酒の原型だ。特に独立前の米国フィラデルフィアでセレブたちにもてはやされ、高値で取引されたという。一方、島の生産者は普通のワインとしてたる詰めし、普通の値段で出荷していた。それが航海を経ると、何千倍もの値段になって米国で取引されていることを知って、「なんとか島内でおいしくする方法はないか」と模索を始める。
そして、ついに「そうだ! ワインを温めればいいのだ」と考えつく。以来、屋根裏部屋にたるを並べて、床下から火をたいて温め、熟成させるようになった。
さらに、もっとおいしくする方法が加わる。18世紀当時、マデラ酒の最大の輸出先が北米大陸だったが、米国の独立戦争の戦況が激しくなるにつれ、ポルトガルと政治的関係の深かった英国が「北米大陸に輸出してはならぬ」と圧力をかけてきたのだ。こうして、北米大陸に売れないマデラ酒のたるが島内にどんどんたまっていき、保管場所にも困るようになった。
そんなときアラビアから蒸留技術が伝わり、ブランデー造りが始まる。ただ、使い道もなくブランデーを造り続けることは難しい。そこで、「ブランデーを加えてみるとどうなるかなあ」と試した人が現れる。すると、さらにおいしくなったではないか。

こうした歴史の偶然によって「温めて熟成させる」と「ブランデーを添加する」という製法が確立し、18世紀の後半には現在のマデラ酒がほぼ完成された。以来、高価な乾杯の酒として珍重される。1776年の米国独立宣言のとき、初代大統領のジョージ・ワシントンが乾杯したのもマデラ酒。その評判がヨーロッパにも伝わり、英国王やロシア皇帝の戴冠式の乾杯にも使われた。
ちなみにマデラ酒が乾杯に使われたことで知られているのはノーベル賞の授賞パーティーで、1930年代まで飲まれていたとのこと。今でこそ乾杯の酒といえばシャンパンがお決まりだが、当時シャンパンはまだ甘く、食後酒として飲まれていたからだとか。
現在も、製法は当時と大きく変わらない。収穫したブドウを絞り、果汁をタンクに入れ、発酵を進める。発酵の初期の段階でブランデーを添加すると甘口となり、発酵が進んだところでブランデーを添加すると辛口になる。アルコール添加やそれによる甘辛調節は、ほかの酒精強化ワインとほぼ同じ。マデラ酒の特徴は、ここから先の加熱熟成の過程で顕著となる。
加熱熟成方法は2種類ある。一つは「エストゥファ」という、大きなタンクにはわせたパイプに50℃程度の湯を循環させて、強制的に温める人工的な方法。3カ月と早く熟成させ、その後たるに戻して2年間ほど寝かせる。
もう一つは「カンテイロ」という方法。屋根裏部屋で太陽光を取り入れ、25~30℃というマデラ島の気候に合わせ、ゆっくり温めて熟成させる。熟成期間は、5年、10年、15年と長期にわたる。これ以上たるに入れておくとなくなってしまうので、ガラス瓶に入れ替え、蒸発を止める。それでも、熟成は進む。

カンテイロでは、古いたるを使うという。というのも、古いと目が詰まっているため蒸発しにくいからだそうだ。一般に加熱すると真っ先に蒸発するのはアルコールなのだが、たるの目がつまっているため、大きいアルコール分子は出ていかない。糖の分子もしかり。蒸発するのは水分だけ。すると、中身がどんどん凝縮され、また糖が熱によって化学変化をおこし、今までなかった味が生まれ、味わい深くなる。これがマデラ酒たるゆえんだ。
マデラ島は火山の岩山であることから、耕地面積が小さく、ブドウ畑は約480ヘクタール。フランス・ボルドーの大きなシャトー(ワイン生産者)の4つ分ほどだといい、シェリー酒やポルト酒の生産規模に比べて圧倒的に小さい。しかも、出荷まで最低でも3年はかかる。そうした希少性も人気のゆえんである。
マデラ酒は長く甘味が重視されてきたが、近年また新たな変革を遂げたという。島内には8つの醸造会社があるが、そのうちのヴィニョス・バーベイト社の醸造家、リカルド・フレイタスさんは、高校の社会科教師から転じた。ワインを造ったことがない経歴が逆に革新を生み出した。
同社は90年代前半、従来の甘味重視から酸味へと大きく舵(かじ)を切った。すると、酒精強化ワインの国際大会で何度も賞を獲得することになる。マデラ酒の新たな幕開けと言ってもよい。

さて、酸味の魅力をどう味わおうか。東京・銀座のマデラ酒専門のバー「マデイラ エントラーダ」に足を運んだ。案内してくれたのは、日本で最も多くマデラ酒を輸入販売する木下インターナショナルの舘農俊則さん。日本ソムリエ協会認定のソムリエでもある。
強い酸味は、温熱熟成の過程でたくさんできる揮発酸に由来する。1リットル当たり1グラムも含まれる。これは普通のワインだと酸っぱすぎてとても飲めない濃度だという。それでもマデラ酒は、アルコール度数が18~20%と比較的高く、糖度も高いなどほかの成分もそれぞれ濃度が高いことから、酸味の強さを感じることなく、全体の中の複雑なうまみとして味わうことができるのだ。

だから、日本のすしに合う。「一般に、ご飯ものはワインは合わないとされますが、マデラ酒は酸味が強いため、酢飯とよく合うんですよ」と舘農さんが説明してくれる。
温熱熟成でできる成分は揮発酸だけではない。アミノ酸がメイラード(還元糖やアミノ化合物を加熱したときに見られる褐色物質)反応を起こして、いろいろなうまみを生み出し、味わい深くなるという。実は、和食の代表的な調味料のしょうゆや味噌もメイラード反応でできている。マデラ酒にもしょうゆや味噌と共通する味わいがあるということだ。加えて、ヨード香、いわゆる海の磯の香りもできる。日本人は日常的にのりなどの海藻をたくさん食べるので、マデラ酒から磯の香りをかぎとることは難しいが、外国人はよく感じるらしい。

このようにマデラ酒には、砂糖、しょうゆ、味噌、酢、昆布だしといった和食の基本的な調味料と共通する味わいがあることから、和食に合わないわけがない。ここで舘農さんが勧めてくれたのが、かんぴょう巻き。かんぴょうは、しょうゆと砂糖で煮切っている。のりにはヨード香があるし、酢飯は前述した通り。マデラ酒と実によく合うのだ。
このほか、イカの塩辛、スジコ、カズノコ、ウナギのかば焼きなどにも合うのは、「和食の調味料味」のなせる技。「生ウニも最高ですよ。ちょこっとつまんで、マデラ酒をなめる。特にセルシアルというブドウ品種のものが合うのですが、まるでティラミスのような味わいですよ」と舘農さん。

出てくる香りが熟成度合いによって次々変わるのも特徴だ。初期には、オーク、コショウ、クローブの香りが出てくるのだが、熟成が進むとアルデヒドが出るようになり、最後はソトロンという芳香化合物が出る。このソトロンがまたユニーク。低温だとメープルシロップの味わい、高温だとカレー風味の味わいになるという。
やはり、普通のワインは、カレーや中華にはなかなか合わせられないものだが、どうだろう。マデラ酒はカレー味にもよく合う。「昔、『お節(料理)に飽きたら、カレーもね』というCMがありましたが、日本の正月シーンに最もよく合うのでは。日本酒だとお節には合うけど、カレーには合いませんからね」という舘農さんの説明に思わず納得。

すしにも合う、カレーにも合うとは不思議な酒だ。日本の居酒屋で、ささやかなつまみをつっつくのに好都合の酒ではないか。西洋流の大きなステーキをほおばりながら赤ワインを飲むのとは一線を画す。ちょこっとつまんで一口、また箸を伸ばしてもう一口。こんなシーンに実によく合うだ酒なのだ。
こうした飲み方ができるのも、スティルワインとの違いがあるからこそ。スティルワインはコルクで「栓」をするのに対して、マデラ酒は「蓋」をする。「栓」とは外界と遮断して内部の状態を守るものだが、「蓋」は一度開けても劣化せず、ずっと同じ状態を保てるので、ほこりなどが入らないようにするためのもの。スティルワインは一度開けたら、飲み切るのが普通だが、マデラ酒は50年前におじいちゃんが開けたものを孫が楽しむこともできるというから驚く。
「自分たちが生きている間は絶対、味は変わらない」という自信があるからこそ、「マデイラ エントラーダ」のような専門バーが成り立つのだろう。聞けば、ウイスキーやブランデーよりももつという。
最後に、舘農さんがマデラ酒選びについてアドバイスしてくれた。「スティルワインの味は年によるブドウの作柄によって随分変わりますが、マデラ酒はたる熟成によって味が変わるんです。ここが醸造会社の腕の見せどころとなります。バーテンダーに尋ねれば快く教えてくれるので、いろいろ味わってくださいね」
(中野栄子)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。