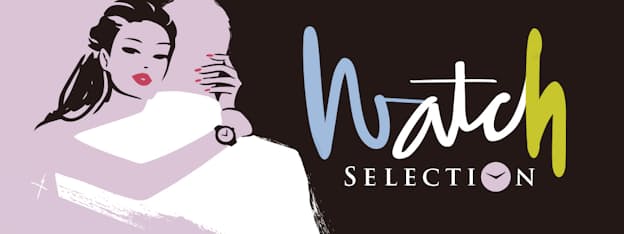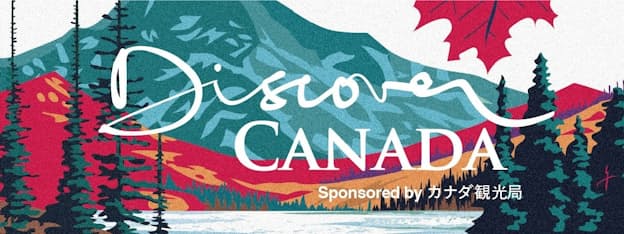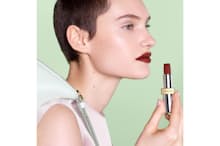分析・計測機器大手の堀場製作所は、エンジン排ガス計測システムや半導体製造装置用のガス制御機器で世界トップのシェアを誇る。創業者である父、故堀場雅夫氏から会社を受け継いだ2代目、堀場厚会長兼社長は「おもしろおかしく」を社是とする個性的な企業風土を守りながら、積極的な買収戦略を展開、グローバル化を進めてきた。若いころから海外勢と競ってきた堀場氏に、世界を相手にする際の「装い」について聞いた。
後編「服装もマネージできずに、人をマネージできますか?」もあわせてお読みください。
――スーツに強いこだわりを持たれているとうかがいました。
「スーツはビジネスの世界のいわば戦闘服のようなものですね。提携や買収、顧客訪問などで海外出張の機会が多いのですが、やはり相手が着ているスーツは気になりますね。海外のエグゼクティブ、特に欧州の方は身だしなみをきちんとしています。ネクタイひとつとってもそうです。だから逆にいうと日本のクールビズは、少し違和感があります」
「その省エネという精神自体は良いのですが、『それならネクタイを外す前に上着を脱ぐべきではないか』と思います。スーツを着てノーネクタイというのはグローバルではだらしない印象を与える恐れがあります。少なくとも欧州ではビジネスの世界でそのようにネクタイを外している人はあまり見かけません。米国のカリフォルニアでは、上着やネクタイはせず本当のクールビズを実施しています」
「ネクタイを外して、上着は着用しなさいという。やはり日本人というのは、何か教科書的なルールに安心したり、言葉に踊らされるところがあって、実質的な意味を考えるところで弱いと感じますよね」

「コーディネーションは自分というよりは家内の方が…」と話す堀場氏
「プロトコルというのが分かっていない。例えば、暑い時期に着物を着るために、腰紐(ひも)だけ結んで、『帯をしたら汗をかくからしません』と言っているのとほぼ一緒ですよね。それならまず、それらしい夏物の着物を着るか、浴衣にするでしょう、という話ですね」
「人と会うときには、やはり言葉遣いや服装など、TPO(時・場所・場合)に応じてのマナーというものがありますよね。それをルーズな方向に、真のマナーの意味を分かっていない人たちがスタンドプレー的にルール化を進めているという感じがしますね」