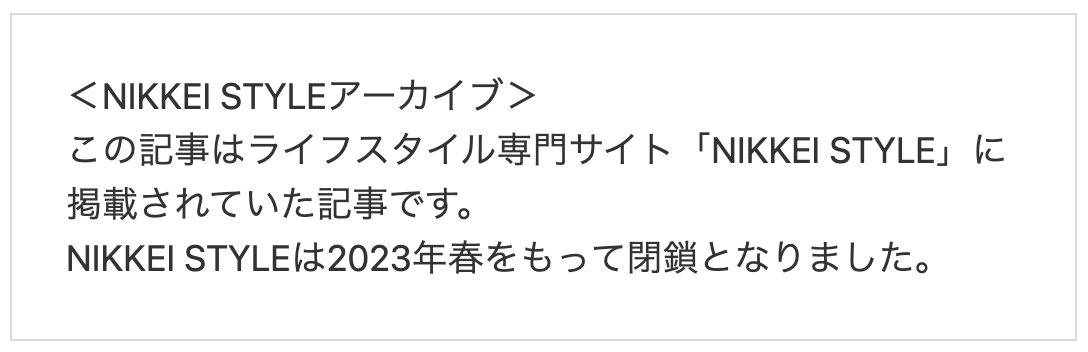カンヌに登場した3つの「怪物」 世界の不安を映す
カンヌ国際映画祭リポート2017(2)

ポン・ジュノ監督『オクジャ』が19日、コンペで上映された。韓国の山奥の農家で飼われている架空の巨大ブタ、オクジャの物語である。どのくらい大きいかというと、ウシやカバよりずっと大きい。ゾウくらいはある。
祖父と2人暮らしの14歳の少女ミジャ(アン・ソヒョン)が4歳のころからずっと世話をしてきた。一緒に山を歩き回り、柿の木にぶつかって実を落として食べたり、渓谷にざぶんと飛び込んで魚を捕ったり。夜はミジャと一緒に眠る。
オクジャがミジャの家で育てられたのは、ある多国籍企業のプロジェクトのためだ。自然環境の重視をアピールする同社は、チリで発見されたという新種の巨大ブタの肥育を世界各国の農家に依頼した。それらを10年後にニューヨークに集め、コンテストを開く。人口爆発と食糧危機に対処する切り札というわけだ。最高経営責任者のルーシー(ティルダ・スウィントン)による記者発表は芝居がかっていて、狂気さえにじむ。
テレビクルーと共に韓国の山奥までやってきた博士(ジェイク・ギレンホール)はオクジャの巨体に驚く。連れて行かれるオクジャ。止めようとするミジャ。過激な動物愛護団体も加わって、オクジャを巡る激しい争奪戦が、ソウルで、ニューヨークで、繰り広げられる。そして隠された多国籍企業のたくらみが明らかになる……。
『グエムル/漢江の怪物』のポン・ジュノらしい巨大生物のドラマだ。アクション映画であり、SFであり、少女と動物の愛の物語でもある。巨大企業の陰謀を告発する社会批判の側面もある。

ポンは記者会見で宮崎駿作品の影響について聞かれた。「宮崎監督を尊敬している。彼は自然や暮らしを描きながら、その影の部分も描いている。『オクジャ』も自然や暮らしを描きながら、現代の資本主義を描いている」とポン。同じく宮崎を敬愛しているというティルダ・スウィントンも「資本主義には人間を幸福にする面の一方で、ダークな面もある。オクジャという動物は資本主義の時代の苦難を象徴している」と語った。
オクジャは優しくて賢い。それゆえに悲しい。資本主義の暴走と世界の不安を、巨大ブタという具体的、独創的な事物で描ききる。そこにポン・ジュノの本領がある。
空中浮遊する難民と欧州の危機
同じく19日にコンペで上映されたハンガリーのコーネル・ムンドルッツォ監督『木星の月』にも"怪物"が登場した。
ハンガリーに不法入国しようとした難民の青年が、国境地帯で銃撃される。ところがどうもおかしい。飛び散った血のしずくが浮き上がり、やがて全身が空中に浮遊する。傷がいえた青年は、自在に浮遊する能力を身につけていた。

難民キャンプでその秘密を知った医師は、青年をブダペストに連れて行く。酒飲みで金に汚い医師は青年に、国境ではぐれた父のもとに逃がしてやるからと言い含めながら、その超能力を使って金を稼ぐ。
『ホワイト・ゴッド/少女と犬の狂詩曲』で都市を占拠する犬たちの反乱を描いたムンドルッツォが、今回も長回しのカメラで都市に出現する非日常の光景をとらえる。空中浮遊する青年は時に天使のようにも見える。
題名は木星の第2惑星エウロパのこと。ヨーロッパの隠喩だ。難民の青年が命からがらたどり着いた夢の土地、ヨーロッパの退廃とモラルの危機がここには映っている。ムンドリッツァは「この映画をヨーロッパの物語として見てもらうことが大事だ。ハンガリーも含むヨーロッパで進行している危機を背景にした物語だ」と説明している。
『散歩する侵略者』の不穏な空気
21日にある視点部門で上映された黒沢清監督『散歩する侵略者』は地球侵略をもくろむ宇宙人の物語である。
ただし宇宙人の姿形は人間となんら違わない。現実の人間の体を借りているので、身内や友人も気づかない。ただ、記憶を失って、人格がすっかり変わってしまったとしか思わない。数日間、行方不明だった夫(松田龍平)を迎えた妻(長沢まさみ)もそう思った。

3人の宇宙人が侵略のために、ある日本の地方都市に先乗りし、人間について調査している。出会った人間の額に触れて、様々な「概念」を奪い取り、学習する。家族、自由、所有、仕事……。そんな概念を。
こうして侵略の準備は着々と進んでいるのだが、街は日常の光景のままだ。でも、どこかおかしい。国家は何かに気づいている。不穏な空気を感じてこの街を取材していたジャーナリスト(長谷川博己)は、奇妙な少年と知りあう……。
原作の劇作家・前川知大の舞台の初演は2005年だが、現在の日本の空気にあまりによく通じていることに驚く。
一見平穏に見える日常の裂け目を描くのは1990年代以来の黒沢映画の特徴でもある。ただ社会の変容と共に、その意味あいも変わってくる。黒沢はこう語った。
「世紀末のころはフィクションとしての不安を楽しむ余裕があった。21世紀に入って、フィクションとして描いたものが、現実になるかもしれないという感じになってきた。でもそれは実は前からあった危機が見えてきたにすぎないのではないか。もともと危機はあったのだけど、我々は見ないふりをしていた」

「核ミサイルが飛んできたら、どこに隠れなさいというような報道が、数週間前からなされている。かつて近未来フィクションで描いていたようなことが、まことしやかに報道されている」と黒沢。黒沢映画の世界に現実が追いついたとしたら、それは世界の不安が顕在化してきたということだろうか。
もちろん、それでもフィクションはフィクションである。黒沢は今回も過去のジャンル映画を参照しながら、虚構と戯れている。長谷川に対しては「ここはカート・ラッセル風に」「ここはトム・クルーズで」という指示も出したという。ジョン・カーペンター監督『遊星からの物体X』やスティーブン・スピルバーグ監督『宇宙戦争』の影を探してみるのも面白そうだ。
(編集委員 古賀重樹)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。