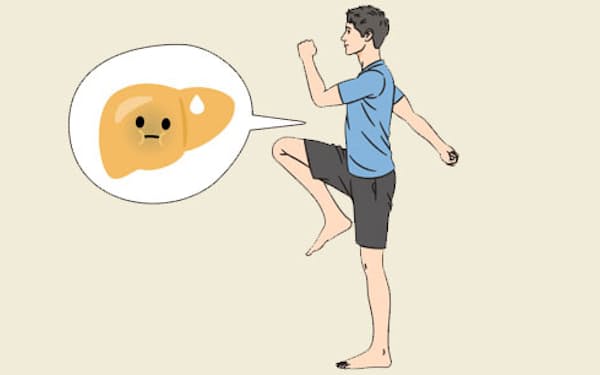昔の花火大会、ゆかた姿はなかった 「制服化」のなぜ
伊藤元重 矢嶋孝敏 共著「きもの文化と日本」(1)

日本が誇る伝統文化「きもの」。生活様式の変化とともに、見かける機会も少なくなりましたが、若者を中心に流れは少し変わりつつあるようです。30年来のつきあいという、経済学者の伊藤元重氏と、呉服大手やまと会長の矢嶋孝敏氏による対談をまとめた「きもの文化と日本」(日経プレミアシリーズ)から、きものをめぐる文化や産業の在り方についての討論を抜粋、5回にわたりご紹介します。
第2回「きものを世界遺産に?「死んだ文化」では生き残れない」もあわせてお読みください。
市場規模は7分の1に
伊藤 この本では、きものが置かれた現状をうかがいながら、「どうすればきものは復活できるのか」を考えたいと思っています。まずは市場規模を教えていただけますか? きものが売れないことは読者もイメージできていると思うのですが、数字でいうと、どれぐらいマーケットが萎(しぼ)んでるのか。
矢嶋 古いデータはないんですが、40年前のピーク時に2兆円強の市場規模といわれていたのが、いま2800億円ぐらいになった感じでしょうか。
伊藤 もう7分の1になっちゃったと。
矢嶋 そうですね。まあ、100万円のきものが1枚売れたのと、10万円のきものが10枚売れたのでは、同じ売上高100万円でも中身が違う。そういう意味で、売上規模だけでは市場実態が見えてこないとは思いますが。
伊藤 たしかに、その売上高100万円の例でいうなら、お客さんの数は1人から10人へ激増してるわけですもんね。そうした中身の分析はおいおいやるとして、大きな傾向としては完全に……。
矢嶋 市場が大きくシュリンクしてしまった。それは動かしようのない事実です。
伊藤 そんななかで明るいニュースというか、今後に期待のもてるような動きは出てきてるんでしょうか?
矢嶋 非常に面白い動きがふたつあります。ひとつは、成人式で振袖(ふりそで)を着る比率が、史上最高に高いこと。もうひとつは、花火大会なんかでゆかたを着る比率が、ものすごく上がっていること。
伊藤 へえー。振袖とゆかたですか。そこに「きものの復活」を考えるヒントが何か隠れていそうですね。では、その話から教えてください。
制服としてのきもの
矢嶋 まず振袖の話からすると、正確な数字はないものの、いま女子の98パーセントぐらいは成人式で振袖を着ている。
伊藤 ほぼ全員といっていいですね。それは5年前、10年前と比べても上がっている?

矢嶋そう思います。メディアに出てくる映像や写真をチェックしてもそうだし、われわれ小売店の実感としても割合は上がってる。100パーセントに近いというのは、過去に例がないぐらい高い。
伊藤 どうしてそこまで、誰も彼もが着る感じになったんでしょう。成人式イコール振袖って記号化されてるんですかね?
矢嶋 振袖が成人式の制服になっちゃってる。記号化ですね。
伊藤 行動経済学では、たとえば「あなたはどうして省エネ・節電するんですか?」という質問で、選択肢を4つ用意するんですよ。1番は省エネすると光熱費が下がって得だと。経済的動機ですね。2番は省エネするのが道徳的に正しいと。モラル的動機。3番は省エネすれば地球温暖化を防げると。社会的動機。では4番は?
矢嶋 みんながやってるから(笑)。
伊藤 正解(笑)。で、日本の場合、4番の「みんながやってるから」という回答が圧倒的に多いんです。
矢嶋 振袖もゆかたもそうだと思う。あれは一種の制服なんですよ。
伊藤 そういえば大学の卒業式でも、きものに袴(はかま)姿の女子学生が増えたなあ。最初に見たときは、すごく奇異な感じがした。もう慣れちゃいましたけどね。
矢嶋 それは学習院だからじゃなくて?
伊藤 いや、東大の卒業式でも同じです。
矢嶋 あれなんかは完全に、大正時代の女学生の格好ですよ。誰が仕掛けたのかわからないけど、いつの間にか大学の卒業式でみんな着るようになった。そういう意味で、きものに袴も卒業式の制服といえる。
ゆかたの人はいなかった
伊藤 振袖の仰々(ぎょうぎょう)しさと比べると、ゆかたはシンプルですよね。ただ、ゆかたって、けっこう昔から花火大会で着られてませんか?
矢嶋 いや、そうでもないんです。僕は新宿で生まれ、小石川で育った。母の実家が浅草だったから、隅田川花火大会は子供の頃からよく行っていたの。だけど昭和30年代だと、ゆかた姿はほとんど見かけなかった。
伊藤 そうなんですか! 僕は静岡育ちなんで、当時の東京はよく知らないけど、いつの間にか花火大会とゆかたをセットで考えてました。だって、いま夏場に電車でものすごく見かけますよね、ゆかたを着た若い子たちを。
矢嶋 花火大会とゆかたがセットになったのは、むしろ最近なんです。いまでは半分以上がゆかたを着ている。特に若い女性の8割がたは着てるんじゃないかな。
伊藤 成人式の振袖や卒業式の袴と同じで、制服化・記号化が起きてるんでしょうね。花火大会イコールゆかたという。

矢嶋まったく同じ現象だと思う。面白いのは、この3~4年、若い男の子のゆかたが増えてる。3割ぐらいには上がってきたんじゃないかな。彼女がゆかたでキメてるときに、彼氏がTシャツ・ジーパンじゃあねえ。
伊藤 見劣りしますよねえ(笑)。花火大会のゆかた比率が高いのは、全国的に見られる現象ですか?
矢嶋 東京の花火大会が、いちばんゆかた比率が高いと思う。
伊藤 特に東京でそういう現象が起きているというのは、ファッションのひとつとして、ゆかたをとらえてるんでしょうね。何かイベントがあるときに、普段だと着られないようなものを着るという。
矢嶋 日本人はシーズンイベントが好きだからね。ハロウィンもバレンタインデーも、世界でいちばん盛り上がってるでしょう。ハロウィンなんてアメリカじゃ子供がやるもんで、大人はやりませんよ。そうしたシーズンイベントのひとつとして、花火大会とゆかたの組み合わせができたんだと思う。
伊藤 いまの若い子が好むゆかたの柄(がら)って、昔と違うんでしょうか?
矢嶋 意外に、半分ぐらいはクラシックな草花模様なんです。残りの半分も、古典的な幾何学模様。市松(いちまつ)模様とか格子(こうし)みたいなやつね。モダンな柄は、全体の4分の1しかない。
伊藤 デザインに関しても記号化されてるのかもしれませんね。花火大会で着るゆかたというのは、こういう感じの柄だと決まってる。だとすれば、テレビや雑誌でよく見かけるような、古典的なデザインを選んでいくことになる。自分で工夫するというより、世間の記号に乗っかっていく。
矢嶋 たしかに、そういうことなのかもしれない。

東京大学名誉教授、学習院大学国際社会科学部教授。1951年静岡県生まれ。東大経済学部卒業。ロチェスター大学ph.d。専門は国際経済学。政府の経済財政諮問会議民間議員などを兼務。
矢嶋孝敏
やまと会長。1950年東京都生まれ。72年早稲田大学政治経済学部卒業。88年きもの小売「やまと」の社長に就任、2010年より現職。17年に創業100周年を迎える同社できもの改革に取り組む。
第2回「きものを世界遺産に?『死んだ文化』では生き残れない」では、 きもの文化が生き残るための道についての討論をご紹介します。
「きもの文化と日本」記事一覧
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界