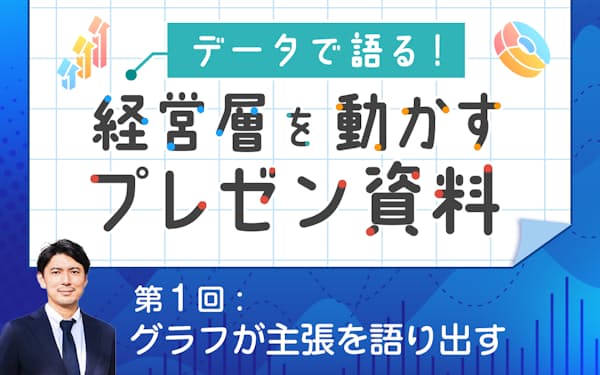「私なんて大したことない」女性が言うべきでない理由

アメリカで注目が集まっている「ハピネス研究」。これは「働く人の精神がどう仕事に影響するか」についての研究で、実践の場でも取り入れられています。翻訳・通訳者の相磯展子さんが、「ハピネス研究」をはじめとする海外の仕事観を紹介します。
「私なんて大したことないんです」と言ってはいけない理由とは
最近「棚からぼた餅」と思えるようなチャンスに遭遇しました。トークイベントと2000人以上の観客の前で話をするストーリーテリングイベントに参加しないかと海外からお声がかかったのです。本番で緊張するかと思いきやどちらもスムーズにいったのですが、トークイベントではついつい無駄口をたたいてしまいました。
それは「私はまだキャリアが浅いから」といった主旨のことを繰り返してしまったことでした。
現地で知り合った香港出身の人に指摘されハッとしました。西洋と東洋の価値観を両方備えていた彼女は私の中に自分の姿を見たのでしょう。「昔の私もそうだったんだけど、あなたはステージに立って話しているのだから、そんなことは言う必要は全くない」と言われました。おっしゃる通りという感じです。それは「しまった!」という気持ちと、そんなことをわざわざ言ってもらったことのうれしさが同時に込み上げてくるエピソードでした。
自分の成果を自信に変えられない「症候群」がある
こうしてついつい日本人らしさを発揮してしまったのですが、謙虚に振る舞おうとするのは、日本人の礼儀なのでしょうか。
テレビをつけると30代くらいの俳優さんが「いえいえ、私なんか……」というふうになんとも謙虚にインタビューの質問に答えていたりします。30歳といえばそれなりの年数のキャリアがあるはずなのに。
内心では「私はそれなりのキャリアを積んでいて、自信もついた」と思っているけれど失礼にならないように、「私は大したもんじゃないから失礼があるかもしれないけど、堪忍してください」と謙虚に振る舞っているのかもしれません。謙遜の美学にはいまだに混乱します……。おっと、いけない、いけない、関係ない方向に話がそれてしまいました。
さて、私が上述の言葉を口にしてしまったのは理由があります。それは「今まで人前で話をした経験がさほどない私がなぜ?」と思ってしまったからです。それでも招待してもらったのには私の能力を買ってもらったからなのですが、それを認めることができない自分がいたのです。
自分の成果を自信に変えられない状態は一般的に「インポスター症候群」と呼ばれています。つまり、自分が出した成果を自分のものとして認めることができない人のことです。
この傾向がある人は自分の成果を「単なる運やタイミング、もしくは自身が考えるよりも周囲に頭が良く、有能であるかのように見せかけた結果として片付ける(*1)」のです。
あなたもそうかも? インポスター症候群の特徴とは
さて、冒頭の「棚ぼた」発言(自分の成果を運の良さとして片付ける)からもお気付きかもしれませんが、私もどうやら多少なりともこのインポスター症候群の傾向があるようです(*2)。
インポスター症候群の特徴は、不健全な完璧主義になりやすいこと。「ミスをしたらがっかりすべきだ」と考えたり、失敗や批判を恐れ、他人をがっかりさせているのではないかと過剰に心配したりするのです。
「周囲は私よりもはるかに能力がある」、「私は人一倍頑張らないと失敗する」といったマインドセットもこれに該当します。もちろんこうしたモチベーションで頑張れないこともないのですが、自分に掛かるプレッシャーなどを考えると限界があると思います。
不健全な完璧主義者はつまり「イマイチな自分」では周囲から認めてもらえないと思っています。周囲からは完璧じゃないとイヤだというワガママな人に見えるかもしれませんが、本人は他によりどころがないからなんとか長所をでっち上げ、周囲になんとか認めてもらおうとしているのです。
インポスター症候群は7割の人が経験する
このインポスター症候群、なんと7割の人が経験するといわれています(*3)。興味深いのは女性と男性で対処法が違うこと。男性よりも女性の方が「頑張る」ことでそれをカバーしようとする傾向にあるのです。
[引用] 135人の大学生を対象にしたある研究(*4)では、不安やインポスター症候群のスコアが高い女性は自分の実力を示すため、周囲よりも一生懸命仕事に打ち込み、競争心を燃やす傾向にあった。一方、同じ項目で高いスコアが出た男性は、自分の弱みが表に出るような状況を避ける傾向にあった。彼らの第一のモチベーションは、周囲に自分の強みを示すことができそうなタスクを追求することで、常に自分の力を周囲に見せられる状況を作ることだった(*3)。
常にすごく頑張っているのに、「私は人よりできない」「不器用」とぼやいている女性はいませんか? もしかしたら「これ私じゃん!」と思う人もいるかもしれません。
過剰に頑張るという傾向に加え、過剰にやらないのもインポスター症候群の特徴の一つだといわれています。心理状況としては「挑戦しなければ失敗もしないはず」というものです。
[引用] 自分の失敗を自身の能力ではなく、準備不足のせいにできるようにあえて十分準備せず何かに臨んだり、ギリギリまでやらなくてはいけないことを後回しにする(*5)。
こんな人にも遭遇したことはないでしょうか?
知らず知らずのうちに成功やチャンスが逃げていっている
「私には能力がない」、「私は人一倍頑張らないと失敗する」といったマインドセットはマイナスです。プレッシャーが大きくなり、バーンアウトにもつながります。
またそれ以上に、自分の成果を自分のものにしないとそれに相応するチャンスを手にすることができなくなります。そう、「私がこの仕事ができたのはたまたま」といった口癖であなたの価値が決まってしまうのです。
自分の価値は自分が決定するもの。自分を過小評価すると周囲は、そのようにあなたを見るでしょう。つまり、あなたの態度一つで、手にできたはずのチャンスが羽を生やして飛んでいっているかもしれないのです。
これはトークに登壇したときのエピソードで私が実感したことです。自分の態度に基づいてあなたは自身が発揮する力を知らず知らず決定し、周囲はそれに基づいてあなたの価値を判断するのです。
胸を張って自分に誇りを持つことがいかに大事か分かりますよね?
自分の成果をものにしよう
インポスター症候群はどのように解消できるのでしょうか。一つは自分の努力や成果を意識的に自分のものにしていくことです。
隣の人と自分を比べないこと。なぜならそれをやり始めるとキリがないから。その人はその人なりの複雑な経緯があって今の能力があり、あなたもあなたなりの紆余曲折があって今がある。だから自分と他人を比べて「なんで私はこの人より劣っているのかしら」と思っても仕方がないのです。魚と鳥を比べても仕方がないのと同じように。
特に、競争率が高い環境や優秀な人が集まった職場ではどうしても自分と他人を比べがちになります。こうした環境にいるときこそ、周囲ではなく自分に集中すること。比べるのなら過去の自分と今の自分を比べてください。
[引用] 自分の行動、やり方を自分のものにすること。そして、努力した自分をリスペクトすること(*5)。
ちょっとした姿勢を変えてみることの大切さ
そんなんじゃ変わらないでしょ、と思うかもしれませんが、ちょっとした言動を変えることで自分への評価が変わっていくことだってあります。
私も自分を過小評価していることを他人に指摘してもらって、以前よりもはるかに自分の言動を意識するようになりました。
自分を下げるような前置きはやめて言いたいことをはっきり言うだけでも、自分の気持ちや相手が自分に持つ印象がずいぶん変わっていきます。こんなことでも自分の価値が変わっていくのです。
下記のポイントもヒントになります。
[引用]
・ポジティブなフィードバックをもらったら、それを客観的に捉え、内在化させる。それを否定することは、相手の判断力に傷をつけているのと同じ
・自分の成功を運で片付けない
・自分の能力や成果を「たった~」、「ただ~」、「単に~」といった言葉で語らない
・日記をつけること。自分の成功や失敗談を書きつづることで全体を概観できる。またそれを読み直すことで、[失敗談だけでなく]両方を同じように覚えていられる(*1)
基準はあくまでも自分――他人の基準を持ち込まない
頑張りの指標は他人ありきでなく、自分ありきに変えることも重要です。他人と比べたり、他人の基準を自分に押し付けると過剰に自分にプレッシャーを掛けたり、ヘトヘトになるまで働いてしまったりする原因になります。
[引用] ……周囲から認められるためではなく、自分のためにできる限り頑張る。また、失敗や後戻りすることを必要以上に心配しないこと(*6)。
心配ごとの多い頭は忙しいものです。知らないことがあって当たり前。他人も同じです。お互いがお互いのインプットをし、周囲と補い合っていくことで仕事が形になっていくのです。
そんなことを前提にいろいろなことに臨むことは重要です。自分の能力を気にしだしたらキリがありません。なぜなら挑戦すればするほど、自分が知らないことがたくさんあることに気づいていくからです。
今まで何をやってきたか、どれだけの能力を持っているかではなく、どうやってその仕事に向かっていくか、目の前のことをどう対処していくかという姿勢を大事にしましょう。そして、すぐに答えが見えないときは「なんとかなるさ」という気持ちも大切。新しいことを学んでいく自分でOK! と思っていれば、そこでの失敗も成功も同等に自分のものにできるはずです。
もう一度言っておきます。知らないことがあっても学んでいけばOK! です。
*1 Mike San Roman「8 Practical Steps To Getting Over Your Impostor Syndrome」、Fast Company、2014年9月23日
*2 「Clance IP Scale」を使ってインポスター症候群の傾向があるかどうか自己採点することができます。質問事項は英語のみ。
*3 Denise Cummins Ph.D.「Do You Feel Like an Impostor?」Psychology Today、2013年10月3日
*4 Shamala Kumar & Carolyn M. Jagacinski「Imposters have goals too: The imposter phenomenon and its relationship to achievement goal theory」
*5 Andrea Ayres「Feel like an impostor? You're not alone」、2014年5月13日
*6 Christian Jarrett「How to Beat the Imposter Syndrome Feeling」99U

翻訳・通訳者。アート専門の翻訳、通訳、プロジェクトの企画運営などを行うArt Translators Collective副代表。ネイティブレベルの英語力を生かし、書き手・話者の視点に寄り添う翻訳・通訳に定評がある。美術館、財団、雑誌などの出版物の翻訳、ウェブメディア記事の翻訳・執筆のほか、イベントやシンポジウム等の通訳や海外とのコレスポンデンスなども行う。
[nikkei WOMAN Online 2017年3月28日付記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。