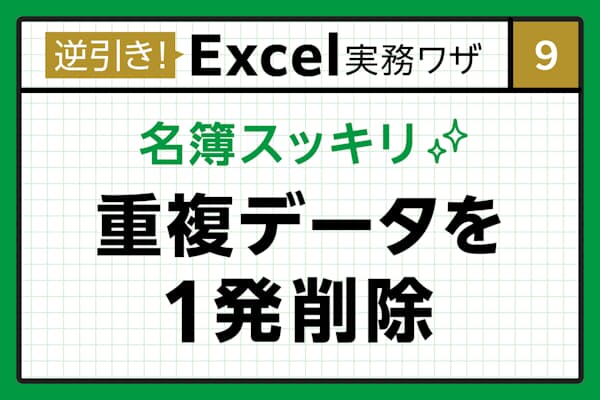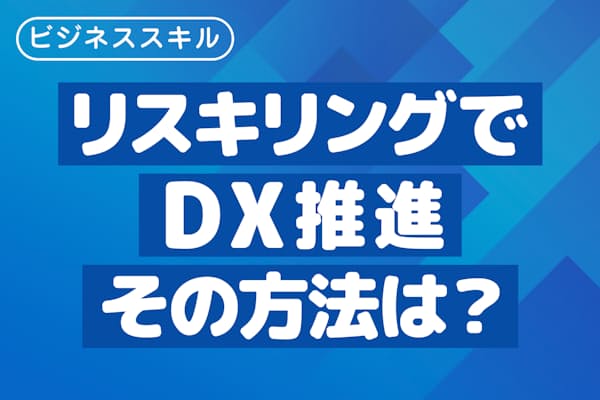見えない課題を探し出せ 現場に耳傾けた工場時代
ブリヂストン社長 江藤彰洋氏(上)

ブリヂストンの江藤彰洋社長(59)は2001年に栃木工場に経理課長として赴任した。
経理課長とはいうものの、実質は幹部として工場全体を見ることになりました。私が力を入れたのはコミュニケーションでした。工場内で多くの人と接し、どうすれば現場の雰囲気がよくなるか、課題を解決できるかを考えました。
(下)強豪ひしめく欧州攻略、コスト競争力を主眼に新工場 >>
課題を見つけて部署横断で協力。
ある時タイヤを作る前工程の部門の主任から未解決の課題があると聞きました。タイヤ部材の両面にゴムを圧着して均一な厚さに伸ばす圧延という工程があります。ゴム同士がくっつかないよう、間にポリシートというシートをはさみ、まき付けることで密着を防いでいました。ポリシートは一度使った後も溶かしてシート状に再生して繰り返し使っていました。
しかし、再生がうまくいかないとぼこぼこの玉のようになり、捨てざるを得ません。溶かした後の冷却過程に問題があったようです。そこで設備や生産技術の専門家などを集め、知恵を出し合って解決方法を探りました。
生産技術の担当者が井戸水と送風機を組み合わせた冷却方法を提案し挑戦することにしました。もちろん1回で成功することはなく、井戸水の量や送風機のあて方を様々試しました。地道な作業でしたが最終的には冷却法を確立。再生率が高まったことで年間5000万円ほどのコスト削減を達成できました。