和楽器マンガ、若者にヒット 「和ものブーム」も背景
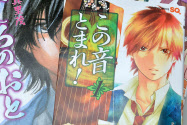
和楽器を題材にしたマンガが人気を集めている。いずれも音楽に情熱をかける高校生の姿を描き、若者の心をつかんだ。背景には日本文化を見直す「和ものブーム」もあるようだ。
「俺、そーきょく部、入っから」。見るからに不良らしい新入生、愛(ちか)が箏曲部の部室へやってきた。地味で気の弱い新部長の武蔵(たけぞう)は戸惑いを隠せない。
月刊誌「ジャンプスクエア」で連載中の「この音とまれ!」(集英社)は箏曲部を舞台に、高校生が仲間との友情を深めていくドラマだ。廃部寸前だったが、愛や箏(こと)の天才奏者のさとわが入部し、全国大会を目指すようになる。中高生を中心に読者を増やし、13巻までの累計発行部数は150万部を超す。
「お箏は、難しい、真面目、と思われがち。親近感をもってもらうため、最も遠い人たちが魅力にハマるストーリーにした」と著者のアミュー氏。母が箏の先生で、自身も高校まで習った。マンガ家を志した小学生時代から「いつか箏をマンガに」と思い続け、「誰かが先に書いたらどうしようと不安でした」と笑う。
演奏動画を公開
登場人物は古典だけでなくオリジナルの現代曲にも取り組む。「読者が口ずさめる曲にしたくて、ポップスに近くメロディーラインがしっかりした曲をイメージした」(同氏)。作曲は母とプロの箏奏者である姉に依頼し、集英社のホームページでプロの演奏動画と楽譜も公開。動画のダウンロード数は70万回を超え、演奏に取り組む中高生は多い。3月にはキングレコードからCDも発売される。
月刊誌「まんがタイムきららフォワード」(芳文社)でも昨年、和楽器を題材にした「なでしこドレミソラ」の連載が始まった。平凡な女子高生が和楽器バンドを組み、何かに夢中になることの楽しさを知る。
著者のみやびあきの氏は和楽器の音色が好きで、自身も津軽三味線を習う。「音色を絵で表現するのは難しい。和楽器は五線譜を使わないから、音符記号は使いたくない。尺八は海や空、津軽三味線はツバキ、と音のイメージを描いている」と苦労を明かす。
和楽器マンガの先駆けとされるのが、2010年から月刊少年マガジン(講談社)で連載する羅川真里茂著「ましろのおと」だ。祖父から津軽三味線の手ほどきを受けた男子高校生が青森から単身上京。演奏に打ち込みながら成長する姿を描く。
当時、「とめはねっ! 鈴里高校書道部」や、女子高生が競技かるたに熱中する「ちはやふる」など、「和もの」と呼ばれるジャンルの人気が出ていた。ただ、「和楽器を扱う作品はなく、面白いと思った」と担当編集者は振り返る。単行本の累計発行部数は250万部に上り、文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞も受賞。その後、各社で和楽器マンガの連載が次々と始まった。
ハードル下がる
実は今の若者は10代から邦楽に触れている。02年度から中学校の音楽の授業で和楽器の指導が義務付けられ、邦楽へのハードルはかつてほど高くはない。昨年にはボーカロイド楽曲のカバーで人気に火が付いた箏や三味線のロックバンド「和楽器バンド」が日本武道館で公演を実施。ゲーム音楽を和楽器で演奏するグループも話題を呼ぶ。
社会学者の難波功士・関西学院大学教授は「グローバル化の反動で日本の伝統文化を見直す動きが続いてきた。東日本大震災後、その傾向が強まっている」と分析。「30代以下の若者は和ものをダサいと拒絶せず、新鮮でかっこいいと考えている。マイナー分野に光があたりヒットする現象は好みが分散した現代の潮流の一つだ」と話している。
(文化部 佐々木宇蘭)
[日本経済新聞夕刊2017年2月7日付]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。














