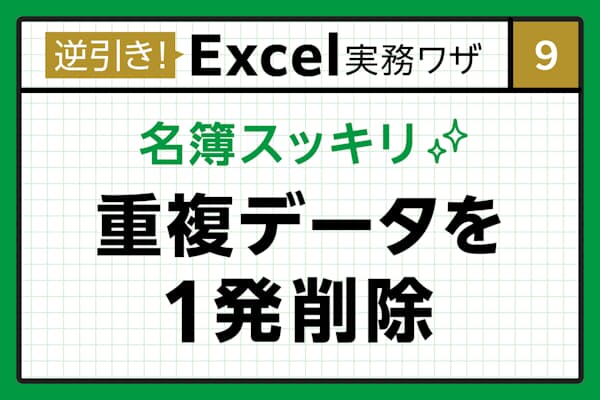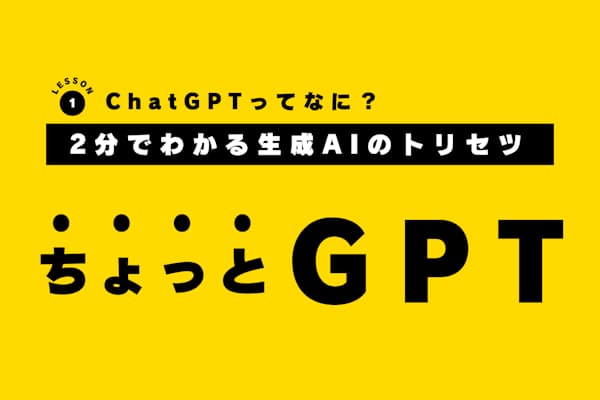大型車で北米に挑む~未知の全長5mミニバン開発、現地の暮らし徹底調査
ホンダ社長 八郷隆弘氏(上)

ホンダの八郷隆弘社長(56)は入社後、本田技術研究所の和光研究所(埼玉県和光市)に配属された。
 はちごう・たかひろ
1982年(昭57年)武蔵工業大(現東京都市大)卒、ホンダ入社。08年執行役員、11年鈴鹿製作所長、14年常務執行役員。神奈川県出身。">
はちごう・たかひろ
1982年(昭57年)武蔵工業大(現東京都市大)卒、ホンダ入社。08年執行役員、11年鈴鹿製作所長、14年常務執行役員。神奈川県出身。">はちごう・たかひろ 1982年(昭57年)武蔵工業大(現東京都市大)卒、ホンダ入社。08年執行役員、11年鈴鹿製作所長、14年常務執行役員。神奈川県出身。
ブレーキ設計から研究所人生が始まりました。プレハブの2階に若い技術者が製図台を並べ、手で図面を描いていました。セダン「アコード」の配線などから担当しましたが、マニュアルも指導もなし。自分で考え、不具合があると先輩から「早く直してこい!」と怒鳴られました。
入社3年目に「早く車を作らせて下さい」と上司にお願いしたら、「だったら辞めて違う会社にいけ」と一蹴されました。「おまえが他の会社に勤められるぐらいになったら俺はうれしいよ」とも。振り返ると、1つの部品を深く勉強することで、ホンダの設計思想や他の部品の理解につながりました。
新車開発の課長級だった1994年から、北米向け大型ミニバン「USオデッセイ」の設計チームを率いる。
米国のミニバンは全長5メートルで全幅は2メートル、排気量3000~4000ccが主流と、ホンダには未知の大きさでした。さらに生産拠点としてカナダの新工場を計画。100人規模の設計チームのまとめ役ですが、日米加の異文化の合同プロジェクトで、企画、開発、生産とすべてが試行錯誤でした。
当時は3車種で年50万台以上を販売していた米クライスラーが「ミニバン王者」でした。ヒントを得ようと、95年のシカゴモーターショーでは一部メンバーがクライスラーの新型車の下に潜ったりメジャーで測ったり。その行動が翌日の地元紙に載ってしまい、米国ホンダの雨宮高一社長(当時)に謝ると、「何とかしとく。その代わりクライスラーが調べにくるぐらい良い車を作れよ」と。皆で「ミニバンで全く新しい価値を創り出そう」と誓いました。
しかしノウハウ不足で、94年末から米国に輸出した日本版「オデッセイ」は苦戦していた。
現地調査を徹底しました。ミニバンは子どもの送り迎えや週末の買い物などに使われます。競合車でロサンゼルスなどを走り回ったところ、高速道路では時速80キロメートルも出すと後部座席が暴れて安定しないことがわかりました。乗用車並みの快適な乗り心地を目標に、上級セダン並みのサスペンションの採用と広い室内空間の両立に苦心しました。
小学校やショッピングセンター、郊外の住宅地での観察から生まれたのが世界初の両側全自動スライドドアです。従来のスライドドアは重く、母親の開け閉めが大変そうでした。リモコン操作や挟まり防止技術も開発するなど、現場で独自の提案が決まっていきました。しかし、開発の6合目で問題が発覚し、プロジェクトが停滞します。
ホンダは1980年代に日系自動車メーカーとして初めて米国工場を稼働。90年には世界生産が約200万台と10年間で2倍となった。国内販売の不振で、92~94年は世界生産が3年連続で減少したが、94年10月に発売した「オデッセイ」の大ヒットを契機に国内販売は回復に転じた。