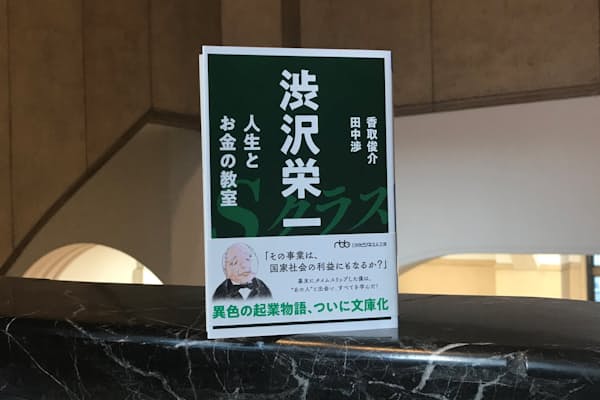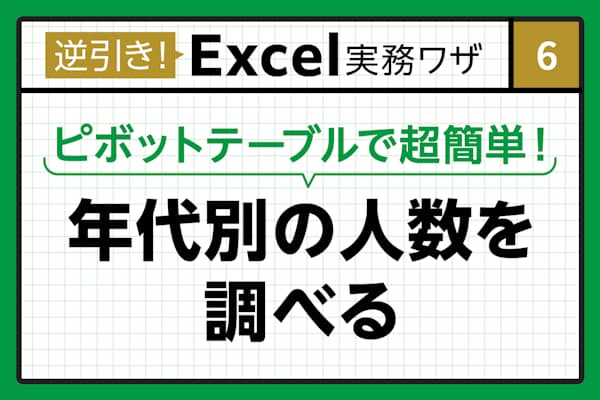今春の賃上げどうなる? 個人の成果反映の動きが加速

経団連は春季労使交渉の指針で日本型雇用の見直しを訴えた(労使フォーラムであいさつする経団連の中西宏明会長)
今春の賃上げ交渉が始まったと聞いたわ。景気の先行きが不透明な感じがするけど、賃金が上がらないと消費も増えないし経済も良くならないはず。見通しはどうなのかしら? 今春の賃上げ交渉の特徴などについて、大友由美さんと藤里美さんが水野裕司編集委員に聞いた。
――賃上げの交渉はどのように進むのでしょう。
毎年2月から3月にかけて、労働組合と会社側が賃金の引き上げを中心に、労働時間や福利厚生に関する事柄なども含めて交渉します。こうした方式は60年以上の歴史があり、かつては「春闘」と呼ばれましたが、いまは春季労使交渉という呼び方が定着しています。大手企業では自動車や電機などの業種ごとに、組合側が統一要求を掲げることが多いのですが、これは交渉力を高めるのが狙いです。
毎年注目されるのは「パターンセッター」と呼ばれる先導役の産業や企業の労組の交渉です。代表はトヨタ自動車でしょう。そのトヨタ労組が今春、賃上げに関して新制度導入を提案します。基本給を底上げするベースアップ(ベア)について、人事評価によって個々人の上げ幅に差をつける内容です。労組は一律のベア要求を基本にしてきました。トヨタの動きは他企業への影響も大きいだけに、日本の賃金制度にとって転換点となるかもしれません。
――一律のベアはなくなるのでしょうか?
ベアを実施している企業でも、すべての組合員一律にというわけではなく、若年層を厚くしたり、職務や資格によって傾斜配分したりすることはありました。会社側の集まりである経団連は毎年、ベア実施企業を対象に具体的な配分方法を調べていますが、一律の配分が減少傾向にある一方で、若年層へ重点配分している企業は増えています。
経団連は今年の交渉開始を前に、終身雇用や年功序列に象徴される日本型雇用の見直しを重点課題に掲げました。世界ではデジタル化やグローバル化が急速に進展しています。その中で優秀な人材を確保するには、従来型の雇用や賃金制度では対応が難しいとの考えが背景にあります。仕事の中身で報酬を決めたり、人事評価で昇給に差をつけたりすることで社員のやる気を引きだそうということです。