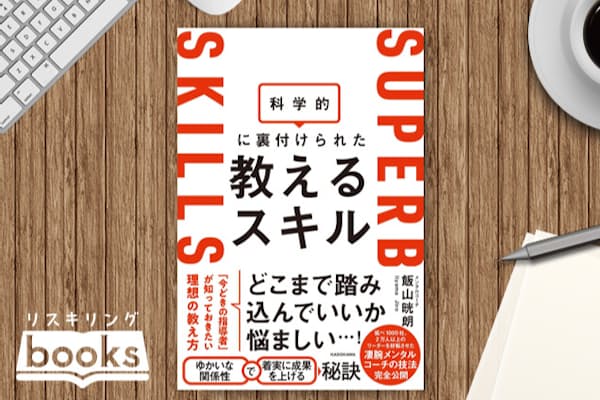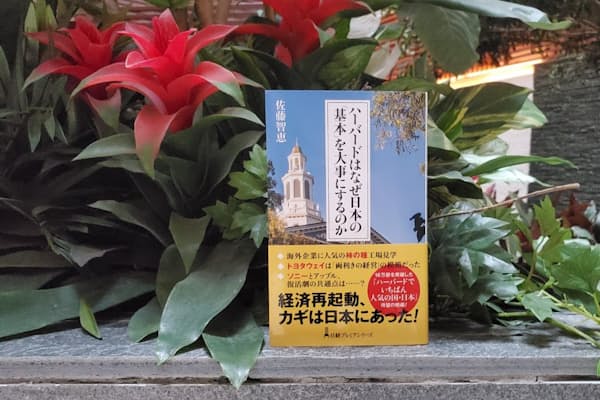年金額はどう決まる? 月22万円のモデル世帯とは

長寿時代の備えには、公的年金額のアップが望ましい。写真はイメージ=PIXTA
公的年金の受給額はどうなるの? 受給額を調整する仕組みが、2019年度は適用されたそうね。今の現役世代は、老後生活を年金に頼ることができるのかな?
公的年金の受給額について、丸山小百合さん(48)と佐藤香織さん(37)が田村正之編集委員に話を聞いた。
――「年金が調整される」とはどういうことですか?
年金の毎年の改定は2段階で決まります。物価と現役世代の賃金の上昇率から、まずベースの改定率を決めます。それに現役加入者数と平均余命の変化によって「マクロ経済スライド」が加わります。
マクロ経済スライドは年金の額を抑える調整の仕組みです。寿命が延びて受け取る人が増える一方、年金保険料を払う現役の加入者数が減ると、財政が厳しくなります。そこでベースの改定率から調整率を差し引いて受給額を算出します。物価・賃金が伸びてベースの改定率がプラスになるときしか適用されないので、2004年の導入後、実行は15年度だけでした。
経済の好転を反映して19年度は4年ぶりに適用されました。ベースの改定率は18年度より0.6%上がるはずでしたが、19年度分の調整率0.2%が引かれました。さらにベースの改定率がプラスにならず適用できなかったときは後からさかのぼって調整するため、18年度に引けなかった分として0.3%減らされました。結果として19年度の増額は0.1%にとどまったのです。60歳で退職した元会社員と専業主婦のモデル世帯では月22万1500円です。
――調整が続くと年金生活が苦しくなりませんか?
調整の目安は、現役世代の賃金手取り額に比べて年金額をどのくらいにするか。この比率を所得代替率と呼びます。今は手取りの6割強ですが、長期的には5割程度になるまで調整します。現役世代との格差は、将来は広がるという覚悟が必要です。
ただ年金保険料を支払う人が増えれば、マクロ経済スライドで差し引く率が小さくなります。19年度の調整率は、以前は0.9%と試算されていましたが、実際は0.2%でした。定年延長や長引く好景気で働く高齢者や女性が増えたためです。好調な経済が続くかどうかが将来の年金額にも大きな影響を与えます。