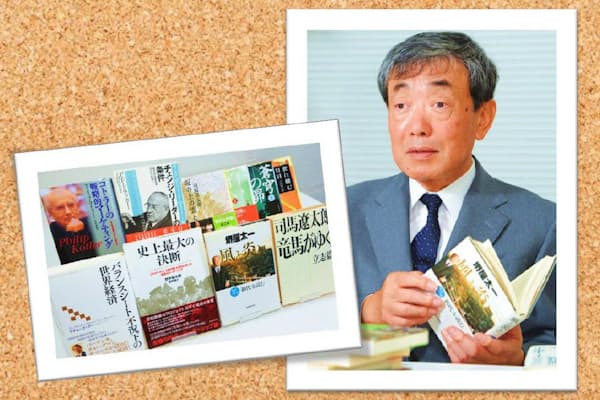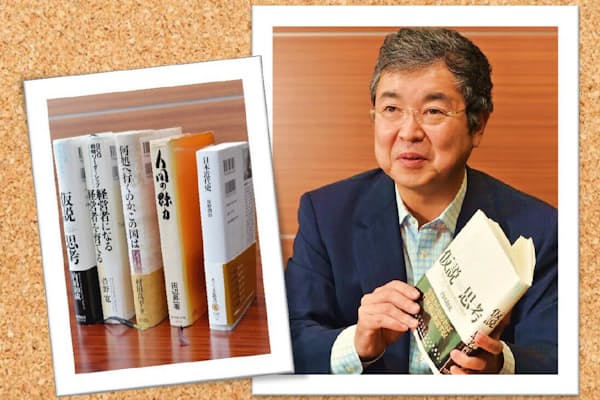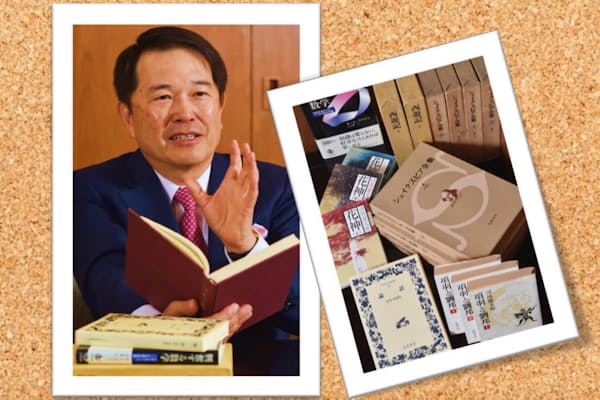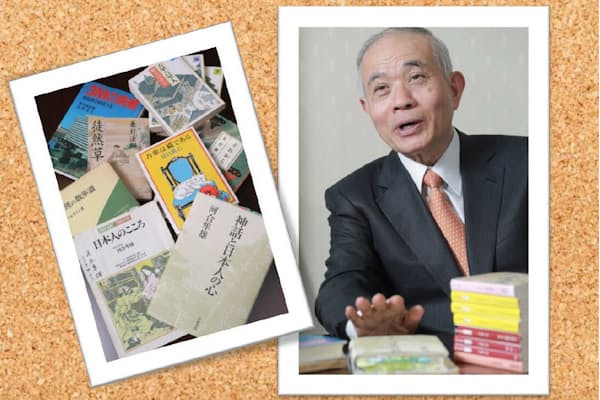諭吉の精神、恩師に学ぶ
日本医療研究開発機構 理事長 末松誠氏

福沢諭吉といえば、普通は『学問のすゝめ』や『福翁自伝』から入るのでしょうが、私は違いました。消化器内科で有名だった師匠、土屋雅春先生が書かれた『医者のみた福澤諭吉』から多くを学びました。

すえまつ・まこと 1957年生まれ。83年慶大医学部卒。米カリフォルニア大サンディエゴ校留学などを経て2001年慶大教授、07年医学部長。15年から現職。
食道がんで入院していた土屋先生のところに、2001年4月に教授就任の報告に行きましたが、約1週間後に亡くなりました。師匠を思い出しながら時々読み返しています。
この本には「先生、ミイラとなって昭和に出現」と副題が付いています。諭吉は死後、土葬されました。福沢家の意向で何カ所かに分かれていた墓をまとめることになり、掘り返すとお棺が冷たい地下水に洗われ腐らずに残っていました。中には帯を締めた着物姿の諭吉が横たわっていたのです。遺体が空気に触れると銅イオンが酸化され緑色に変わり、神様のようだったといいます。
慶応大医学部の北里講堂会議室に掛かっている、諭吉自筆の七言絶句も紹介されています。医師は自然のしもべにすぎず治る病は治るが治らないものは治らない、などと考えてはいけないと戒めています。
優れた眼力とかゆいところに手が届く繊細さをもち、絶対にあきらめずにあらゆる手段を尽くすことこそ医業の神髄であると説くのです。まさにわが意を得たりで、毎年新入生に説明して読ませていました。
『坂の上の雲』も医学部長になった頃に読みました。第1巻に福沢諭吉が出てきたので買ってみたのですが、あっという間に引き込まれて最後まで読みました。明治の人が国のことをどう考えていたのか、興味を持つきっかけになりました。
『医者のみた福澤諭吉』には、官学と私学の対立についても書かれています。私の心に響いたのは、役人におもねるな、尋ねるな、自分で考えろということ。つまり、独立自尊です。さらに、お金をきちんと稼いでそれを還元しなければ、真の教育はできないという趣旨のことを具体例をあげて言っています。

官と民には相いれない部分があります。国立大のような運営費交付金がない私立大は財務の面で厳しく、限られた資源をどう確保し教育や研究の質を保つかが大きな課題です。
福沢諭吉の言葉は、努力して頑張っている地方の大学が報われるようにしたいという私の気持ちにつながっているかもしれません。諭吉は機会均等の大切さも語っており、競争的な環境のなかでよい研究に財源をあてる私の考えと一致します。
映画を見て原作を読みたくなった本もあります。『コンタクト』は10回以上見ました。主人公の研究者が電波望遠鏡で宇宙人を探す計画を提案しますが、上司が邪魔します。それでいて名声は奪おうとしますが、最後は主人公がすごい経験をします。
天文学が好きなこともあり、落ち込んだときにこれを見たり読んだりすると元気が出ます。科学と宗教の問題を考えさせる内容でもあるのですが、AMEDに来てから読み返すと研究費をめぐる判断など役人の振るまいに注目してしまいます。
AMEDは発足前に「日本版NIH(米国立衛生研究所)」ともいわれていました。ちょうどその頃、知り合いからNIH元所長でノーベル生理学・医学賞受賞者のハロルド・バーマス氏の著書『The Art and Politics of Science』を頂き、NIHの歩みを知りました。
ラスカー賞で知られるラスカー財団のジェームズ・フォーダイス名誉理事長に昨秋、初めてお会いした時にはAMEDで何をしたいか聞かれました。難病・未診断疾患やがんの研究だと答えたら翌日に2冊、本を持ってきてくれました。
そのうちの一冊が難病の治療法開発を手掛ける医学博士で法律専門家、起業家でもあるフィリップ・レイリー氏が書いた『Orphan』です。素晴らしい本で、日本の難病プロジェクトを進めるうえでヒントにもなりました。時間があれば自分で翻訳したいほどです。
(聞き手は編集委員 安藤淳)