「エグゼクティブ転職」は、日本経済新聞社グループが運営する 次世代リーダーの転職支援サイトです
厳選209種を日本に! チョコバイヤーの「仕事の流儀」
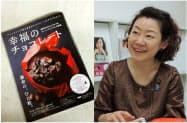
――予約生産スタイルで、とびきりのチョコレートを届ける!
チョコレートは好きですか? 日本市場でチョコレート消費のピークは2月のバレンタインデーです。私の仕事も2月に向けて1年の計画が立てられます。今は、2017年のバレンタインデーに向けた準備が一段落したところです。
私たちが扱うチョコレートは予約生産のスタイルを取っているため、2カ月以上お客様にお待ちいただくことになります。この販売スタイルを海外のショコラティエたちに伝えると、とても驚かれます。
私がお付き合いしているショコラティエたちは、海外へ自分のチョコレートを輸出するよりも、自分の町で、町の人たちのためにチョコレートをつくって暮らしているような人たち。だから、なおさら驚くようです(笑)。
私はそういう小さな町の路地裏に潜む、輝くような素晴らしいチョコレート、そしてそのつくり手たちに出会うことが大好きです。
――日本初上陸のチョコレートを求めて国境を越える日々
私が担当しているフェリシモの『幸福(しあわせ)のチョコレート』というカタログは、毎年11月に発行されます。年明けから商談をはじめ、4月末からは海外出張へ。約束していたお店を回りながら、気になる町へも足を運びます。7月には販売する商品を決定し、9月にはサンプルを日本に集めて撮影。10月にカタログを仕上げる、という1年です。
海外出張中は、5時起きは当たり前で1日に5、6軒を回ります。同じ日にたくさんのチョコレートを食べたほうが違いを感じられるので、予定はかなり詰め込みます。一度出張に出ると約3週間は帰りません。チョコレートを求めて次々と国境を越えていきます。
出張中の苦労はありますが、まだ知られていない日本初上陸の素晴らしいチョコレートと出合える喜びは大きいです。それを日本に紹介でき、ショコラティエたちの作品を多くの人に「おいしい!」と味わってもらえることが、本当に幸せです。
――10年前までは、ただの担当者でした
現在はチョコレートバイヤーとして充実した日々を送っていますが、20年間のバイヤー人生、前半の10年はひどいものでした。
20代で最初に就職した会社で花の商品カタログを担当した後、転職。今の会社に入り、食品のカタログを担当するようになりました。はじめは「食品カタログの一部にチョコレート」という程度でしたが、1999年にタブロイド判の専用カタログをつくることになったのです。
ただ、当時の日本のチョコレートを取り巻く環境は今とは大違い。海外のチョコレートは数えるほどで「ゴディバ」ですら知名度のない時代。私たちのカタログも、日本にあるチョコレートを載せただけのものでした。「来年はこの仕事はないかもしれへん……」と思っていましたが、その後も継続され担当を続けていました。
――トラブルだらけ、会社は謝りにいくところ?
数ある仕事のなかで私にとって一番辛かった仕事が、この「チョコレートカタログ」でした。理由はとにかくトラブルが多かったから。
割れる、溶けるはもちろんのこと、インターネット環境が今ほど整っていない中、取引を始めた海外のショコラティエたちとのコミュニケーションがうまくいかず、ときには勝手に中身を替えられてしまうことも。カタログ販売としては致命的でした。
トラブルばかりで、当時、会社は謝りにいくところだと思っていました。「嫌や、嫌や、もう今年でチョコやめる……」と、ずっと思っていましたね。
――大切なことを気づかせてくれた、お客様の姿
そんな中、ある年、チョコレートのイベントで私がお客様の前でセミナーをやることになったのです。通信販売会社の商品企画の人間がお客様の前に出るなんて当時は考えられなかったですし、私の話などいったい誰が聞くのか、と思って当日を迎えました。
すると私の思いとは裏腹に、会場にはたくさんのお客様の姿が。まさにウキウキわくわくといった笑顔で、心待ちにして、列をつくってくれていたのです。それを見た時に、半分いやいや気分でやっていたことが恥ずかしくなりました。自分が扱っているものが、こんなにも人を幸せにできるものなのだと気づかされた瞬間でした。
「これは本気でしっかりやらなあかん!」と腹をくくりました。私の中では、チョコレート業界に入ったのは、この時からだと思っています。

――味わいを語らずに、チョコレートの魅力を語る
チョコレート一つひとつに真剣に向き合うようになると、チョコレートとつくり手がつながって見えてきました。ひと粒の向こうに人が見え、チョコレートがショコラティエの表現した作品であることがわかってきました。それぞれに個性があり、それぞれが本当に美しいのです。
海外のショコラティエは、チョコレートの説明はほとんどしません。「口で説明するのではなく、僕らはチョコレートで語る」というスタンス。はじめは戸惑いました。「もっとうんちくを聞きたいのに」ともどかしく思ったこともありましたが、徐々に彼らの気持ちもわかってきました。
では、バイヤーである私は、何を基準にチョコレートの良しあしを判断し、どう伝えたらいいのか。私のなかで大きな基準になっているのは、チョコレートをつくること(自分の仕事)が好きなショコラティエとしか仕事をしない。そして、味を語らなくても買いたくなるように伝えることを信条としています。味や形の好みは、人によって好き嫌いがありますからね。バイヤーの仕事は難しいです。
――相手を尊重して無理のない判断を
私を悩ませ続けたチョコレートのトラブルについては、ショコラティエたちのアトリエを訪ねて直接話をすることで、回避できるようになっていきました。
このアトリエでつくれる無理のない量はどのくらいか、この人が表現したいことは何か、この中のどれを選べば彼の思いが伝わるいい状態で日本まで届けることができるか、どの箱に何粒をどう入れてリボンはどうかけるのがベストか。
相手を尊重したチョコレート選びをし、状況を見極めて無理のない判断をする。それが、結果的に問題が起こらず、相手にとっても私にとっても、いい仕事になることを学びました。
――失敗は大事! 人に使われるな!
仕事を続けていくなかで、失敗は大事です。辛いこともいいことも、仕事がすべて教えてくれました。昔のように気乗りしないまま働き続けなくて、本当によかったと思います。
楽しく仕事を続けていきたいならば「人に使われるな!」です。文句を言うのは、誰かに依存している証拠。たとえ与えられたことでも自分のものだと思った瞬間から、仕事は楽しくなります。サラリーマンなのにまるでフリーランスのように、こうして私が活動できるのは、仕事へのプライドと、この仕事が好きという思いが誰よりも強いからだと思います。
かつては謝りにいく場所だと思っていた会社も、今では休み明けの月曜日が毎週楽しみなほど(笑)。今週は何があるだろう!?とワクワクしています。一番辛かったチョコレートの仕事が、一番私に光を当ててくれました。
――私のライフワークから「フェリシモ臨床美術部」が発足
チョコレートのほかに私が情熱を注いでいるのが「臨床美術」です。これは医療現場でアートセラピーとして活用されているもので、絵を描くことを通じて多様性を認め合うプログラム。脳を活性化するといわれ、最近注目されているものです。
これも10年ほど前から取り組んでいます。ごく個人的な興味から資格を取得し、週末にお年寄りや子供たちと一緒にワークショップを行ったり、各地で講演を行ったりしているのですが、なぜかこれが社内で人気となり、資格取得者が続々と増え、「フェリシモ臨床美術部」が発足(笑)。今では、家でも体験できるお絵かきキットが商品化されるまでになりました。
老後の社会貢献活動になればと思って始めたことが、思わぬ広がりをみせ、面白い展開になっています。それにしてもいったい私は何者なのか。目指すは「チョコレートとアートで世界平和!」ですね(笑)。

フェリシモ バイヤー/企画開発
美術系の大学を卒業し、1996年よりフェリシモへ。食品カタログを担当するなかで、チョコレートの買い付けに従事。「チョコレートバイヤーみり」の名のもと、日本に初上陸させたチョコは209ブランド。著書に『世界の果てまでチョコレート』。兵庫県生まれ。
●取材後記
チョコレートやショコラティエのこととなると、自分の話よりも熱が入り、瞳がキラキラと輝き出す木野内さん。バイヤーというよりも、チョコレート親善大使のような姿に引き込まれました。彼女の情熱に触発されて、チョコレートづくりに熱が入るショコラティエも少なくないはず。仕事とは1人の情熱のある人がいれば、高まっていくものなのかもしれません。時には情熱をかける側になったり、期待に応える側になったり。そんな相乗効果を生む掛け合いができるのも「仕事が好き」な者どうしだからこそ、と感じた取材でした。
『幸福のチョコレート』のホームページ http://www.felissimo.co.jp/choco/
[2016年12月1日公開のクラブニッキィの記事を再構成]





















