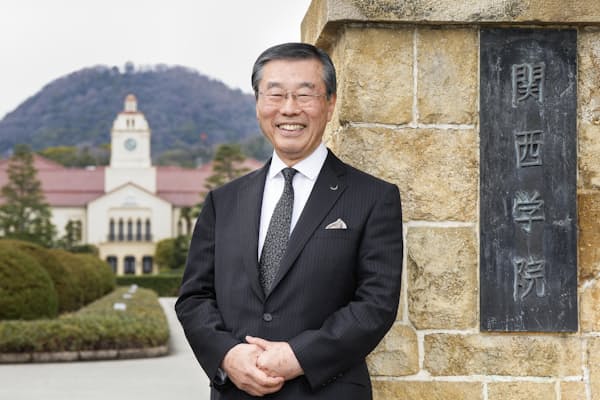「とと姉ちゃん」花山編集長の仕事に役立つ名セリフ

「とと姉ちゃん」がいよいよ最終回
NHKの連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の最終回が迫り(執筆時点)、「ああ、春、夏が過ぎて、もう本格的に秋なんだなあ」とセンチメンタルな気分に浸るビジネスパーソンはあまりいないかもしれない。オンデマンドでしばしば楽しんでいた私としては、真夜中に宇多田ヒカルの「花束を君に」(番組の主題歌)が聞けなくなるのもなんだか寂しい……なんてこととは別に、番組後半で活躍する唐沢寿明演じる花山伊佐次の「仕事に役立つ名セリフ」が聞けなくなるのがちょっと残念だ。
いうまでもないが、花山のモデルは雑誌「暮しの手帖」編集長の花森安治。ドラマをきっかけに、今年「花森本」が10冊近く出版されたのは、花森安治が偉人であるというばかりでなく、「今という時代を生きる上で有益な言葉」をたくさん残してくれていることに私たちが今さらのように気がついたからなのではないか。
花森の超初心者である私は、その魅力のごくごく一部しか理解していないが、「これは実生活に使える!」と思われる「会話技術」を、ドラマの場面とともに振り返ることとする。
入社試験での花山伊佐次の振る舞い
とと姉ちゃん(常子)が社長、花山が編集長として戦後まもなく発刊した「あなたの暮し」(もちろんモデルは「暮しの手帖」)も、例の「商品テスト」の企画が当たり、売れ行き絶好調。社員募集に多くの若者が押し寄せ、最終試験を勝ち上がった10人ほどを前に、花山がしみじみと語り始める、というシーンがあった。

チンジャオロースー(イメージ=PIXTA)
心細げな受験生が連れて行かれた部屋で彼らを待っていたのは、「四川料理の鉄人」陳建一さんだった。とと姉ちゃんや、花山編集長からこれといった説明のないまま、陳さんはいきなり料理を作り始める。中華の定番、チンジャオロースーだ。
「肉は薄めに筋に沿ってこうやって切るね。タケノコは……ネギは……ピーマンは……油通ししてね……盛りつけるよ……はい出来上がり、さようなら……」
陳さんは手早く仕上げると、そのままその場を去って行った。
アッケにとられる受験生たちに「はいここまで!」。さっきまで「憂鬱なものだねえ」としみじみ語っていた花山が噂通りの「鬼編集長の顔」に戻り最終試験の課題を告げた。
狭い部屋には小論文作成のための椅子やテーブルなど一切ない。しかもほぼぎゅうぎゅう詰めの室内だ。機転を利かせた一人(とと姉ちゃんのめい)が床にメモ用紙を広げ書き始めると、全員が慌ててそれに習い、道路にろうそくで文字を書くようにはいつくばり、必死に鉛筆を動かす。
そんな困難に追い打ちをかけるように、花山は蓄音機でベートーベンの「運命」を大音響で鳴らしたり、録音しておいた工事現場の騒音や電車のがたんごとんいうノイズを「これでもか!」と言わんばかりの音量で垂れ流したりして、受験生の集中力をそごうとする。最悪の受験環境だ。
編集長が意地悪そうに、若者に大声で呼びかけた。
「伝えた」と「伝わった」は完璧に違う
花山のモデル花森安治さんが実際にここまでなさったかは知らないが、津野海太郎著「花森安治伝」(新潮社、2013年)によれば、「暮しの手帖式料理記事マニュアル」とも読める箇所にこうあった(以下は梶原の大ざっぱな書き抜き、詳しくは原著に当たっていただきたい)。
(2)このレシピだけを頼りに、現場にいなかった別の記者がその料理を作って、同じ味の料理になっていればレシピを書いた観察者はOKがもらえる。同じにできなければレシピは作り直し。OKが出るまで何度でもレシピを作り直させる…… キビシー……
レシピ通りに作ったのに「一流の味」にならないならレシピの意味がない、というのが「暮しの手帖」のポリシーなのだ。
書かれたレシピがプロの味を忠実に再現できるものでなければ不合格。「まったりしたとろみ感」とか「四川風な辛みたっぷりなのにコクがある」などという、「抽象的で幅のありすぎる表現」はアウトだ。調理プロセスを目の当たりにした編集者以外には、実際に調理する上で何の助けにもならないコメントは役に立たない。
独りよがりな文章や話し方は、読み手や聞き手に伝わらない。「伝えました」と言っても読み手や聞き手が「いや伝わってきません」と言ったら伝えたことにはまるでならない。「伝えた」と「伝わった」は完璧に違うということを理解することは、コミュニケーションの基本中の基本だ。
分かりやすく書くコツはひとに話すように書くこと
「思いは伝わる」とのんきなことを言う人がたまにいるが、伝える側の頭の中に「明確な絵」が描かれていない限り、そしてその絵を伝える技術がない限り「モヤモヤした思い」はなかなか伝わらないものだ。
「あなたの思いって、要するに、何?」
かといって、やたら細かく分量や調理時間の詳細をダラダラ書き、読み手や聞き手の都合も考えず並べたてても、読者や聞き手はうんざり。読む気も聞く気もうせてしまう。素材の切り方、調理の手順、火加減など、必要最低限の客観的な情報を、端的で、わかりやすくコンパクトに。しかも楽しく。
「簡単なレシピ通りにやっただけなのに、こんなにおいしくできちゃった!」
こういう文章や話こそが読み手に、聞き手にストレートに伝わる。花森さんはそういう「プロの技」を講演や、インタビューや、書籍でお話になっているらしいが、前述のごとく、花山で花森安次さんに出会ったくらいだから、詳しくは知らない。
津野海太郎「花森安治伝」には、花森さんが「良い文章とは」との趣旨でこう述べていたと記されている(梶原解釈)。
「分かりやすい言葉以外使うな。全部ひらがなで書いてみてそのままでわかる言葉を使え」
「最小の漢字で書き、漢字は画の少ないものを使え。改行も多くしろ」
「君の書いた文章が(八百屋、魚屋など)ごく一般のおくさんにそのまま読んでもらえるものか考えて書け」
「文章をやさしく分かりやすく書くコツはひとに話すように書くことだ」
これら「書くこと話すこと」に関する「花森安治の、プロの伝えるテクニック」が、花山伊佐次の言葉として「とと姉ちゃん」の中で何度となく登場して「得したなあ」と思うことがしばしばだった。
「日常世俗の細部への好奇心の強さ」
現代でも「花森直伝のテクニック」はいささかも古びていない。そう思わせる貴重な事例を、「月刊プレジデント10月17日号」の特集にあった「ここがおかしい! 理系の日本語(高橋友紀氏)」の中に見つけた。「理系」というくくりになっているが、現代人の多くが自分にも当てはまると感じるものが多い。そしてここでの教えは花森の説いた「伝える技」に通じるものだと感じた。
例えば特に以下の2つは耳が痛い。
【1】「グーグル検索が大好き!」――答えをすばやくグーグル検索で、という傾向のある理系への戒めとして、「人に会いに行こう!」という解決策を高橋氏は挙げる。「生身の人間の話を直接聴く労を惜しまない」というのは、実に的を射た考えだ。「検索のなかった時代」の花森安治も、「生身の人間から直接真意を聞き取れ」と同様の趣旨を述べている。しかもその注文は、さらに厳しかった。
「出かけて直接話を聞くだけでは不十分。君の考えを確かめるだけの質問をするな! 『はい、そうです』以外の、相手が本当に話したい言葉を話させろ!」
「相手の答えを先取りする質問に意味はない」――理系でなくとも思わずビビる厳しい言葉が聞こえてくる。
【2】「専門用語があちこちに」――「サイロ」「デプロイ」「バズワード」など、同業者でしか通じない言葉を普段の会話で使いがちな理系への戒めとして、高橋氏は「自分の母親にわかる言葉で」と解決策を示している(ちなみに、母親がマサチューセッツ工科大学卒のエンジニアみたいなケースは除く……だよね)。これぞまさしく花森がしばしば言っていた「八百屋のおくさん。魚屋のおくさんにわかってもらえる話をしろ」に通じる教えだ。
何度も引用する津野海太郎「花森安次伝」によれば、花森安治は自らの特性を「日常世俗の細部への好奇心の強さ」と言っていたらしい。一言でいえば「やじうま」ともいえるが、私が見てきた限り、面白い書き手、面白いしゃべり手の多くはまさに「日常世俗の細部への好奇心」が極めて旺盛だ。
「日常世俗はくだらない」「細部より大局を見ろ」「好奇心など下品だ」とばかりに「悠然と生きている人」は、「すてきだなあ」と憧れるが「面白いなあ」とは思えない。私が花山やそのモデル、花森安治に引かれるのはこの辺りが理由かもしれない。
[2016年9月29日公開のBizCOLLEGEの記事を再構成]

1950年生まれ。早稲田大学卒業後、文化放送のアナウンサーになる。92年からフリーになり、司会業を中心に活躍中。東京成徳大学客員教授(心理学修士)。「日本語検定」審議委員を担当。
著書に『すべらない敬語』『そんな言い方ないだろう』『会話のきっかけ』 『ひっかかる日本語』(新潮新書)『敬語力の基本』『最初の30秒で相手の心をつかむ雑談術』(日本実業出版社)『毒舌の会話術』 (幻冬舎新書) 『プロのしゃべりのテクニック(DVDつき)』 (日経BPムック) 『あぁ、残念な話し方』(青春新書インテリジェンス) 『新米上司の言葉かけ』(技術評論社)ほか多数。最新刊に『まずは「ドジな話」をしなさい』(サンマーク出版)がある。