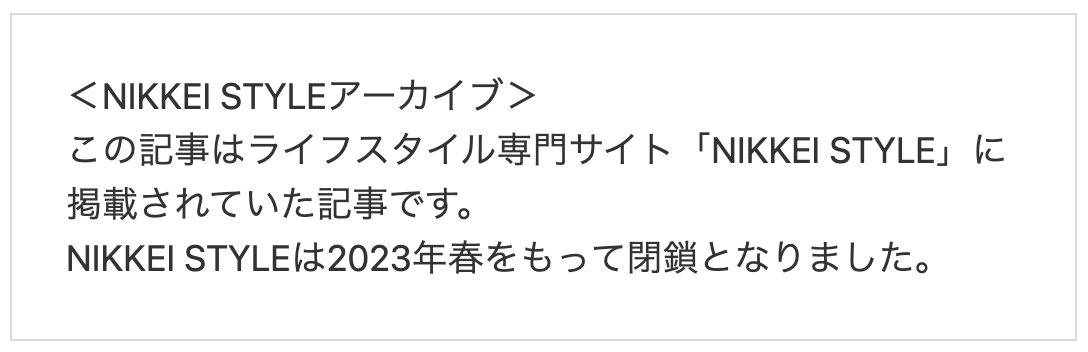長嶋有『ルーティーンズ』 99%、僕の日常のスケッチ
デビュー作の『サイドカーに犬』から20年。これまでも著者自身を連想させる人物がしばしば登場してきた長嶋有の小説に、18作目となる本書で初めて"ナガシマ"が登場した。ぐるっと回って新たな境地に到達した、無二の長嶋文学がここに。

2020年4月。緊急事態宣言下の東京で、作家の「俺」と漫画家の「私」との夫婦の日常が、交互に視点を変えながらつづられる。生活の中心は、保育園を休園中の2歳半の娘だ。ご飯を食べさせ、一緒にテレビを見て、公園に連れていく。トイレトレーニングをし、風呂に入れ、寝かしつける。交代で仕事をし、娘が寝た後には晩酌したり、ドラマを見たり。それは、コロナ禍という非日常のなかの日常で無意識に繰り返される膨大な"ルーティーン"。
「こういう、視点を切り替えて書いていく手法だと、たいてい、夫の思惑を、妻サイドは見抜いていて……という、うらはらな話になるんですね。夫と妻の"違い"を見せることで、読者を裏切っていく。でもこれは、視点を変えても、全然うらはらなことがない話。夫と妻はそれぞれ、娘に『お菓子は買わないよ』と言い、近所の犬に『コロネちゃーん』と同じ口調で話しかける。でも、そんなふうにルーティーンが同じであることを、当の2人は知らない――ということを、読者だけが知っている。そういう仕組みの小説です」
つまり、「俺」と「私」は似ている。でも、だからこそ際立つ微差がある。「台所のここにフックがあったらいい」など、家族の日常に「良さ」をもたらそうとする妻に比べて、夫はそういうことに気が回らない。妻に「ありがとう」「すみません」と思いながら、同時に夫は、「俺は自分の人生を旺盛に生きていない」という寂しい気持ちにもなる。同じルーティーンを積み重ねながら、夫と妻はそれぞれに時間を過ごし、それぞれの思いを抱いている。それがなんともおかしく、そしていとおしい。
「オチがつかないような、とりとめもないことこそ、文学に持ち込めると思っていて。深刻な話の余り物というか。コロナ禍をはじめとする社会の問題にフォーカスするのも文学だけど、僕は、スレスレのところにあるおかしさを小説にする。コロナをテーマにした作品はいろいろありますが、これは、『こういう"のも"あるよ』という感じでしょうか(笑)」
「9分9厘、僕の日常のスケッチ」という本書は、エッセーのような読み口でありながら、小説だからこその味わい深さを含んでいる。
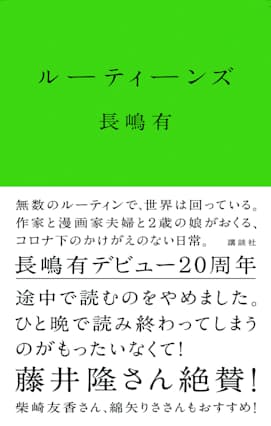
21年に作家20周年を迎えた。同年1月、『願いのコリブリ』という妻視点から書かれた短編と、夫視点で書いた『願いのロレックス』を、文芸誌『群像』と『文学界』に同日発表した。それをきっかけに誕生したのが、2人の視点が交互に変わる『ルーティーンズ』である。
「ここまで18作。突拍子もない舞台を思いつくタイプの作家ではないわりには、いろいろ、違うものを書いてきたかなと思っています。僕は、そもそもそれほど読書経験がなくて、文学というものに対して手探りでやってきた感じがあるんです。『世の中の問題に対して解が得られるようなものこそが小説なのでは?』と思っていた時期もあった。デビューして10年を過ぎたくらいからは、人がやっていないような実験的なものを描いてみたりとか。でも、今回は久しぶりに、最初の頃のように素直に、平易な、読みやすいものが書けたんです。コロナで世界のほうが変になったから、かえって、ただ、スケッチすればいいんだ、と思えた」
自身が子育て真っ最中であることも、スタンスを大きく変えた。
「子育てって、率先して"面白くなくなりに行く"ことなんですよ。人付き合いも、自分のための時間も減るし、とにかくルーティーンの繰り返し。でも、その面白くなさが、望みにもなっている。そのことも書きたかった。そういう意味では、子育て世代の人にも読んでほしい。今回は間口広いですよ。売れるといいなあ(笑)」
無数のルーティーンが、ゆるやかに私たちをつなげている。世界はルーティーンでできている。そのことが、私たちを支えてくれる。
1972年、東京都生まれ。2001年『サイドカーに犬』で第92回文学界新人賞を受賞しデビュー。翌年『猛スピードで母は』で第126回芥川賞を受賞。2007年『夕子ちゃんの近道』で第1回大江健三郎賞、2016年『三の隣は五号室』で第52回谷崎潤一郎賞を受賞。ブルボン小林名義でコラムニストとしても活躍。
(ライター 剣持亜弥)
[日経エンタテインメント! 2022年1月号の記事を再構成]
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。