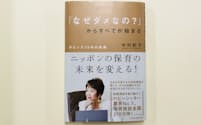保育・介護職員の待遇改善 公費助成と企業努力の両輪で

政府は11月19日に経済対策をまとめました。岸田文雄首相は「成長と分配の好循環」を掲げ、分配強化策として介護職員や保育士、看護師など、いわゆるエッセンシャルワーカーの待遇改善を盛り込みました。新型コロナウイルス感染拡大下での貢献に報いると同時に、賃金アップで人手不足懸念の解消を目指します。
「独自に処遇改善しているが、公費で助成してもらえれば業界全体で保育士希望者の増加が見込める」と、保育大手JPホールディングスの広報担当者は期待します。コロナ下で在宅勤務が増え、生み控えの動きも広がったため、足元の保育需要は一時期より落ち着いていますが、保育士不足は変わりません。有効求人倍率は2.29倍(2021年7月)で、全産業平均のおよそ2倍です。同社が運営する認可保育所などの中には、施設規模に余裕があるにもかかわらず、保育士が手当てできないため受け入れを制限している施設もあるそうです。
賃金構造基本統計調査によれば20年の平均月収は、介護職員29.3万円、保育士30.3万円で全産業平均35.2万円を下回ります。政府は、介護職員や保育士は現行収入の3%程度に当たる月額9000円、看護師は同1%程度の4000円の引き上げで、待遇改善を目指します。
ただ、問題はその先です。介護や保育、医療は暮らしに不可欠な基盤です。安定的に運営できるよう、公費助成する一方で提供価格を公的に定めています。恒常的に待遇改善するには、公定価格を見直し人件費の財源を確保しなくてはなりません。政府は公的価格評価検討委員会を11月9日に立ち上げ、年内に中間取りまとめをする予定です。
公定価格を引き上げれば利用者負担が重くなります。公費を増額する手もありますが、その財源も元を正せば税金。国民負担が増えることは同じです。ニッセイ基礎研究所の清水仁志研究員は「公定価格引き上げで利用者負担が増えれば、世帯の可処分所得が減る恐れもあり、成長と分配の好循環につながるか不透明です」と指摘します。
SOMPOケア(東京・品川)は来年4月、介護スタッフ約7000人を対象に独自の待遇改善を計画しています。現場リーダー職で年収を50万円引き上げます。引き上げは19年10月に次ぎ2回目です。
前回の引き上げで離職率は17%から12%に下がりました。2回あわせて34億円が必要ですが、見守りセンサーなど先端技術を導入し、業務改善で確保しました。「機械ができることは機械に任せ、人にしかできないケアに集中することで介護の質も向上した」(佐藤和夫執行役員)
介護や保育など福祉分野は人手に頼っていたため、IT(情報技術)化は遅れています。賃金アップの原資確保には現場の自助努力も求められています。
清水仁志・ニッセイ基礎研究所研究員「利用者の負担増で議論も」
「成長と分配の好循環」実現を掲げる岸田文雄首相。介護職員や保育士、看護師の待遇改善を進める背景には、これを呼び水として日本社会全体の賃金水準アップを図りたい思惑もあります。思い描く設計図通りに動くのでしょうか? 社会保障制度に詳しいニッセイ基礎研究所の清水仁志研究員に聞きます。
――介護職員や保育士、看護師の賃上げは思惑通りに進むのでしょうか?

「政府は11月19日に財政支出55.7兆円に上る経済対策を閣議決定しました。その中で当面の賃上げに必要な原資を確保しました。2022年2月から介護職員や保育士は現行月収の3%程度にあたる月額9000円、看護師は月収1%程度にあたる月額4000円をそれぞれ引き上げる計画です。この部分は財源も手当てできたので確実に実行されるでしょう。でも問題はその先です。介護や保育、医療は公定価格が決まっているので、恒常的に処遇改善を続けるにはその原資を確保するために公定価格の引き上げなどが必要になります。11月9日に政府は公的価格評価検討委員会を立ち上げました。公定価格の見直しなどを今後議論していきますが、現状では財源が未定です」
「公定価格を引き上げると、どんな影響があるのか、介護を例に紹介します。介護サービスの提供体制や利用者の状況などにより、介護事業者に報酬が支払われます。報酬は基本的に出来高払いです。その中から事業者は介護職員らの人件費を払います。財源は原則10%がサービス利用者の負担、残る90%は国民が支払っている介護保険料と公費です。賃上げの原資となる報酬を引き上げれば、サービス利用者負担や介護保険料、公費も通常上昇が避けられません」
――つまり賃金を上げるために公定価格を上げれば利用者負担は増すということですか?
「端的にいえばそうです。悩ましいのは負担増に利用者がどこまで耐えられるかです。例えば介護保険料は介護保険制度が導入された2000年当時、加重平均で3000円程度(65歳以上)でしたが、今では6000円前後と倍増しています。個人の負担感はすでに増しています。細かな仕組みは異なりますが、こうした収支構造は保育も医療も同様です。介護職員や保育士、看護師の賃金アップのために負担増を国民がどこまで受け入れる覚悟があるのか、分かりません」
「新型コロナウイルスの感染拡大で、こうしたエッセンシャルワーカーは暮らしを支えるために奮闘しました。その貢献に報いたいとする気持ちを多くの方が持っているでしょう。今のところ政府の賃上げ方針に反対する声は聞こえてきません。でも、それは現下の施策に関すること。今後、公的価格評価検討委員会で議論が進み、個人負担増が明確になってきたとき、反対の声が上がる可能性はないといえません」
――政府は、介護職員や保育士、看護師の賃金アップを呼び水に成長と分配の好循環が起きることを期待しています。賃上げにより、消費の喚起や経済成長は実現可能でしょうか?
「賃上げによる経済的効果は不明です。個人的にはあまり期待できないとみています。国勢調査によれば、介護や保育、医療の現場で働く人は就業者全体の1割程度。彼ら彼女らの可処分所得が増えたとしても消費喚起効果は軽微です。むしろ先述したとおり、公定価格引き上げに伴い利用者負担が増えれば、その分、家計全体の可処分所得は減るのでマイナスの影響もあるかもしれません」
「今回の経済対策には、社員の賃金を上げる企業を対象にした優遇税制の導入も盛り込まれました。エッセンシャルワーカーの賃上げだけでなく、社会全体で賃上げを図る仕組みがないと、成長と分配の好循環は生まれません」
「基本的に賃金は需要と供給のバランスで決まるものだと思います。人手不足でありながら、賃金が増えないのは、いびつです。政府が定める公定価格が制約になっているなら、見直すべきです。ただ、今回の動きで気になるのは介護職員と保育士が同じステージで議論されていることです」
「高齢化に伴い、介護職員は今後も人手不足が続きます。でも保育士の需給状況は異なります。ここ数年の待機児童対策の効果があがり、待機児童は減少傾向です。都心部は相変わらず多くの待機児童がいますが、地方では待機児童ゼロを実現した県・市町村もあります。保育士の有効求人倍率も、都道府県ごとに開きがあり、全国で保育士不足が深刻な状況でもありません。限られた財源をどう効率的に配分するか。きめ細かい議論も必要です」
(編集委員 石塚由紀夫)
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。
関連企業・業界