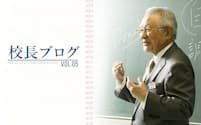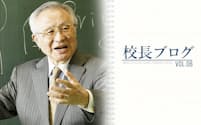修学旅行は「不要不急」か? 学校行事が生む効果とは
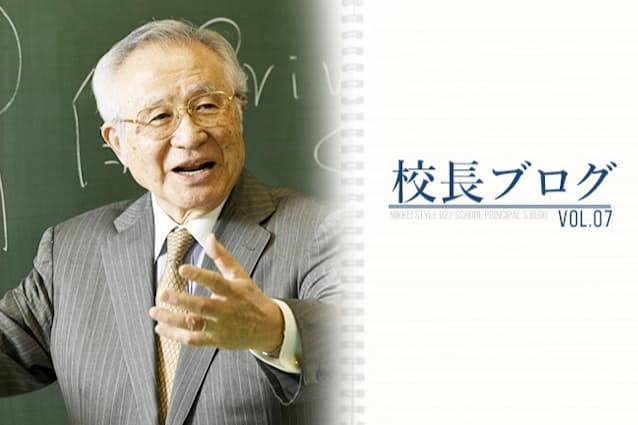
学校とはどんな場なのでしょうか。コロナ禍の中で、学校とは生徒がワクワク、ドキドキする場なのだと改めて痛感しました。オンラインも活用できますから、授業自体の影響はそれほどありません。しかし、生徒の元気がだんだんなくなるのがわかります。昨年は運動会や文化祭、校外学習などのリアルな行事が、縮小や中止、あるいは延期やオンラインへの変更に追い込まれたからです。
感染対策徹底して、文化祭など各種行事を再開
そこで今年はできる限り、コロナ対策を徹底して各種行事に実施するようにしています。9月には渋渋、渋幕では保護者を呼ぶことはできませんでしたが、文化祭を開催。10月には両校の高校2年生が九州、広島に修学旅行に出かけました。もともと「日本文化の源をたどる」をテーマにして中国に行っていましたが、今、海外は難しいので、中国から最初に文化の伝わった九州を選択したわけです。
ただ、この修学旅行ではちょっと残念な出来事がありました。羽田空港から飛行機に乗り込む際、一般の乗客の方が修学旅行の生徒を見て、係員の方に「修学旅行なんて不要不急だろう」とクレームを言ってこられたようです。
渋渋、渋幕両校では修学旅行といった校外学習など行事の開始を控え、8~9月に希望する生徒、教職員全員にワクチン接種を実施、さらに旅行の1週間前からの検温、そして直前にも生徒、関係者の希望者全員にPCR検査を行い、結果は全員陰性、無事に出発することができました。
コロナ禍において、一般の乗客の方が懸念されるのはもっともだと思います。ただ、少し疑問を感じたのは「不要不急」についてです。確かに大人の団体旅行なら、いつでもいいかもしれません。しかし高校生の場合、3年生になると受験があるので難しい、人生の中で今しかチャンスはないのです。しかも校外学習のような行事は非常に大事で、効果的な学習法なのです。
灘高の強さの秘密 生徒同士で教え合う
米国の研究機関がまとめた学習内容が頭に入る学習定着率のデータがあります。それによると、最も低いのは「講義」で5%。定着率が高いのは「自ら体験」が75%、最も定着率が高いのは「他の人に教える」の90%です。これは生徒同士で教え合うというやり方です。この学習法を実行するには、行事が有効に働きます。
この九州の修学旅行も、目的地は学校側で決めましたが、それぞれのコースや各地の企画などはすべて生徒主導で行います。自分たちで調べ考えて、実際にいろんな現場を巡り、自ら体験しながら、学び合うわけです。そこで生徒同士の友情や信頼関係をはぐくみ、勉強でも教え合う関係に発展していくのです。
「教え合う」と言えば、1983年に印象深い場面がありました。千葉市に渋幕を新設する前、全国の進学校を見学して回ったとき、灘高(神戸市)も訪問したのです。
一体どんなすごい授業なのか、試験もハードなのだろうと思ったのですが、意外とゆったりやっていて、詰め込み授業なんてやっていない。ただ、驚いたのは放課後にそれぞれ何人かの生徒たちが集まって、「この解法の方が面白い」といいながら、数学などの問題を教え合っていたことです。受験勉強のライバルだから仲が悪いのではなく、互いに助け合っているのです。「これが灘の強さの秘密なのか」とつくづく感心しました。灘も文化祭などの行事を非常に大切にしている学校だと思います。
ワクチン接種、PCR検査でいい先輩と触れ合う
10月前半の1週間、渋渋、渋幕の高2の生徒が修学旅行に参加している間、他の学年も期間は短いですが信州や房総半島など近場に校外学習に出かけました。みんな急に元気を取り戻し始めました。鬱屈した表情だった生徒の顔が輝き始めたのです。
ちなみにこの夏、ワクチン接種や修学旅行のためのPCR検査をしてくれたのはいずれもうちの卒業生です。「大丈夫、僕1人で打てますから」とOBの1人の医師が250人あまりの生徒など関係者のワクチン接種をやってくれました。一方で、「東京PCR衛生検査所」を運営するナチュラリ(東京・港)の社長である植島幹九郎くんも、急な依頼にも関わらず生徒向けPCR検査の態勢を整えてくれ、おかげで生徒側の負担はゼロに抑えることができました。植島くんは東大時代に起業家になり、今も母校のことを何かと気にしてくれます。彼らは生徒にとっていい先輩であり、ロールモデルにもなっています。リアルな場では、このような先輩との触れ合いも可能ですが、オンライン学習だけでは難しいでしょう。
コロナ禍での集団行動は非常に気をつけなくてはいけません。しかし、生徒同士や先輩などともつながり、学び合うリアルな行事はとても大切なのです。学校は生徒にとって、ワクワク、ドキドキの場でなくてはいけない。今日、何か面白かったり、楽しかったりすることはあるのかな、と思えないと学校なんて何の意味もありません。コロナ禍で改めてそう確信しました。
麻布高校を経て東京大学法学部卒、1958年に住友銀行(現三井住友銀行)に入行。62年に退職し、父親が運営していた渋谷女子高校を引き継ぐ。70年から渋谷教育学園理事長。校長兼理事長として83年に同幕張高校、86年に同幕張中学をそれぞれ新設。96年に渋谷女子高を改組し、渋谷教育学園渋谷中学・高校を設立。日本私立中学高等学校連合会会長も務めた。
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。