ウーマン・オブ・ザ・イヤー2023、全受賞者を発表
大賞はクラシコムの佐藤友子さん
女性のキャリアとライフスタイルを支援する月刊誌『日経WOMAN』(日経BP 東京都港区、編集長:藤川明日香)は、「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2023」の大賞者・株式会社クラシコム取締役 佐藤友子さん(46)を含む、今年の受賞者7人を決定いたしました。
佐藤さんは2006年に兄とクラシコムを創業し、インテリア雑貨や食器、アパレル、コスメなどを取り扱うECサイト「北欧、暮らしの道具店」を2007年に開業。既存のECサイトの枠を超えた多様なチャネルで独自の世界観を発信し、熱いファンを獲得。創業以来一度も資金調達することなく、2022年には年商51億円を突破、8月に東証グロース市場に上場を果たしました。そのビジネスの独自性や成功度、キャリアの築き方が評価され、今年の大賞となりました。
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2023総括
コロナ禍、ウクライナ問題、円安と、2022年も世界が大きく揺れ動きました。そんな先行き不透明で誰もが不安を感じるこの時代でも、ウーマン・オブ・ザ・イヤー2023の受賞者7人に共通していたのは、自分の「好きなこと」「やりたこと」を貫き、壁にぶつかっても諦めずに成功をおさめたこと。「やりたいこと」を自己実現するためのキーワードとして審査員が挙げたキーワードは以下4つです。(1)やりたいことに価値を見いだす、(2)周囲をとことん巻き込む、(3)成熟した市場で独自性を出す、(4)自分の感性を信じて諦めない。「自分らしく生きることが人生を豊かにする」という価値観を信じて北欧文化を軸に事業展開した大賞の佐藤さんをはじめ、通常は削られる「無駄」に価値を見いだしたものづくりを突き詰めるクリエイター、10代のころに決意した事業承継を完遂した社長、「コロナ禍で口紅は売れない」セオリーをはねのけた開発者、日本のお菓子のサブスクで日本文化を世界に発信する起業家、難民認定待ちの来日難民をグローバル人材として就労支援するNPOの代表、いち早くオンラインイベントに商機を見いだした起業家――。自分の感性を信じて軸をぶらさず、壁にぶつかっても粘り強く進んでいく、そしてピンチのときには周囲を巻き込んで力を借りる。そうすれば、おのずと道が開けることを、今年の受賞者たちは示してくれました。
ウーマン・オブ・ザ・イヤー2023 受賞者
株式会社クラシコム 取締役 佐藤友子さん(46歳)
共感を呼ぶ独自メディアでECサイトに熱いファンを獲得。
年商51億円を突破し、東証上場も果たす

佐藤友子(さとう・ともこ)さん
1975年神奈川県生まれ。高校卒業後、アルバイトや契約社員として職を転々とした後、結婚。インテリア事務所を経て兄とクラシコムを創業し、ECサイト「北欧、暮らしの道具店」を開業、現在に至る。1児の母。
2006年に兄である青木耕平さんと佐藤さんが創業。「フィットする暮らし、つくろう」をミッションに、雑貨、アパレル、コスメなどの物販や、暮らしにまつわるコンテンツ配信を手がけるオンライン・プラットフォーム「北欧、暮らしの道具店」を運営。読み物などのコンテンツを充実させるだけでなく、YouTubeやSNSなど多様なチャネルで独自の世界観を伝え、それに共感した熱量の高いファンも多い。2022年8月に東証グロース市場に上場。
佐藤さんは2006年に兄の青木耕平さんとクラシコムを創業し、食器やインテリア雑貨、アパレル、コスメなどを取り扱うECサイト「北欧、暮らしの道具店」を2007年にスタート。「北欧、暮らしの道具店」の店長として、独自の世界観をつくり上げてきた。ECサイト上に、商品紹介だけでなく、暮らしに関するコラムやレシピ、インタビューなど月70本の記事を更新。読み物を充実させ、「売り場」ではなく、「モノやコトに出合える場」にすることを徹底してファンを増やしてきた。多様なチャネルでファンとつながりをつくっており、メルマガやYouTube、インスタグラムなどの登録者数は延べ560万人。2018年には初製作したYouTubeのオリジナルドラマが好評を得てシリーズ化し、映画も製作。隔週日曜日に配信しているインターネットラジオは累計再生1200万回超えという人気ぶりに。今年8月には、創業当初から一度も資金調達せずに、東証グロース市場に上場を果たした。
「好きなこと」を仕事にして大成功を収めた佐藤さんだが、実は10代、20代は職を転々とし、「何をやっても続かない」と自分を否定し続けていた時期もあったという。常に悩み、失敗を経験しながらも、自分のすべきことを模索して誠実に取り組んできたことが、現在のキャリアにつながった。顧客や従業員にとって居心地のいい場をつくることにフォーカスする生き方、自分にフィットする経営者像を体現する姿は、自分らしい生き方を模索する多くの働く女性を勇気づけるロールモデルになると編集部は考えている。

遠藤さんは2001年にカネボウ化粧品(現・花王)に入社して以来、一貫して化粧品開発を担当。2019年にコスメブランドKATE(ケイト)の開発チームのリーダーとなり、2021年5月に発売した口紅、「リップモンスター」を手がけた。「モンスターの棲む世界」を意識し、チームメンバーとともに、「2:00AM」「ラスボス」「欲望の塊」などユニークなネーミングを考案。落ちにくさとツヤ、潤いを両立した機能性も相まって、発売以来、累計出荷本数 550 万本以上の大ヒット商品に。SNSでのバズらせ戦略も功を奏し、いまだに入手困難な状態が続いている。「コロナ禍で口紅は売れない」という常識を見事に覆した。
竹下真由(たけした・まゆ)さん(41歳)
竹下製菓株式会社 代表取締役社長
「ブラックモンブラン」の製菓会社を事業承継。
M&Aなどの多角化経営で売上200%超に

発売から53年、九州を中心に根強いファンを持つアイスバー「ブラックモンブラン」を手がける佐賀の竹下製菓を6年前に事業承継。10代の頃に「私が継ぐ」と決め、大学では経営工学を学び、新卒でアクセンチュアに入社。コンサルタント経験を生かして組織・業務改革を推進、地方企業のM&Aを積極的に行うなどして、社長就任前と比較するとグループ全体の売り上げは200%超に。年間数千万円に及んだ廃棄ロスも、原料見直しや包材開発で3分の1まで抑え込んだ。また、父から受け継いだホテル経営も、2022年春に2棟目を大分県の別府駅前に開業。着実に事業を拡大させている。
近本あゆみ(ちかもと・あゆみ)さん(38歳)
株式会社ICHIGO 代表取締役CEO
「お菓子のサブスク」の越境ECを展開し、起業6年目で年商40億円に成長。
世界180の国と地域に日本の菓子や文化の魅力を発信

2015年から海外向けに日本のお菓子を詰め込んだボックスをサブスクリプション(定額課金)で販売するサービスを開始。コロナ禍で国際配送がストップ、梱包材の値上げなど逆境もあったが、粘り強い交渉力で乗り切った。世界180の国と地域に日本のお菓子やキャラクターグッズを届け、起業6年目で年商40億円に。2021年にスタートした和菓子や和雑貨を詰めた「Sakuraco」では、京都や沖縄など地域の商品を詰め合わせて販売。コロナ禍でインバウンド消費が激減して苦しむ地方の菓子メーカーの新たな海外販路創出をサポート。ガイドブックとして封入する冊子には文化や和菓子の解説も詰め、日本の魅力を世界に発信する架け橋になっている。
藤原麻里菜(ふじわら・まりな)さん(29歳)
株式会社無駄 代表取締役 コンテンツクリエイター、文筆家
人の心を豊かにする「無駄づくり」活動を展開。
新しい価値観を生み出し、独自のキャリアを形成

独創的なものづくりが人気のクリエイター。「無駄づくり」と題して作った作品を、You TubeやツイッターなどのSNSで発信し続ける。これまでに制作した作品は「オンライン飲み会緊急脱出マシーン」「水がびしゃびしゃになるよう計算されたスプーン」「インスタ映え台無しマシーン」など200点以上で、台湾など国内外での展示会や、企業コラボの作品も世の中から高い評価を得ている。無駄づくりの理由を「無駄をあえて生み出すことで心の余白が変わってくる」と語る。コロナ禍で不要不急の行動が戒められ、「無駄」が排除されがちな時代に、社会の役に立たないと思われている「無駄なもの」をブレることなくつくり続け、独自のキャリアを築いた姿勢は多くの人々にインパクトを与えている。
山本理恵(やまもと・りえ)さん(34歳)
株式会社EventHub 代表取締役CEO
受注ゼロからオンラインサービスにいち早く転換。
累計60万人が使用するイベントシステムで人をつなげ、世界を近づける

参加者同士のつながりが生まれにくい日本のイベント業界に商機があると考え、2016年にリアルイベント支援サービスの会社を起業。しかし事業が軌道に乗り始めたころに、コロナ禍で受注がゼロに。そこでいち早くオンラインイベントシステムに転換したことで受注が大きく伸び、官公庁や企業、学会など幅広いジャンルで累計60万人が使用するBtoB支援ツールに成長させた。アメリカで生まれ育ち、日本のビジネス作法に慣れずつらい思いをしたこともあるが、異文化をリスペクトする姿勢が育まれたことで、アメリカで浸透していたオンラインイベントや参加者がつながりやすいイベント支援ツールが日本でも成功すると確信。逆境を商機に転換させた。
渡部カンコロンゴ清花(わたなべ・かんころんご・さやか)さん(31歳)
NPO法人WELgee 代表理事
難民認定待ちの来日難民を「グローバル人材」として就労支援。
ウクライナ避難民支援でも注目の社会起業家に

日本の難民認定率は1%程度と極めて低いなか、日本に来た難民申請者を、支援が必要な「弱者」ではなく、祖国で培ったスキルや経験、情熱に光を当てる「グローバル人材」として捉え直し、日本企業への就労をサポートする事業を展開。発想の転換で、長期の在留資格を獲得するという新しい支援の形を構築した。日本企業にとっても、難民申請者が持つスキルや経験を生かした就労支援の実績は、ビジネスの成長にもつながることを証明。大手企業との協働事例も増加している。2022年はウクライナ避難民の来日で、企業からの問い合わせやメディア出演、講演依頼が一気に増加し、社会起業家として注目されている。
「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」は、(1)働く女性のロールモデルを提示する、(2)組織や社会の中に埋もれがちな個人の業績に光を当てる、(3)活躍した女性たちを通して時代の変化の矛先をとらえる、という主旨のもと、1999年から毎年実施しているアワードで、本年が24回目となります。『日経WOMAN』は、1988年の創刊以来、「働く女性」をバックアップしてきました。今後も「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」を通じ、社会で活躍する女性を表彰することで、時代を担う女性たちを応援していきたいと考えています。なお2022年12月7日発売の『日経WOMAN』2023年1月号では、受賞者紹介と審査結果の詳細を掲載いたします。
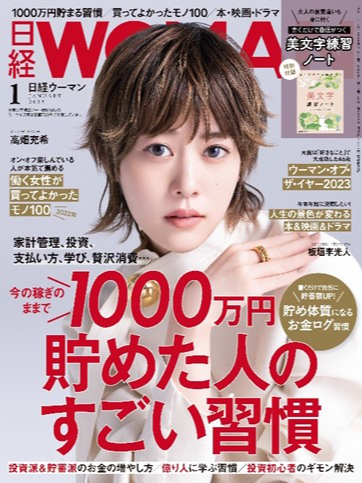
・相内優香さん(テレビ東京 総合編成局アナウンス部)
・入山章栄さん(早稲田大学ビジネススクール 教授)
・関 美和さん(MPower Partners ゼネラル・パートナー)
・村上 臣さん(武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 客員教員)
●審査方法
以下4つの評価基準で採点、審査員4人と編集部の総合得点で決定。
(1)新規性 着眼点の新しさ。イノベーションを起こし、新しい価値観を提示・実現したか。
(2)成功度 今年のビジネスの業績。社会への貢献度。
(3)社会へのインパクト 社会に多くの影響を与え、その発展・改革につなげたか。人々の心を豊かにしたか。
(4)ロールモデル性 自ら切り開いたキャリアの道筋が、読者にとってモデルとなるか。
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。















