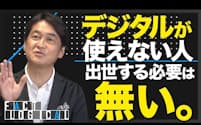バンクシーと医療の未来 Web3.0時代のフォーマット
HDCアトラスクリニック院長 鈴木吉彦

米Google(グーグル)が2015年、動画共有サイト「YouTube(ユーチューブ)」で会員制の有料サービス「YouTube Red(ユーチューブ・レッド、現在のYouTube Premium=ユーチューブ・プレミアム)」を開始すると発表した時、「医療分野は除く」との声明が含まれていて、ハッとしたことがあります。「あのグーグルでさえ医療分野を苦手とするのか」という思いと、「著作権の問題なのだろうか」との思いが脳裏をよぎりました。
医療の学術論文は、学術誌への論文投稿にあたり、投稿先の出版社、それを支える学会などに著作権を「移譲する」という契約をします。
著作権の移譲に抵抗感を抱く医師は、以前はほとんどいませんでした。しかしネット社会の拡大や、知的財産についての意識の高まりなどを背景に、抵抗を示す医師も出てきました。日本を代表する学術誌においても、論文投稿の際に、「著作権の移譲を拒否する」とする医師が増えてきたと聞いています。
「世界初を発見した医師」か「出版社・学会」か、著作権をめぐり関係者がもめるような分野への参入を、グーグルが見送ったのは当然かもしれません。
実は私も「世界初」という論文を学術誌に投稿した経験があります。「世界初のミトコンドリア糖尿病3271番位変異をもつ症例画像」「世界初のミトコンドリア糖尿病3264番位変異をもつ症例画像」「ミトコンドリア遺伝子変異と核遺伝子変異との相関を世界初で証明した図表」「世界初のミトコンドリア糖尿病患者がもつ特有のシンチ画像所見」などは、アメリカ糖尿病学会(ADA)の学術誌に投稿したため、ADAが著作権を保有しています。「日本初のミトコンドリア糖尿病症例の画像や図表」「日本初のI型糖尿病と多発性硬化症の症例の画像や図表」は日本糖尿病学会(JDS)の学会誌「糖尿病」に投稿したのでJDSが著作権を保有しています。
これらの論文に掲載したオリジナルの画像や写真は、自分のパソコンの中に眠っています。ですから、それらを動画編集して、ユーチューブや自分のホームページで公開してもよいはずなのですが、上述のいきさつから、躊躇(ちゅうちょ)してしまします。
こうした問題に悩んでいた時、2つの考えさせる事件が起きました。
1つは、2015年の欧州糖尿病学会で発表された糖尿病治療薬に関する「EMPA-REG OUTCOME Study」という論文が、あまりにも内容が凄すぎて、全世界の医師たちが無断コピーして使い始めたことです。さすがに、これを止めることは著名な米医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン(NEJM)」でも無理だったようです。
こうした動きがあったからでしょうか。翌年の欧州糖尿病学会では、とんでもない発言に出くわしました。あるカンファレンスで、座長が開口一番、「今日のこの発表はネットで公開します。いくらでもコピーしても、使い回ししても構いません。どんどんシェアしてください」と宣言したのです。
さらに驚いたのは同じ年のアメリカ糖尿病学会です。「slides are available(発表スライドは利用可能)」との表示のある講演はいくら写真を撮影しても構わないとなっていたのです。一方、「not available(利用不可)」とあるものは撮影禁止とされていました。研究成果をポスター形式で発表するポスターセッションの会場では、その表示すらない場合もありました。
第2の事件は、正体不明の路上アーティスト、バンクシーの作品が非代替性トークン(NFT、唯一無二のデジタル資産であると証明できるもの)で販売されたことです。デジタル化されたデータを「唯一」のものとして、ネット上で販売できるのであれば、オリジナルをもつ医師は、論文を投稿する前の「世界初の症例の写真」「世界初でみつけた現象の図表」を頒布できるのではないでしょうか。
こうした問題を解決すれば、医療の世界に世界規模の地殻変動が訪れるのではないでしょうか。全く新しい概念にもとづく「医療動画収集のプラットフォーム」の「フォーマット」を作れる可能性があるはずです。バンクシーの「シュレッダー事件」(2018年、当時1億5000万円あまりの価格で落札された絵画作品をその直後、額縁に仕掛けたシュレッダーで細断した)のようなことがあれば、社会は注目してくれるのかもしれません。
デジタル資産を保有する価値を理解することができれば、日本のみならず、世界にむけて、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を活用した自律分散型ネットワーク「Web3.0」的な発想をもつ、医療情報発信プラットフォームを構築することも、夢ではないのです。

1957年山形県生まれ。83年慶大医学部卒。東京都済生会中央病院で糖尿病治療を専門に研さんを積む。 その後、国立栄養研究所、日本医科大学老人病研究所(元客員教授)などを経て、現在はHDCアトラスクリニック(東京・千代田)の院長として診療にあたる。
関連リンク
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。