普及なるかオンライン診療 DXが変える医師の働き方
HDCアトラスクリニック院長 鈴木吉彦

第2次世界大戦が終わり20年後。山形県の農村で病院を営んでいた私の実家には、町内なら無料でかけられる「黒」電話がありました。町内限定だったので、電話番号はたったの3桁でした。
その電話がなると夜中でも母が起きて、寝ている父を起こし、往診に送り出していました。当時、開業医は救急車がわり。ひどい時には夜中に何回も起こされて往診へ。あまりの重労働に当時の医師の寿命は短いのが当然と考えられていました。戦争で多くの若者が亡くなり、同時に医師の数も減っていたからです。
夜中に往診にいった父は患者さんから、お礼に、とばかりにお酒をごちそうになり、車で送られて帰ってきました。でも酔いがさめないうちに、また呼ばれることもありました。
その後、医大の数が増え医師数が増え、救急車が発達することで、この問題は解決されました。
日本では、医師法第17条に、「医師でなければ、医業をなしてはならない」という規定があります。この法律が、昔は開業医の寿命を短くさせた原因のひとつとなり、新型コロナウイルス禍の中で、日本でのワクチン接種の開始の遅れや、病床が空いているはずなのに入院できない「幽霊病床」の理由となっているように思えます。
私が病院の勤務医だったときに、とある患者が夜中に亡くなったことがありました。死亡宣告は当直医がしたものの、死亡にいたった経緯については、難病だったため、担当医が説明しなくてはなりませんでした。翌朝までに死亡診断書がないと葬儀が遅れるという理由から、主治医の私が呼び出されました。夜も遅かったので晩酌をすませて、顔が赤らんでいたため、とっさに顔に白く薄化粧(なんと、マヨネーズ!)をほどこし、ご遺族に説明したことがあります。
「夜間医療」には、さまざまな苦労があります。この難題について最近、「自宅待機中の医師がオンライン医療で対応」できるという、「新たな制度」についての報道がありました。https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t349/202201/573460.html
この制度変更は夜間医療に、大きな影響をもたらします。医師は自宅にいて、オンラインで患者を診察することができます。患者さんは「119」に電話しなくても開業医や専門医に、オンラインで相談できます。「コロナ禍医療」のためだけではなく、夜間医療のあり方を、一変させる大変革になるかもしれません。昼夜を問わず24時間、医師がいるクリニックができますから、その「医師の求人・求職」市場にも、コンビニが24時間営業になった時なみの、大きな衝撃を与える事は必須です。私のクリニックなら「夜間専用の医師」を雇用することができてしまいます。
「二刀流」医師が誕生!?
昼から夕方まで他の仕事をして、夕方から夜だけ医師の仕事をする「二刀流」をもつ医師もうまれてくることでしょう。「医師に転身したスポーツ選手」と検索すると、五輪金メダリストやメジャーリーガーもたくさん、見つけることができます。元カージナルスのマーク・ハミルトンは医学部を卒業し、コロナ治療の最先端に立つと現地メディアが報じています。野球選手と医師との「二刀流」も可能になる時代は近いと考えます。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61758000R20C20A7I00000/
こうした事態を想定して、実際に「オンライン医療」システムを構築していた医師は少ないかもしれません。ですが、私にとっては、想定範囲内でした。新しい「フォーマット」を作ればいいわけです。いつか、それを、このコラムでご紹介します。
ただ、ひとつだけ心配な状況があります。死亡診断書を書かなくてはいけない場合です。死亡診断書に、誤診や偽造は許されません。天才外科医を主人公にした韓国ドラマ「浪漫ドクター キム・サブ」には、病死か外因死かをめぐり死亡診断書の偽造が、大波乱を及ぼす印象深いエピソードがありました。
医師がしっかりとした所見にもとづき、判断して正確な診断名を書かないと、大変な犯罪につながりかねません。万が一であっても、「他殺」を「自殺」と診断するようなことがあってはならないのです。
日本の「オンライン医療」についての厚生労働省の指針では、「プライバシーが保たれるように、患者側、医師側ともに録音、録画、撮影を同意なしに行うことがないよう確認すること」とされています。いわば録画は「例外」といえるのでしょう。実際、メジャーなオンライン診療アプリには「録画」機能は削除されているものもあります。ですが、もし犯罪性があるような場合には、医師も医師の立場を守るために「録画」が必要になることがあるかもしれません。
訴訟大国のアメリカでも、コロナ禍をきっかけに「オンライン医療」が急速に普及しましたが、「保険制度」の違いが大きな差となりました。医療機関の患者さんに対する診察代金請求を保険会社が代行してくれることや、もともと、「時間予約をいれてから医師と予約した時間に患者が訪問して診察をうける」という、通常の完全アポイント制度が当然だった事、などの理由もありますが、「録画ができるか、できないか」の違いも、多分にあったのではないか、と思います。そして、日本で、オンライン会議サービス「Zoom(ズーム)」などをお薦めできないのは、自動的に録画が始まるように設定されていることがあるからです。
さらに細かい事を言えば、治療の内容ではなく、「必要な説明をしなかった」ことが問題とされ裁判になる事もあります。医療機関で標準治療とは異なる治療が行われた際、事前説明の内容などを巡ってトラブルになり、裁判に発展する事例も見られます。夜間医療、救急医療、自由診療、標準治療外医療において、医師に求められる注意事項は半端なものではありません。
現代の「常識」が未来では「非常識」に
ただし現代での「常識」が、未来では「非常識」になることはあるかもしれません。かつて、がんの告知がそうでした。ですから「原則」として「録画」ができるか、できないか、の問題は、将来、身近な問題に発展していく予感があります。
また、もう一つ、日本のオンライン医療には、「チャットでのURL 表示をクリックしても、URLのある箇所に飛べない」という問題もあります。まだまだ、世界との違い、「差異」を掘り下げて議論していかなくてはいけないのが、日本の「オンライン医療」のようです。
そして、特に「世界の未来」を考えるに注意すべきは、上記のような「日本のルール」はドメスティックルールであり、「世界のルール」つまり「インターナショナルルール」「グローバルルール」ではない、という点です。「ドメスティック」にも、「グローバル」にも対応できる「フォーマット」を作れる能力がある医師がいるとしたら、海外事情にも詳しく、医師(臨床家&学術業績)としての実力もあり、かつ、IT分野での、かなりの成功体験があり、世界に通じる「道徳心」と「倫理観」と「正義感」とで世界をまとめる力がある医師でないといけないと感じています。
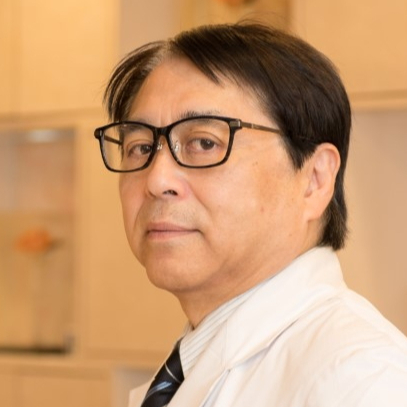
1957年山形県生まれ。83年慶大医学部卒。東京都済生会中央病院で糖尿病治療を専門に研さんを積む。 その後、国立栄養研究所、日本医科大学老人病研究所(元客員教授)などを経て、現在はHDCアトラスクリニック(東京・千代田)の院長として診療にあたる。
関連リンク
健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。















