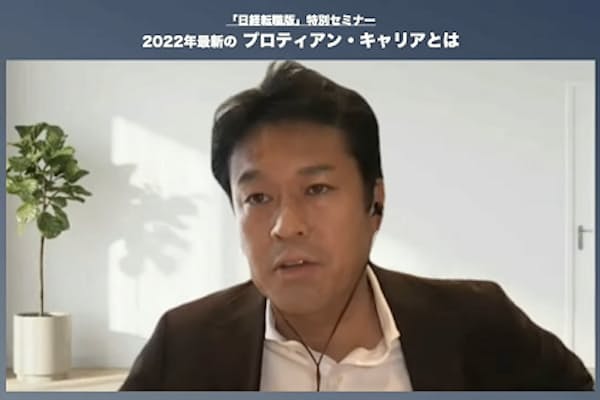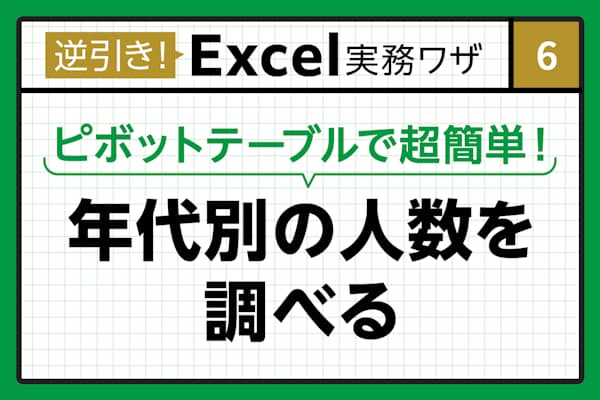週休3日制はラッキーばかりではない 導入広がるか?
あしたのマイキャリア最近よく耳にするようになった「週休3日制」。政府も本格的に議論を進めようとしており、2022年に入ってから導入を表明する企業が相次いでいる。注目される背景と実態について、企業の働き方改革に多く関わり、企業現場に詳しいリクルートマネジメントソリューションズのエグゼクティブコンサルタント・武藤久美子(ぶとう・くみこ)さんに話を聞いた。
週休3日制 3つのタイプ
――「週休3日制」と言っても、大きく分けて3つのタイプがあるそうですね。
「労働時間と給与の観点で大きく3つに分けられます。『(A)週の労働時間が変わらず、給与も変わらないもの』『(B)週の労働時間が減り、給与も減るもの』『(C)週の労働時間が減るが、給与は変わらないもの』の3つです。今のところ日本で導入が多いのはAタイプやBタイプです」
「Aはさらに2つに分けられます。"3日目"の休みを週のうちにいつにするか、『自分で決められるもの(選択式)』『会社であらかじめ一律に、休日として設定されているもの』の2つがあります。前者は、出勤日は長い時間働き、その代わりに休む日をもうける "スーパーフレックス制の拡大版"のように捉えることもできます。現状の社員の労働実態がこれに近いという企業であれば、これまでの働き方と大きく変わらないため、企業・社員双方にとって受け入れやすいといえます」
「Bはおもに介護、看護、育児など家庭の状況と両立しながら働く社員が利用することを想定しています。現時点で当事者ではなくても制度があることで安心感につながる、保険のような役割を果たしているといえるでしょう」
「Cは働く側にとっては魅力的、言い換えると企業にとっては人材を惹きつけ、引き留めるのに効果的な策です。海外ではCを導入している企業も多く、そのような企業と人材獲得競争をしなければならない場合は、この体制を検討する必要性が増すでしょう」
――週休3日制は働く人々にどのような影響がありますか。
「全社員が当事者となる点で、インパクトのある施策です。例えば『副業解禁』は副業を希望する人のみ、男性育休にしても、取得者という点では該当年齢の子供をもつ社員が対象です。もちろん副業解禁や男性育休も会社全体の働き方を考えようという施策ですが、週休3日制は、実際に社員全員が対象となる可能性があります。もともとの制度の枠組みからして、週休3日制は影響度が大きくなりやすいのです」
「労働時間に直接関係するだけに、働き手にとっては自分の生産性について考えるきっかけになります。リモートワークの普及もあって"自律"がキーワードになることの多い昨今ですが、『週休3日にした場合、対応できるだろうか?』と時間と成果のあげ方について見直す機会になるでしょう」