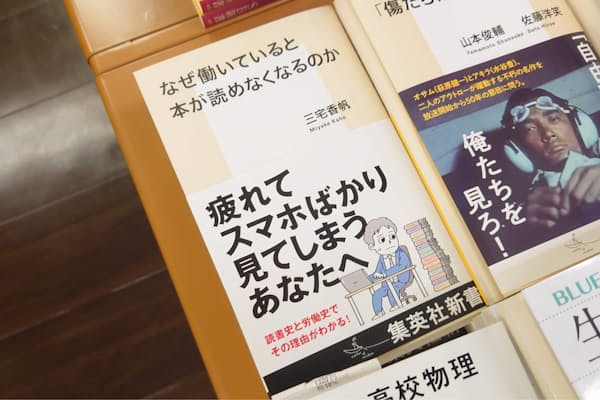人間関係表すリファレンスチェック 愛あるコメントも
解剖リファレンスチェック(後編)
あしたのマイキャリア転職希望者(求職者)の働きぶりや経歴について、同僚や上司に照会する「リファレンスチェック」は、IT(情報技術)企業やベンチャー企業だけでなく、大手企業にも広がりつつあります。ところが、同僚や上司にどんな質問がいくのかや、採用担当者が選考にどう生かしているのかなど、具体的なところはあまり知られていません。リファレンスチェックサービスを提供する企業の担当者と、中途採用の選考にリファレンスチェックを使っている企業の人事担当者に、実際の運用について聞きました。(前編はこちら )
――「back check」を使ったリファレンスチェックはどのようなものなのか、流れを教えてください。
「まず、採用企業が候補者(選考を受けている人)にリファレンスチェックを実施したいと説明し、同意を得たうえで、候補者自身にback check上で推薦者(回答する第三者)の情報を登録してもらいます。そうすると推薦者に案内メールが届き、用意された質問に回答するという流れになります。なりすまし防止のため、名刺や身分証明書など本人確認情報の登録もプロセスに含まれています」
「推薦者が回答を終えると、企業は結果リポートをback check上で見ることができます。候補者は閲覧できません」
文字量に関係性が表れる
――具体的にどういった質問がされるのか気になります。
「記述式質問で多いのは『相性が良かったメンターや上司はどのようなタイプの人物か』『コミュニケーションをとるのに苦労したのはどういうタイプの人物か』『候補者がもう一段階成長するためにはどうすればよいと思うか』『また一緒に働きたいと思うか』といったものです」
「社内異動ではあらかじめ異動前・後の上司同士が対象の社員について情報共有をすることがあると思いますが、それに近いイメージでしょうか。面接では『今』の情報しか知りえないのに対し、リファレンスチェックでは長い時間、一緒に働いてきたからこそわかる情報を提供してもらいます。『時間軸』がポイントになります」

ROXX取締役COOの山田浩輝さん
「質問は自由記述式で回答するものに加え、4段階の選択式のものもあります。記述量にはとくに目安を設定していませんが、リファレンスチェックのリポート1件あたり平均1200字ほど。文字量から推薦者と候補者の関係性や評価がうかがえることもあります。全ての項目で1文しか書いてもらえなかったら、それもまたリファレンスチェック。築いてきた信頼関係が表れる部分でもあります」