人口75万人 大都市だったアンコール・ワットの歴史

うっそうとしたジャングルの中に突如現れる熱い夢の跡、アンコール・ワット。そこは石造りの壮大な都市で、優雅にそびえる塔や広々とした中庭と回廊、複雑なレリーフなどが残されている。
アンコール・ワットは、およそ900年前に古代クメール王朝によって建てられた寺院で、カンボジア北西部、トンレサップ湖の岸辺に位置する。この付近には、今も数百の寺院が残っているが、群を抜いて有名なのがこのアンコール・ワットだ。広さ約1.6平方キロメートルに及ぶ世界最大級の宗教建造物は、人類の文化的偉業のひとつであり、現在のカンボジアの国旗にも描かれている。
クメール語で「王都の寺院」を意味するアンコール・ワットの建造が始まったのは12世紀前半のこと。クメール王スーリヤヴァルマン2世(在位紀元1113年〜1150年ごろ)が、自らの葬祭殿とするために建造したと考えられている。
アンコール・ワットはヒンドゥー教の影響を色濃く受けており、もともとはブラー・ヴィシュヌロカ(ヴィシュヌの聖なる住居という意味)と呼ばれていた。ヴィシュヌ、シヴァ、ブラフマーといったヒンドゥーの神々の姿は、アンコール・ワットの多くの彫刻にも残されている。
もっとも目を引く建造物は、中央にある5つの円すい形の塔だ。そのうち4つは四隅に、1つは中心に位置する。蓮(はす)が積み重なるようなデザインは、古代インドの世界観で中心にそびえる聖なる山、須弥山(しゅみせん)を象徴する。長さ188メートルの橋を渡って敷地に入り、3つの回廊を抜けて寺院に向かうと、ヒンドゥーの神々、古代クメールの出来事、サンスクリットの大叙事詩『マハーバーラタ』『ラーマーヤナ』の場面など、さまざまな浅浮き彫りを施された内壁が迎えてくれる。

クメールの隆盛
クメール王朝は9世紀から15世紀にかけて繁栄し、広大で豊かな、そして文化程度の高い帝国を築き上げた。支配地域は、現在のミャンマーからベトナムまで、東南アジアの大陸部ほとんどに及んだ。都市は河川や幹線道路で結ばれ、現在よりも温暖な気候と豊かな雨のおかげで農産物にも恵まれていたと考えられる。
アンコールの寺院群は、古代クメールの首都アンコールのそばに建造された。高度な建築(アンコール・ワットを見下ろす位置にある9世紀のプノン・バケン寺院など)は、王朝の初期のころからの関心事だった。12世紀には、スーリヤヴァルマン2世のもとで、アンコール・ワットの建造が進み、クメール全域でヒンドゥー教から仏教への転換が行われた。

仏教とヒンドゥー教は、長年にわたって平和裏に共存していた。仏教が初めてカンボジアに入ってきたのは5世紀ごろだ。インドからの商人や布教者がもたらした仏教文化は、カンボジアの歴史に大きな影響を与えることになった。それ以前にすでにヒンドゥー教をカンボジアに伝えていたのもインドで、クメール語はサンスクリット語と関係が深い。
スーリヤヴァルマン2世の死後約30年、1181年に即位したジャヤーヴァルマン7世は、チャム族の侵攻を受けたクメールを復興させ、仏教を国教に定めた。近隣のアンコール・トムにあるバイヨン寺院には、このジャヤーヴァルマン7世の顔をモデルにしたと思われる装飾が多く残されている。アンコール・トムは、新たなクメールの隆盛を象徴する城塞都市で、クメールの新首都となった。当時としては記録的な75万人が暮らしていたとされる。

アンコール・ワットはヒンドゥー教の寺院だったが、1300年代に正式に仏教寺院に改められた。仏教はヒンドゥー教に寛容だったので、仏像は追加されたものの、既存の彫像や彫刻が破壊されたり置き換えられたりすることはなかった。
ヨーロッパ人の到来
だがこのころには、クメール王朝の衰退が始まっていた。そして1430年代にはアンコールが放棄され、その後、 首都は南方の新都市プノンペンに移された。
遷都には、環境的な要因もあったようだ。アンコールには、人工の運河や堤防、貯水池などの高度な仕組みがあった。最大の貯水池だった西バライは、東西8キロメートル、南北2.5キロメートルにおよぶ規模で、高度な技術が使われていた。この水路網が、産業革命前の都市としては最大規模である75万人の住民ののどを潤し、米の栽培にも使われていた。しかし、強烈な季節風や干ばつに繰り返し襲われた結果、灌漑(かんがい)設備が機能しなくなり、都市の衰退につながったものと考えられている。
一帯は再びジャングルに覆われ、都市は深い緑に埋もれた。崩れた塔の間に育った巨木の根が柱や壁に絡みつき、ジャングルと遺跡は一つになった。それでも、ある寺院は決して見捨てられることがなかった。それがアンコール・ワットだ。やがて14世紀末から15世紀初めにかけて、寺院群が再建され、仏教僧たちによって巡礼地として整備された。
16世紀半ばには、ヨーロッパ人がやってくるようになった。当時のポルトガルの商人で歴史家のディオゴ・デ・コートは、「カンボジアのジャングルには都市の遺跡が眠っている。壁はすべて切り出した石でできており、まるでひとつの石でできているように思えるほど、完璧に並べられている。石はまるで大理石のようだ」と書いている。
アンコールの魅力
その後も、アンコールは数世紀にわたって海外からの旅行者を引き寄せ続けた。マレーシアのイスラム教徒をはじめとする東南アジアの商人、日本の仏教徒など、多くの人がカンボジアを訪れるようになったのだ。アンコール・ワットの壁に落書きを残した人さえいた(1612年から1632年までの間に、14の落書きが描かれたことがわかっている)。アンコールの最古の地図として、注釈付きのカラーの図面が残されているが、それは日本人によるものだ。

ヨーロッパ人のアンコールへの憧れが最高潮に達したのは19世紀だった。フランス人探検家であり博物学者のアンリ・ムーオは、英国王立地理学会の援助を受け、1858年4月、愛犬のティンティンとともにタイのバンコクに向けて出港し、1859年後半にアンコールにやってきた。ヨーロッパ人コレクターのために、現地の植物や動物の標本を集めるためだった。
ムーオは3カ月をかけてアンコールを調査し、多くのスケッチや日記を残した。その記録には、アンコールのことだけでなく、クメールの人々のことも記されている。
「この地方は、今もアンコールという名で呼ばれている。なんという壮大な遺跡だろうか。初めて見た者は深い畏敬の念に満たされる。そして、この高度な文明や知識を持ち、このような巨大な建造物を作り上げた強力な民族はいったいどうなったのかと問わずにはいられなくなる」
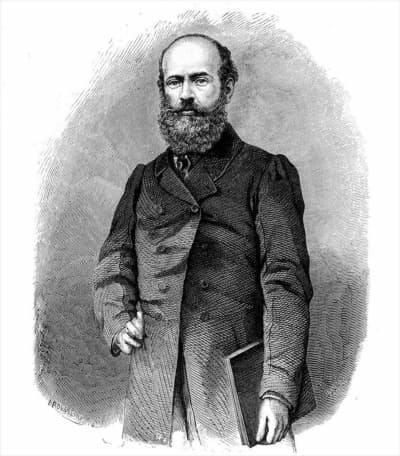
1864年に、精緻なスケッチを含むムーオの著作が出版されると、ヨーロッパ人たちの関心がアンコールに向けられるようになった。1867年には、メコン川の流域調査を行うという名目で、フランスの探検隊がこの地を訪れた。メンバーの1人、ルイ・ドラポルトという若く有望な芸術家が描いたアンコールのイラストによって、その人気は確かなものになった。カンボジア芸術の複製品は、1867年から1922年の間に開催された主要な万国博覧会でも展示され、1931年のパリ植民地博覧会では、アンコール・ワットの実物大模型まで作られた。
(文 VERONICA WALKER、訳 鈴木和博、日経ナショナル ジオグラフィック)
[ナショナル ジオグラフィック 日本版サイト 2022年5月22日付]
関連リンク
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。












