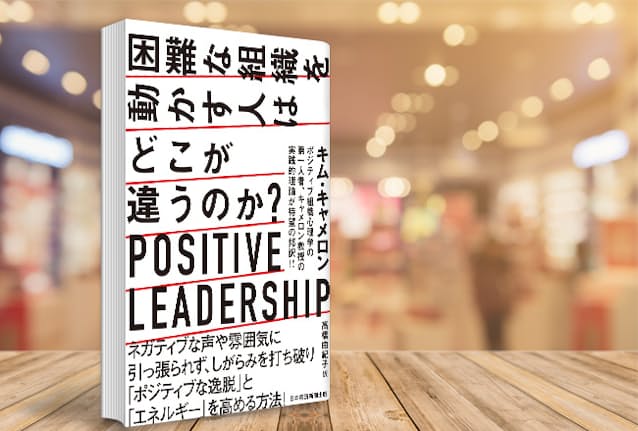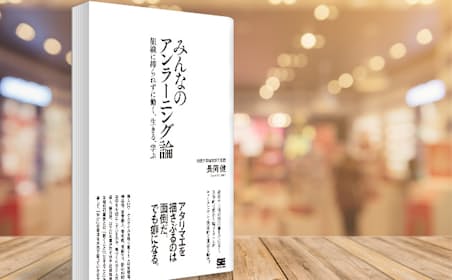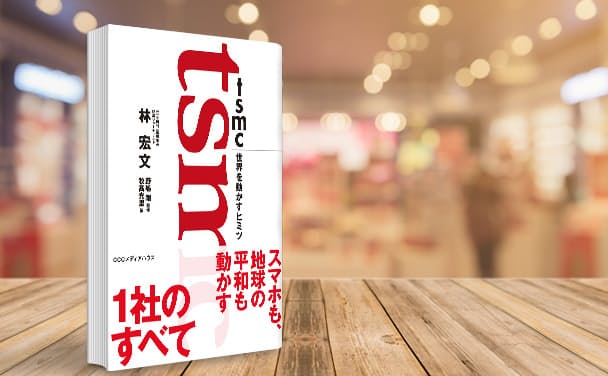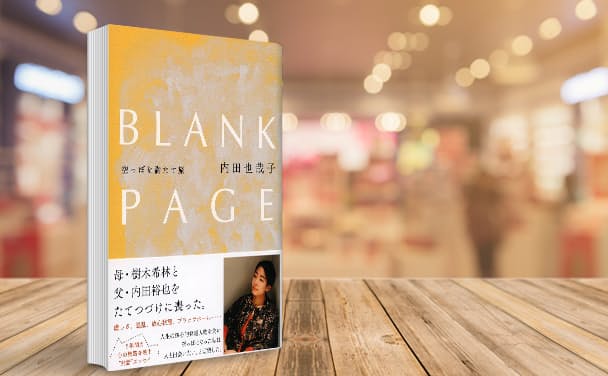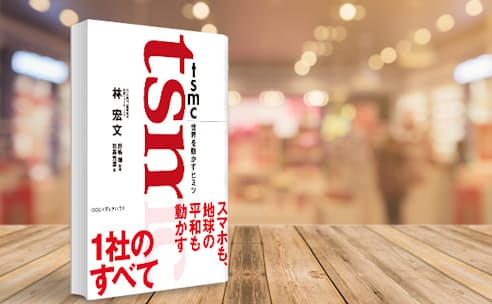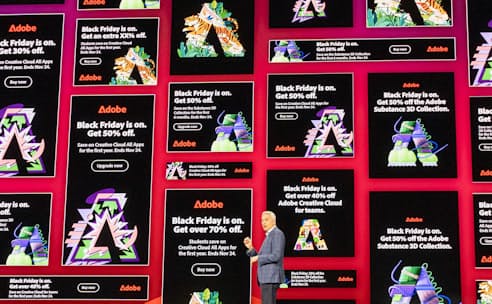思うように成果があがらない、業績が思わしくないなど、組織やチームが何らかの困難に見舞われた時に、リーダーとしてどのように対処しているだろうか? 深刻な顔つきで問題点を探し、部下のミスや欠点を指摘し、反省を促したりしていないだろうか? 特に今は、新型コロナウイルス禍からマイナスの影響を受けやすく、組織もネガティブな思考に陥りがちだ。
だが、本書『困難な組織を動かす人はどこが違うのか?』(高橋由紀子 訳)によると、組織やチームが困難な状況にあるときこそ、ポジティブなリーダーシップが苦境を乗り越えさせ、劇的な成果を生み出すというのだ。
著者のキム・キャメロン氏はミシガン大学ロス・スクール・オブ・ビジネス教授で、ポジティブ組織心理学の第一人者と言われる人物。本書では、組織風土、人間関係、コミュニケーション、意味づけという4つの切り口で、実証的研究に裏づけられた「ポジティブリーダーシップ」の有効性と実用的なアプローチ方法を詳しく解説している。
■ポジティブになるとパフォーマンスが上がる
キャメロン氏がいうポジティブリーダーシップとは何か。それは、メンバー個々の強みや潜在能力を信じ、彼らの最も良い面を引き出すことで、目覚ましい成果を上げようとするリーダーシップなのだそうだ。
その成功例として本書であげられている米国のグリフィン・ホスピタルが興味深い。業績悪化に苦しむ病院の財政を立て直すのに社長兼CEO(最高経営責任者)のパトリック・チャーメル氏が実践、成功したのが、まさしくポジティブリーダーシップだったのだ。
チャーメル氏が人員削減といった、いわば「定番」の経営改革と同時に進めたのが「ポジティブな組織風土」づくり。単に明るく振る舞うだけではない。日々のコミュニケーションを「オープンでウソのない」ように意識して心がける。自分や周囲の「仕事の意味」を問い直し、尊重する。対話や行動に気をつけることで、組織の中に寛容さや楽観性、信頼などが望ましい行動として定着するようにしたそうだ。
精神論と言うなかれ。本書によると、ポジティブな思考や行動、態度が良い結果をもたらすという実証的研究がいくつもある。例えば、楽観的な将来を思い浮かべると脳のより広い範囲が活性化するという。また、喜び、愛情、感謝といった感情を抱くと、多くの情報に注意を向けられるようになるという研究もある。