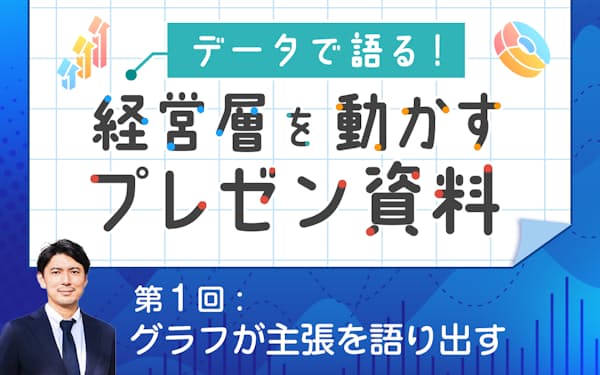夫と別居後、パート勤務ママが独立に向け歩み出す
働きかた研究所代表 平田未緒
働かない夫の浮気が発覚、実家へ戻る
「どうしても、もう一度仕事をしたかったんです」。
正社員で働いていた斎藤裕子さん(仮名/39歳)が、結婚・出産を経てパートで再就職をしてから、今年で10年になる。
10年前、再就職したのは仙台だった。今は名古屋で、やはりパートで働いている。
10年前と違うのは、住んで働いている町だけではない。今は、小学校高学年になった一人息子との、二人暮し。夫とは7年前、子どもが5歳のときに別居した。パートで再就職して3年目のことである。
「別居した理由はお金です。夫は就職しても長つづきしない人でした。結婚した当初はそうでもなかったのですが、次第にカード支払いやキャッシングで、後先考えずにお金を使うようになりました。いつしか毎月末の銀行口座の残高は、常にマイナスという状態に。最初はそのマイナスを、私が独身時代に働いて貯めた預金や、パートで働き始めてからは微々たるそのお給料で、補てんしていました」
収入以上に使うことが、いったいどういう事態を招くのか、どれだけ言っても「同じことの繰り返し」。状況を知った親戚の紹介などにより、なんとか正社員での再就職を果たしても、「仕事がきつい」「上司と合わない」など理由をつけてはやめてしまう。
斎藤さんはもともと真面目で、堅実な性格だ。夫のしたこととはいえ、いわれのない借金に追われる生活は、次第に心をむしばんでいく。
「これ以上この人と一緒に生きていくのは、無理かもしれない」

こう思い始めた矢先、夫のカバンの中に見つけたのが避妊具だった。自分に対するものではない。やり場のない怒り。言いようのないむなしさ。落胆、そして絶望。
しかし斎藤さんは心の傷を、再スタートへのエネルギーへと変換した。結婚するまでずっと名古屋で、親と同居していた斎藤さんは、親に事情を話して、出戻ることに心を決めた。夫が外出している間に、少しずつアパートの荷物をまとめては、宅急便で実家に送った。そして、ある日突然、子どもを連れて郷里の名古屋に帰ったのだ。
子どもが2歳の時、パートで復職
結婚するまで斎藤さんは名古屋で正社員として働いていた。
「短大卒業後、新卒で生命保険の代理店に入社し、正社員として働いていました。結婚するまで9年間、親元から通勤していたんです」
そんな斎藤さんが結婚を決意した相手が、仙台の人だった。相手が職を転々としていることや、生まれ育った名古屋を離れることに迷いはあったが、その人が好きだった。その思い1つで仙台で暮らすことを決めたのだ。
結婚後はすぐに子どもができ、毎日はそれなりに忙しかった。しかし仙台は何の縁もなかった土地。新生児を抱え自由に外出もできないなか、新たに築く人間関係はすべて子どもか夫つながりということになる。
要するに、誰に会っても「○○ちゃんのお母さん」か「斎藤さんの奥さん」だ。そうではない、自分自身を見てもらえる場が欲しかった。また退職して初めて、「家にこもっているのは性に合わない」と実感もしたという。
子どもが2歳のときに就職活動を開始。ハローワークの紹介で、仙台市にある生命保険会社の面接を受けてすぐ、採用された。仕事の内容は窓口の後方支援事務だった。
「勤務時間は10時~16時。時給は750円でした。安いなあと思いましたが、保育園のお迎えなどを思うと、扶養の範囲内で働く選択が妥当でした」
一方で、すでにその頃、「すぐにでも現金が欲しい」状況になっていた。生活はギリギリ。しかも自分の知らないカード支払いやキャッシングによるマイナスが、だんだん大きくなっていた。
お金をめぐり、日々夫と口論になる。そんな折、決まって迫られたのが、夫の親との同居だった。
夫が親との同居を望む理由は「家賃や光熱費が浮くから」だ。「お前が同居しないから、家賃がかかって生活が苦しいんだ」となじられた。
もちろん家賃が浮けば生活は楽になる。でも斎藤さんは、同居は絶対に嫌だった。結婚して分かったことだが、夫の細かな借金を、義父母はずっと肩代わり返済していたのだ。
「大人なのに」。生活は苦しくとも、自立していたかった。
正社員とパートの大きすぎる待遇差
親から独立できない夫に対する意地もあり、仕事にはまじめに取り組んだ。
職場は恒常的に忙しかった。誰かが辞めても、めったに人の補充はない。パートとして働いていても、誰も「帰っていいよ」と言ってはくれず、残業は日常的。保育園のお迎えも、18時の閉園ギリギリになることが増えていった。
「時給は1年に1度、評価によって見直されました。評価は、自分、直属の上司、支店長の3人が、定められた項目に従って、それぞれ5段階で行います。その上で、この3人で面談し、評価のすり合わせを行って、時給が決まる仕組みです。私の場合、2年で上限の時給850円に到達しました」
評価されるのはもちろんうれしい。しかし、パートでいる以上、どんなに頑張ってもこれより賃金は上がらないのが現実だった。
加えて斎藤さんには、納得できないことが2つあった。1つはパートのサービス残業。もう1つは、正社員との給与格差についてである。
「パートは全員、年収103万円以内を希望していました。ところが日常的に残業をしていると12月末日を待たずにこれを超えてしまいます。といって、最繁忙期に『休みたい』とも言えず、結果的に多くのパートが、サービス残業していました」
一方、正社員との給与格差についてはこう考える。
「仕事の違いは『営業の有無』。商品の販売をするか否かです。もちろん営業は大変だし、少しでも早く帰れたり、子どもの病気や保育園の行事を理由に休めるのは、パートで働く魅力です。でも、それだけで一般職女性の年収はサービス残業で働くパートのほぼ4倍です。正社員とパートの給与格差は大きすぎると感じました」
「正社員にならないか」という打診も受けたけれど
別居と同時に斎藤さんは、仙台の生命保険会社を退職した。名古屋に戻って仕事を探し、今はまた保険会社で働いている。
会社は違っても、保険会社の窓口の後方支援事務仕事の内容に大差はない。そんななかで、正社員として9年、ほぼフルタイムでのパートとして10年働いてきた。
20年近くに及ぶ長いキャリアに裏打ちされた、ミスのない安定した仕事ぶりが、会社の目にとまったのだろう。昨年、雇用形態の区別なく「がんばった」人に贈られる社長賞を、支店の推薦を得て受賞した。
「本社に呼ばれて、式典に出席し、社長から表彰状を手渡されました。その後は役員や人事部長も一緒に、立食パーティで会食です」
時給は1300円にまで増えている。現在の会社には正社員登用の道もあり、上司からは「正社員にならないか」と打診もされている。正社員になれば安定し、賞与も出る。それでも斎藤さんは、パートを選んだ。
「正社員になると、転居を伴わない範囲ではありますが、転勤があるのです。今は実家を出て、子どもと二人暮らしです。自宅から徒歩圏内の支店だから、家事や子どものことと仕事を、なんとか両立させています。これが正社員となり、仮に通勤1時間となってしまうと、年収的には余裕が出ると思いますが、収入以外の面で生活が破たんしてしまうと思うのです」
斎藤さんが正社員で働いていた頃、「39度の熱を出しても休めなかった」のを思い出す。結婚し、家事や育児もこなす今、家族や親の協力が見込めないのに、とても当時のようには働けない。
「夫とは音信不通で、金銭的にも一切支援を受けていませんが、まだ正式に離婚もできていません。こうした状況のせいか、子どもも精神的に不安定です。やることが山積し、とても正社員には踏み切れないのです」
ジレンマはある。でも、夫に耐えていたころよりはずっといい
自らパートを選んでいるが、割り切れないものはある。
キャリアを積めば積むほど、周囲から頼られる。若い正社員から、質問をされることもしばしばだ。例外的な処理が必要だったり、判断に迷う案件や、クレーム対応などを、決まって「押しつけてくる」正社員もいる。
「やっぱり腹が立ちますよね。私は、自分がやっている仕事がどのレベルなのか。同じ仕事をする正社員の賃金がどのくらいなのか、知っていますから」
自らの収入が子どもとの生活を支えている。腹が立つことがどれだけあっても、仕事を辞めるわけにはいかない。正社員になることも、生活状況が許さない。いかんともしがたいジレンマ。
「いろいろと思うことはあります。でも、これが私が選んできた生き方です。短大に通っていたころは、自分がこんな人生を歩むとは想像もしなかったけれど、夫の借金に苦しみながら働いていた当時より、今の方がずっといいと思えますから」
今は対処のしようがない問題も、苦しくとも意思をもって働いていれば、いずれ環境が変わり、解決してくれると考える。
来年には、子どもも中学生になる。部活で帰宅が遅くなったり、友達同士でどこかに行ったり、塾通いも必要になるだろう。そうなれば、子どもとの関係が変わり、必要なお金も増えてくる。その時に向けて、どうするか。
今の会社で正社員になるのか、あるいは他の仕事を探すのか。自らの心の声に耳を澄ませつつ、新たな道へのスタートを切るタイミングは、そう遠くないかもしれないと思っている。

株式会社働きかた研究所代表取締役。早稲田大学卒業後、情報誌記者・編集者として勤務。その後求人広告企業株式会社アイデムに入社、人事マネジメント情報誌3誌の編集長を歴任する。この間、パート・アルバイトの戦力化などをテーマに、数多くの企業ならびに働く個人を取材。雇用に関する現場情報に詳しい。2009年よりアイデム人と仕事研究所所長。2013年同職を辞し、「企業におけるパート・アルバイトの活躍支援」事業で独立。著書に『パート・アルバイトの活かし方・育て方~相思相愛を実現する10ステップマネジメント~』『なぜあの会社には使える人材が集まるのか~失敗しない採用の法則』(PHP研究所)などがある。社会保障審議会の委員等、公職も多数。
[日経DUAL2014年2月21日掲載記事を基に再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。