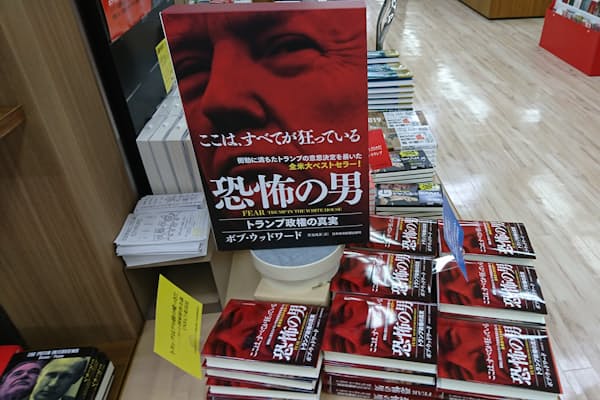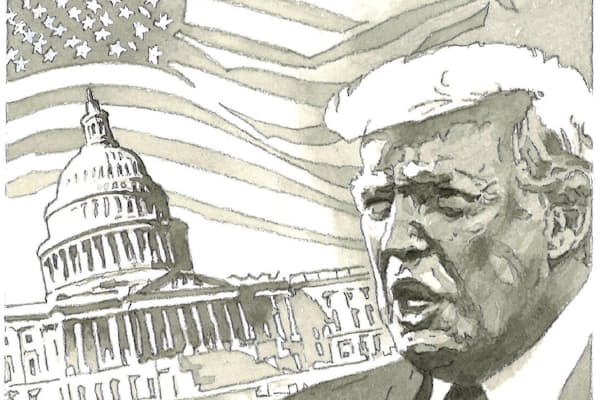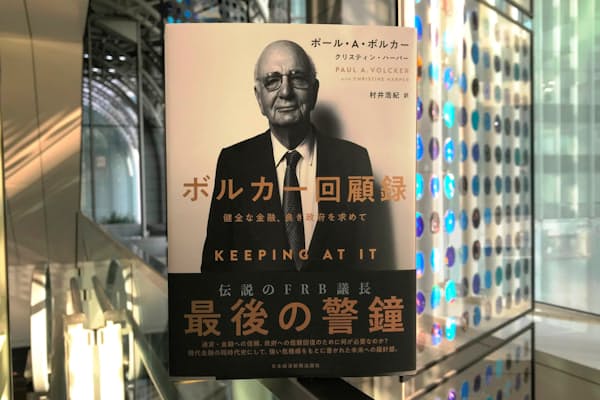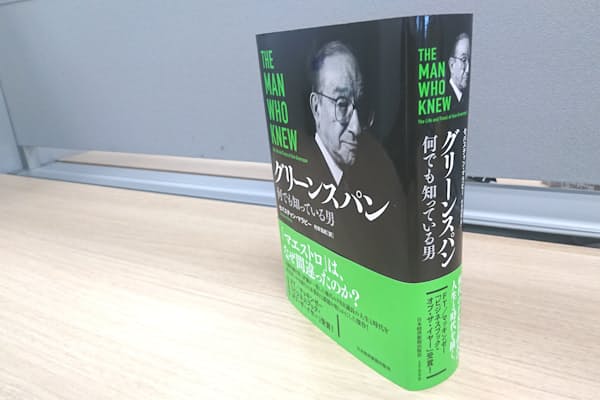米外交に潜む独善性 対中政策を転換させた男が警鐘
『戦場としての世界:自由世界を守るための闘い』訳者に聞く
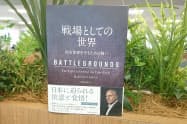
『戦場としての世界:自由世界を守るための闘い』 日本経済新聞出版
ホワイトハウスに陣取る外交・安全保障政策の司令塔(国家安全保障担当大統領補佐官=ナショナル・セキュリティー・アドバイザー)といえば、読者の多くはヘンリー・キッシンジャー氏(ニクソン政権およびフォード政権、98歳)やズビグニュー・ブレジンスキー氏(カーター政権、故人)を思い浮かべるかもしれない。2人とも退任後も論客として鳴らし、著書の大半が日本語に翻訳された。
このポストをトランプ政権の前半、2017-18年に務めたハーバート・レイモンド(H・R)・マクマスター氏(59歳)も骨太の論理構成と透徹した歴史観を基に国家安全保障会議(NSC)を切り盛りした。陸軍中将にして歴史学者でもある同氏が任期中を振り返りつつ、アメリカと世界が現在、直面する数々の脅威を鋭く分析した『戦場としての世界:自由世界を守るための闘い』の日本語版が日本経済新聞出版から刊行された。訳者の村井浩紀・日本経済研究センター・エグゼクティブ・フェローに読みどころを語ってもらった。
◇ ◇ ◇
トランプ政権は2017年12月に発表した文書、「国家安全保障戦略」で中国を競争相手と明記し、それまでの歴代政権が続けてきた「関与政策」に終止符を打った。党派による分断が著しい米国にあって、この対中強硬策に対する支持は超党派で広がり、現在のバイデン政権にも引き継がれている。つまりマクマスター氏が率いていた当時のNSCのチームが米国の対中戦略の歴史的な転換を実現させた。本書は同年11月のトランプ大統領の訪中の際のやり取りなどにも触れながら、米側が中国の指導部に対する警戒感を募らせていった経緯を鮮やかに再現している。
背景に戦略的ナルシシズム

著者のH・R・マクマスター氏 (c)Ray Kachatorian
本書を貫くキーワードは2つある。米国の歴代政権が独りよがりな対外姿勢を続けた背景にある「戦略的ナルシシズム」と、それがもたらすワナから脱却するための、相手国の真意を見抜く「戦略的エンパシー」である。中国の経済成長を支えれば、やがて民主化が進み、責任ある国際秩序の担い手にもなる――。そのような一方的な期待を込めた対中関与政策は、結果的に今、私たちの目の前にある強権的な「異形の大国・中国」の登場に手を貸した。また習近平国家主席がストックホルム症候群(誘拐・監禁事件の被害者が犯人に対して肯定的な感情を抱いてしまうなどの状態)よりも深刻な心理状態に陥っているのではないかというマクマスター氏の分析はユニークだ(119ページ)。習氏は毛沢東が進めた文化大革命で大きな被害を受けたのに、この中国共産党の過去を非難することを渋るからだ。
マクマスター氏の前著はベトナム戦争の泥沼化の経緯を描いた『職務怠慢:リンドン・ジョンソン、ロバート・マクナマラ、歴代の統合参謀本部議長たち、そしてベトナムへと導いた嘘』(1997年、邦訳未刊)である。国内の政治的な判断を優先し、戦争の現実を直視しなかったために敗戦に至った姿を浮き彫りにし、高い評価を受けた。米国の外交・安全保障政策のゆがみを正そうとする問題意識は一貫している。