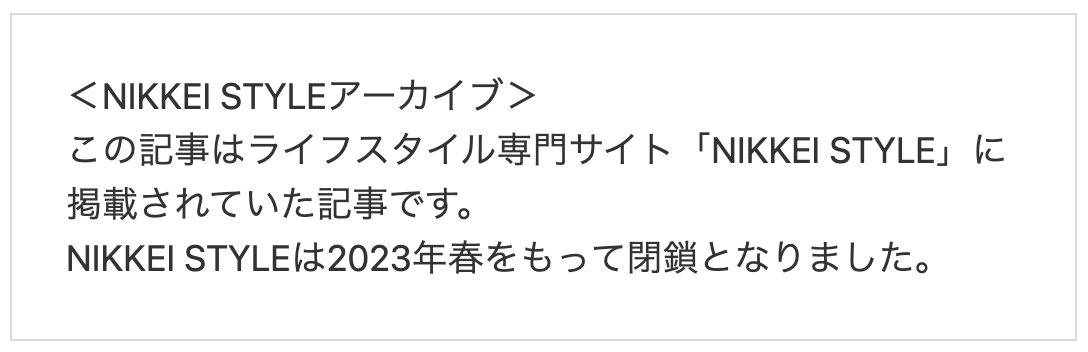有森裕子 スケボー選手たちが教えてくれた五輪の原点

2021年8月8日、聖火台の炎が静かに消え、熱戦が繰り広げられた17日間の東京五輪が閉幕しました。私もさまざまな競技をテレビで観戦し、マラソンは現地で選手と同じように北海道の気温や湿度の高さを感じながら見ることができました。
コロナ禍において、選手や関係者には厳しい行動規制が課され、無観客で開催された、異例尽くしの東京五輪。私が一般人であれば、「選手たちは本当によくがんばりました。感動しました。何とか無事に終わってよかった」で済むかもしれません。しかし五輪を経験したオリンピアンとして、今もスポーツに関わり、スポーツで人々が健康で幸せになってもらいたいという思いで活動をしている身としては、それだけで済まされない大会であり、良い・悪いでは語り尽くせないものだと感じています。
何をもって無事だというのか、何をもって成功というのかを、今一度考える必要がある大会だったとも思います。皆さんは、どのように感じられたでしょうか。
新種目・スケートボードの選手の姿に五輪の原点を見る思い
今回の東京五輪で一番心に残ったのは、スケートボードやサーフィンなどの新種目でした。特に10代、20代前半の若い選手たちがメダリストになって一気に注目を集めたスケートボードの選手の姿には、心を動かされた人も多いのではないでしょうか。スケートボードという競技を心から楽しみ、国籍や成績に関係なくお互いを称え合いながら極めてハイレベルのトリックに挑む彼ら・彼女たちの姿を見ていると、晴れ晴れとした気持ちになりました。
それを象徴したようなシーンが見られたのが、日本の四十住さくら選手と開心那選手が金・銀のメダルを獲得した、女子のパーク種目でした。最後に難易度が高いトリックに挑戦して、惜しくも着地失敗に終わってしまった岡本碧優選手に、さまざまな国の選手が駆け寄り、抱きしめ、笑顔で担ぎ上げたのです。失敗を恐れずに自分が理想とするトリックにチャレンジした仲間の勇気を称え、慰め、同じ競技者として支え合う。そんな姿勢をごく自然に行動に移した彼女たちの姿に、ハッとさせられました。
スケートボードの持つ、ライフスタイルの一環のような競技性も関係するかもしれませんが、国を背負っているという悲壮感がまったくなく、高いレベルのパフォーマンスを繰り広げながらも自然体であり続ける10代の選手たちの姿に、スポーツとは何か、五輪とは何かということを改めて考えさせられたのです。

五輪は本来、国と国との戦いの場ではない
五輪という特別な世界の舞台は、いつの間にかメダルの目標数を掲げて国別に競い合うようなメダル至上主義や、放映権やスポンサーを重視する過剰な商業主義に傾いてしまっています。もちろん、例えば柔道が日本のお家芸であるように、それぞれの国がプライドをかけてメダル獲得に挑む競技もあります。開催国の威信をかけて、1つでも多くのメダル獲得を目指したいという心情もあるでしょう。これだけの世界規模の大会を運営し続けるためには、莫大な放映料やスポンサー料が重視されるのは致し方ない側面もあります。
しかし、オリンピック憲章では本来、五輪の目的はスポーツを通じて調和のとれた人間を育て、互いを理解し、個人の尊厳を尊重する社会の実現を目指すこととされています。五輪は「平和の祭典」であり、過剰なプレッシャーを背負った国と国との戦いでもなければ、メダルの数を争う場でもありません。どの国がいくつメダルを取ったということは重要ではなく、本来は、個人と個人が競い合い、高め合い、認め合う場なのです。
今回、スケートボードをはじめとした新種目で活躍した新世代の選手たちは、多くの選手や指導者、そして応援する私たちが忘れかけていた、五輪の原点を思い出させてくれたように思います。
互いを敬い、助け合う精神を教えてくれた海外の選手たち
スケートボードの選手たちの姿を見ながら、私自身、スポーツマンシップとは何かを海外の選手から学んだことを思い出しました。
私が実業団に所属していた時代は、実業団全体に、「周りの選手はすべてライバル」という雰囲気が漂い、どちらかというとギスギスした関係性が多かったように思います。でも、日本のレースで海外の選手たちと走ったとき、水を含んだスポンジを取り損ねた私に、前を走る外国人選手がわざわざ振り向いてスポンジを渡してくれたり、スタート前はピリピリしていて敵だと思っていた選手が、ゴール後に人間味あふれる表情で握手やハグを求めてくれたりする経験を何度もしました。それは、相手を同じ競技に挑む同志として認め、リスペクトしてくれているからです。
そんな彼女たちの自らを称え、そして競った相手も称える考え方がとても好きで、たくさんのことを学びました。こうした国境を超えてお互いを認め合い、称え合うことの大切さを実感できる最たる場が、五輪なのです。
こんなにあらゆる人が五輪について考えた大会はなかった
私は東京五輪の開催が決定したときから、開催までのプロセスや運営も含めて、東京五輪が社会全体にどうコミットしながら、どのような意味、どのようなレガシー(社会的・経済的・文化的恩恵)をもたらすのかということに強い関心を持っていました。
そもそもコロナ禍での大会になる前から、「五輪のレガシー」という言葉の意味や、何をもってレガシーとするのかが、今一つ腑に落ちていない自分がいました。パラリンピックには「共生社会の実現の促進」といった明快なレガシーがありますが、五輪については正直なところ、どこかぼやっとしていて、自分でも示すことができませんでした。
しかし、皮肉なことに、このコロナ禍での開催だからこそ、これまで以上に、選手や指導者、大会関係者だけでなく、社会全体がさまざまな角度から五輪やスポーツのことを考え、行動を起こしたように思いました。
目に見える形での"安全"と"安心感"を得られないまま、不安と不信感で悩み悲しむ人たちの傍らで開催されたコロナ禍での今大会。その開催までのプロセスは、決して良いモデルになったとは言えません。悩まなければならないことをさまざまな角度から生んだ大会だったように思います。しかし、違う視点から見れば、貴重な経験だったとも言えます。「希望となる」とは言いづらいですが、未来へつながる課題、考えるべきことを持てたのが、今大会のレガシーなのかもしれません。単に「オリンピック、楽しかったね」で終わらせるのではなく、今まで常識だと思っていたことに対する批判や疑問も含めて、いろいろな角度から今回の五輪を検証し、考えることが、レガシーになっていくのではないかと思います。
オンライン上で誰もが自由に声を上げることができる時代だからこそ、オリンピック憲章を今一度見直して、関わるすべての人々が主役であり、スポーツを通じた平和の祭典である五輪の意義とは何か、スポーツの未来とは何かということを、関係者だけでなく私自身も、そして今回の五輪でいろいろなことを感じたすべての人が考えていく必要があると強く感じた大会でした。
次回は、東京五輪の陸上競技について感じたことをお話ししたいと思います。
(まとめ 高島三幸=ライター)
[日経Gooday2021年8月17日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。