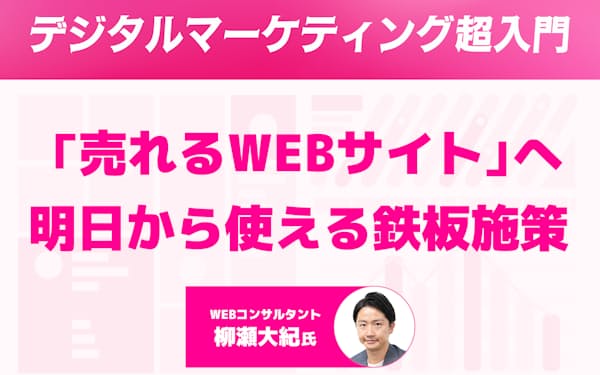出社か在宅か 生産性高まる働き方、客観データで分析
セールスフォース・ドットコム日本法人の小出伸一会長兼社長(下)

顧客情報管理のセールスフォース・ドットコムは大切にする価値観にあたるコアバリューとして、「信頼」「カスタマーサクセス(顧客の成功)」「イノベーション」「平等」の4つを掲げる。前回の「セールスフォース、『平等』で革新生む 人材獲得も」に引き続き、働き方改革に詳しい相模女子大学大学院特任教授の白河桃子さんが、平等推進への取り組みやリモートワークなどについて、日本法人の小出伸一会長兼社長に聞いた(以下、2人の敬称略)。
場所に依存せぬ働き方、女性活躍のチャンスに
白河 「Work from anywhere(場所を選ばない勤務)」と呼ばれるリモートワークやワーケーションの推進を、新型コロナウイルス禍の前から進めていたそうですね。南紀白浜(和歌山県)にワーケーションのサミットで行った時、御社のオフィスが南紀白浜にあるので驚きました。
小出 はい。当初は、「テレセールス(電話営業)であれば、オフィスはどこでもいいんじゃないの」という発想から、地方創生プログラムの一環として始めた取り組みでした。実際にやってみると生産性も上がりますし、特定の場所に依存しない働き方を推進することで女性の活躍のチャンスは増えると確信しています。
白河 たしかに、「在宅勤務になったことで、保育園のお迎えのために時短勤務を選ぶ必要もなくなった。予定よりも早くフルタイム勤務に戻した」という女性の声は聞かれます。
小出 幅広い業態で、働き方が根本的に変わろうとする転換期も2年目を迎えているわけですよね。これまでの議論は在宅比率が何%かでしたが、これからはその先の議論が重要になるとみています。
つまり、データの分析とそれに基づく施策です。例えば、在宅勤務によって生産性が上がるかどうかは、職種や地域などの条件によって異なるはずです。どんな状況下で、誰が、いつ、どのくらい、出社・在宅を選ぶのが最適なのか。そういったデータ分析の結果を、来年にも移転予定の新オフィスの設計にも生かす計画を立てているところです。
しかし日本社会全体を見渡すと、コロナ禍の働き方に関する客観的なデータに基づく議論がほとんどなされていないように思えます。データ活用の面で世界に遅れをとると、さらにギャップが開いてしまうのではないかと懸念しています。
白河 これからの働き方について、データを基にした議論を進めていくべきだということですね。
小出 データに基づく議論というのは、平等の推進の面でも不可欠で、米国では非常にシビアに求められる視点です。万が一でも、特定の人種に偏って出社を指示するようなことは絶対に許されませんから。客観的な生産性分析をベースに議論をすべきで、曖昧な感覚ベースでは納得感は得られないわけです。ですから、私たちは各部門や個人の働き方の違いと結果を分析しながら、次の施策に生かそうとしています。
また、新入社員研修に関しては、リモート形式だと生産性が低下することが明らかになったので、今後は集合形式で実施できる環境を整える方策を練っていくと思います。
平等を維持するためチェックを続ける

白河 やはり客観的な事実を観察する姿勢を持つことが大事ですね。御社が米国本社でジェンダーや人種の賃金格差の是正に取り組むに至った経緯も、実際に調査してみたことが出発点だったわけですし。賃金格差などについては、「そう簡単には調べられないんですよ」という声が経営者から時折聞かれますが、実際はいかがでしょう。
小出 本気でやろうとすれば、難なくできるはずですよ。加えて、調査も継続することが重要です。そもそもIT(情報技術)業界というのはM&A(合併・買収)によって成長する会社が多く、自然と(従業員間に)格差が生まれやすい構造になっているんです。賃金体系が異なる会社同士が統合するので、何も手を打たなければ格差は広がりやすい。我々のように激動の中で会社経営をしていると、真剣にチェックと是正を繰り返さないと、平等は維持できない。
平等の測定は、ある時点の「断面図」を見るだけでは不十分です。こまめにチェックして是正するという繰り返しを、経営の柱に入れておかなければいけません。「一度やりました」だけでは、格差はいつまでも解消しないと思います。
白河 「やったつもり」で終わると、いつの間にか同質性の高い環境をつくってしまうのですね。その結果、イノベーションに出遅れてしまう。「同質性のリスク」の増大は、経営を揺るがしかねないと私は注目しているのですが。
小出 おっしゃるとおりで、私も強く同感します。特に日本は、教育でも産業でも同質性を求めてきた歴史があるので、強く意識しなければ同質性のリスクから脱するのは難しい。皆が同じ黒電話を欲しがった高度経済成長時代には、均一なクオリティーの製品を安く生産して届ければよかった。でも今は、携帯電話の形状も多様で、使い方も人によってまったく異なるニーズがある。経営者が発想を変えないと生き残れません。
白河 テレビという機器の使用法も地上波放送だけでなく、ユーチューブやネットフリックス、テレビ局の見逃し配信など、多様化していますよね。某局の方に「なぜ御社の配信チャンネルのボタンをリモコンに搭載してもらわなかったのですか」と聞いたところ、「地上波放送が絶対という上層部の考え方が強くて」という答えが返ってきました。同質性の高い組織であるテレビ局が変われないのは無理もないと思いました。
「男性ばかりの会場でプレゼンしてきた」と自覚
白河 ダイバーシティ(多様性)に関してもいまだに「CSR(企業の社会的責任)だ」と位置付けている人は結構いるのですが、そうではなくサバイバルのための経営戦略ですよね。女性だけでなく、外国人人材や障害のある方、LGBTQ(性的少数者)の方も含めて多様な視点を生かすことが、企業成長につながるという理解が進まないといけませんね。
小出 その重要性が高まっているという空気を、経営者が肌で感じないといけないですし、先頭に立って腕まくりをしないとダメでしょうね。LGBTQへの理解を深める「東京レインボープライド」というパレードに当社が参加したときに、私も先頭で歩かせてもらったのですが、やはり先頭に立って初めて見える風景がありました。頭では分かっていたつもりでしたが、「え? うちの社員が200人も参加しているのか」とその数のパワーを感じられて。本気で経営課題として取り組まないといけないという使命感が湧いてきました。
白河 実際に歩いて分かるんですね。女性活躍推進の課題を本気の経営課題として捉えられる経営者はまだ一握りで、「福利厚生課題」で止まっているケースは多いと感じています。するといつまでたっても「女性をたくさん採用すると、育休を取ったときにどうするの?」といった発想で終わってしまう。経営のサクセスにつながる課題なのだと、経営者が実感するには何が必要だと思いますか?
小出 20年くらい前に私自身が言われたことなのですが、「マイノリティーになる経験」が1番効くと思います。女性が2000人集まった会場で、5人のパネリストのうち男性は私1人だけというステージで話す機会がありました。このときばかりは、仮病を使って休もうかと思うくらい気が重かったですね(笑)。
実際にステージに上がると、そこから見える風景にいい意味でのショックを受けました。いつもはダークカラーで染まる風景が、この日はカラフルな色彩で埋め尽くされていて。「ああ、私は今までずっと男性ばかりの会場でプレゼンしてきたのだな」と自覚が芽生えました。女性ばかりを相手にするパネルディスカッションも、やはりいつもとは違う感覚でした。「これがマイノリティーになるという感覚なのか」と気づきがありました。
私の場合は外資系企業で海外赴任も多かったので、常にマイノリティーの立場であったとも言えます。「もうちょっと気を使って(分かりやすい)英語を話してほしい……」と汗をかいたことは数え切れないほど。やはり体験が何より学びになりますね。日本企業でずっと働いている男性には、マイノリティー体験が圧倒的に足りないはずです。今からでも遅くないので、男性リーダーにマイノリティー体験の機会を与えることは有効なのではないでしょうか。
白河 マイノリティー体験の機会をつくることが、社会全体の改革にもつながるのかもしれないですね。そして、チェック&バランスとデータに基づく施策を練ることも重要である、と。本日は示唆に富むお話をありがとうございました。
あとがき:ESG(環境・社会・企業統治)投資におけるSの指標は、女性管理職の数というよりも、グローバルでは「男女の賃金格差」が基準です。欧州などでは公表する企業も増えていますが、日本で公表しているのはホンダくらいです。賃金格差というのは分かりやすいジェンダー平等の指標です。まずはマイノリティーの中のマジョリティーである女性の賃金を調べてみたら、平等ではなかったというのがセールスフォースのプロジェクトの始まりでした。日本では正社員同士で比較しても女性の賃金は男性の75%強です。格差を是正するために、企業はまずは数値を出してみることが重要です。

(文:宮本恵理子)
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。