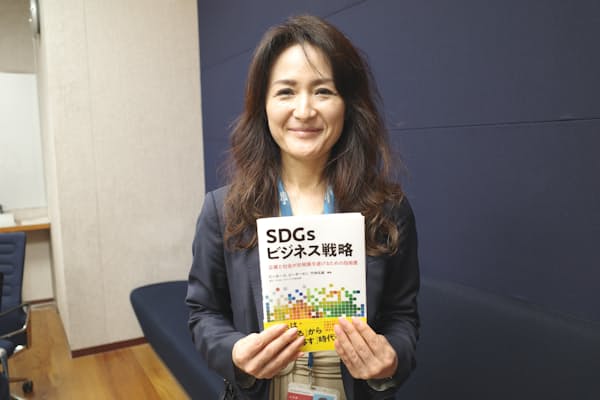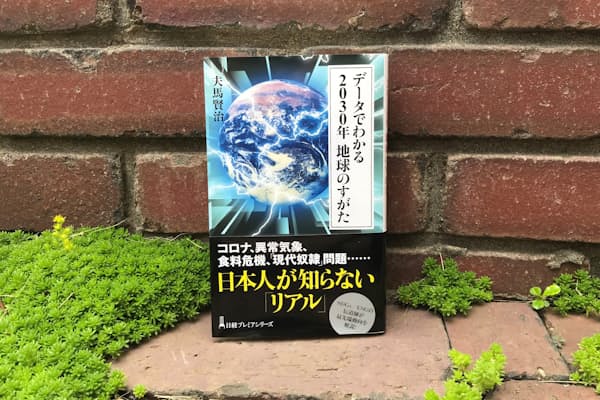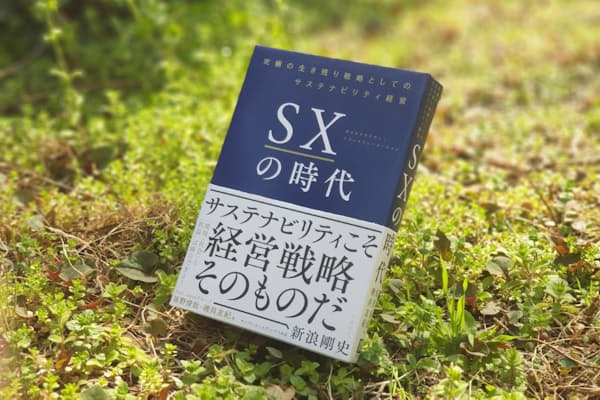コロナ後の経済再生、SDGs実現がカギに サックス教授
コロンビア大学教授 ジェフリー・サックス氏(下)

ジェフリー・サックス米コロンビア大学教授
米コロンビア大学教授のジェフリー・サックス氏は、国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)の理論的支柱となるなど、これからの世界に強い影響力を持つ経済学者の一人だ。新型コロナウイルスによるパンデミックが今なお続く中、世界の今と未来をどのように見ているのか。コロナ後の世界に関心を寄せる作家・コンサルタントの佐藤智恵氏によるインタビューの後編は、SDGsと世界経済の復元への動きを巡るサックス氏の見方に迫る。
パンデミックで高まったSDGsへの認識
佐藤 サックス教授は、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標「持続可能な開発目標」策定の理論的基礎を築いた立役者と言われています。日本ではいま、急速にSDGsが普及しはじめていて、「はやっている」と言ってもいいほどです。SDGsのピンバッジを付けているビジネスパーソンをよく見かけますし、テレビ番組でも頻繁に特集が組まれています。新型コロナウイルスの感染拡大がSDGs実現への動きを加速させたのでしょうか。
サックス パンデミック(世界的大流行)が人々に地球の未来について考える機会を与えているのは確かです。世界が直面している危機にどう対応したらいいのか、パンデミック後、より良い経済を築くにはどうしたらいいか、世界は共通課題の解決に向けてどのように連携していくべきか。これらはすべてSDGsに関わることです。昨年からのパンデミックで、日本だけではなく世界中の人々がよりSDGsの重要性を認識するようになったといえるでしょう。
パンデミックがもたらしたのは未来への不安です。いま必要なのは明確な指針です。SDGsが国連で採択されたおかげで、どの国の政府も「これはすべての国連加盟国が合意した目標です。パンデミック後は経済を回復させながら、SDGsの実現に向けて行動していきましょう」と国民に示すことができるようになりました。
ところで日本ではSDGsがそんなに広まっているのですか。それは朗報ですね(笑)。SDGsを実現する上で、日本の協力は不可欠です。日本がSDGsの目標に向かって注力するのは、日本国民、そして、日本経済にもプラスになると思います。
SDGsの実現に向けた取り組みは多くのビジネスチャンスを生み出します。まず技術革新は不可欠です。エネルギーや資源をより効率的に使う技術、生物多様性を守る技術の開発は必須です。さらには環境を破壊しない新しい素材の開発も必要です。日本はこれらすべてにおいて優れています。日本が率先して機器や技術システムを開発すれば、日本だけではなく、他の国の変革を後押しすることができます。