苦手な上司、嫌な部下 心理学に学ぶ上手な接し方

せっかちな上司にやる気のない部下……働く女性のお悩みは尽きません。知っておくことで発想の転換が図れる、イライラやモヤモヤがスッキリ晴れて気持ちがラクになる心理学を、立正大学名誉教授で対人・社会心理学を専門とする齊藤 勇さんに解説してもらいました。
先輩・上司のお悩み
A 話すスピードや、メールの長短などを「ミラーリング」でまねる
相手が笑ったら笑う、コーヒーを飲んだら飲むなど、同調した行動を取り、文字通り鏡のような振る舞いを意図的にすることで、相手に好意を持ってもらいやすくなる効果。
人がイライラするのは、間が悪い、ペースが遅いなど、相手とテンポが合わないときだ。逆に仲がいい友人とは、ランチを食べ終わるタイミングも笑うポイントもきっと似ているはず。
「仲のいい人と行動が合ってくるのは、好意のある相手を無意識のうちにまねるからです。それを応用して、鏡のように相手に同調した行動をするミラーリングで、類似性を意図的につくり出し、相手を気持ち良くさせることができます」(齊藤さん)。
例えば、早口の相手には早口で話す。メールも「明日、出張なのでよろしく」と簡潔に書く上司なら、丁寧なフレーズを延々と書くよりは、「かしこまりました。何かあればメールでご連絡します」と簡潔に返す。心理的テンポを合わせることで、上司のイライラを軽減できる。
A 「自己開示」でまずは自分について話すことから
相手からしてもらったことに対し、「お返し」をしなければと感じる心理。敵意を向けられれば敵意を返し、譲歩してもらったら譲歩したくなる。自ら心を開くほど、相手も開いてくる。
先輩に溝を感じているとしたら、先輩も同じように感じているはずだ。相手ともっと気軽に話せるようになりたければ、「まずは、自分の情報を伝えることから始めましょう」。趣味や出身地、好きな食べ物などを話し、自分のことをもっと知ってもらおうと自己開示すれば、相手も心を開いてくる。
「『返報性の原理』といって、自己開示には相互性があります。例えば、過去の失敗談などを話すと『こんな話までしてくれるなんて』と感じ、相手もそれに応えて『実は、私も…』と話したくなるのです」。示した自己開示が親密なら、相手の自己開示も深くなる。
ただし、自己開示には相互性があるからこそ、関係が深まらないうちに、急に踏み込んだことを話題にするのはNG。相手を身構えさせてしまい逆効果になりかねないので、段階を踏もう。
A 得意なことを見せるなど、「ハロー効果」を有効に使おう
ハローとは、仏像や聖人の背後に表現されている光背のこと。望ましい特徴があると、その人に関わるすべてのものが、望ましいものに見えてしまう。認知バイアスのひとつ。
冴(さ)えない上司が、クラシック音楽に造詣が深いと分かっただけで、知的で穏やかな人物に見えてしまったりする。「何か1点、秀でたものがあったり、目立つ特徴があったりすると、それが人物全体に反映していると思ってしまうことを、ハロー効果といいます」。
例えば、エクセルが得意な人なら、きっと仕事のダンドリも効率的、企画を理論的に組み立てることができるだろう……と、全体の印象まで変わってしまう。これを利用すればいい。日ごろの会話で、SNSの人脈が広い、地元の地理に詳しいなど、自分の得意ジャンルをアピールしよう。企画書に専門家の意見や、上司が認めている人物のコメントを引用して、説得するのもハロー効果。七光は、上手に利用すればいい。
A 2つのいずれかを選ばせる「チョイス・メソッド」で迫る
選択肢を2つに絞ることで相手を追い込み、判断をコントロールする方法。買わないという選択肢がない2択を提示して売りつける、悪徳セールスの手法としても利用されている。
優柔不断な上司に「どうしますか?」と尋ねても、「とりあえず、様子を見てからだな」と言われるのがオチ。そこで有効なのがチョイス・メソッドだ。「デートに誘うときに、『今度の日曜日に一緒に遊びに行かない?』と聞くのではなく、『今度の日曜日に一緒に出かけようよ、遊園地がいい? 映画がいい?』という選択肢の提示の仕方で、決断を迫るのがチョイス・メソッドです」。
このとき、選択肢を多くしすぎないことも大切。「最近の実験社会心理学の研究では、人は選択肢の多い状況を求める一方で、選択肢が多くなるほど、実際に選択した結果への満足度は低下することも明らかになっています。『選択のオーバーロード現象』といいます」。
決められない上司には、限られた選択肢を提示して決断をさせることがポイントだ。
A 「スモールワールド現象」で意外に世界は狭いと考えよう
ミルグラムが1967年に行った実験。ランダムに選んだ人たちから、知り合いへの受け渡しを通じて手紙が特定のAさんに届くかを調べた。21.6%以上が届き、平均5.2人を経ていた。
転勤や転職で、新しい職場となれば、誰しも緊張し不安に感じるだろう。しかし、知り合いの知り合いをたどれば、世界中の誰にでも行き着くと、仮説を立てて実験した人がいる。結果は、最初に決めた人に、多くの人から6人目で行き着いた。「このようにつながっていることをスモールワールド現象といいます。それぐらい世間は狭い。逆にいうと、人間は実際よりも世界を広く感じてしまっているのかもしれません」。隣の席のこの人も、自分の友人の友人の……と思えれば、新しい環境への不安も軽減されるはずだ。
同僚や部下のお悩み
A あえて頼み事をして好意を呼び込む「ベンジャミン・フランクリン効果」
米国の政治家。政敵にコレクションしている本を貸してと頼むと相手は応じ、その後は友好な関係に。「大事な本を貸すくらいだから自分は相手に好意がある」と、認知の転換が起きた。
ウマが合わない、あるいはなんとなく敵視されていると感じる相手にこそ、あえて頼み事をするという方法がある。
普通、嫌いな相手には頼み事をしない。頼み事をされるのだから、自分は好かれているのに違いない。それに応えなければと、人は感じる。
「相手の求めに応えることで、自分の考え(相手が嫌い)と、行動(相手のためにやってあげる)とに矛盾が生じます。その矛盾を心理学では、『認知的不協和』といいますが、矛盾を解消するために認知の転換が起きるのです」。頼み事に応えて相手のために何かしてあげるということは、自分は相手を好きなのだと認知が変わるのだ。「人への頼み事は遠慮しがちですが、ちょっとした頼みなら、頼み事も解決するし、むしろ自分が好かれる効果があります」。
A 「ウインザー効果」で第三者の「ほめ」を伝える
第三者から言われたほうが信頼性が増す心理傾向のこと。小説『伯爵夫人はスパイ』のウインザー公爵夫人の言葉、「第三者の褒め言葉がなんといっても一番効果があるのよ」が由来。
おいしい店を探すときに、口コミサイトを参考にする人は多いだろう。「人は、直接利害関係がない第三者による情報を信頼する傾向があります。これをウインザー効果といいます」。
やる気のない部下に「2日で調べ上げるなんて、すごい」と面と向かって褒めても、素直に受け取れない人もいる。しかし、「マーケティング部の人が、あれを2日で調べ上げたなんて驚きだと言っていたよ」と第三者の言葉として伝えたら、説得力が高まる。「間接的に褒めることで信頼され、それを言ってくれた第三者にも、伝えてくれた人にも好感が生まれます」。
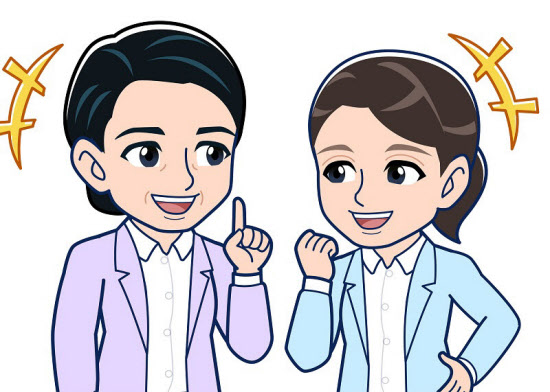
A 期待することで「ピグマリオン効果」が生まれる
小学校で教師が、生徒に対して期待を持つと学力の伸びに大きな影響があることを、ローゼンタールらが実験で証明した。ギリシャ神話の女神にちなんで、ピグマリオン効果といわれる。
部下を見て伸び悩んでいると感じるとしたら、そこには期待があるということだ。そこで、「この人なら、もっとできるはずなのに(やらない)」と見るのではなく、「この人なら、きっとできる」と思って、見守ってはどうだろうか。
「人が人にレッテルを貼る『ラベリング』によって生まれる、プラスの効果をピグマリオン効果といいます。この人はできるという期待感が、無意識のうちに声や表情、態度によって相手に伝わり、相手はそれに応えようとする結果、実際に成果として表れるのです」
人に期待する気持ちを持つことがスタート。「部下の言動を否定しない、『そうだね』と相づちを打つだけでも効果があります。相づちは会話をスムーズにし、良い人間関係を築く上で、非常に重要なノンバーバルコミュニケーションなのです」。
夫や子どものお悩み
A 小さな頼み事からスタート。「フット・イン・ザ・ドア ・テクニック」
セールスマンが訪問販売をする際に、ドアに片足を入れて閉まらないようにしてから商談に入ったことに由来。相手が承諾しやすい要求から始めて、次第に要求を大きくしていく交渉術。
家事に不慣れな夫には、ちょっとしたお願い事から始めよう。例えば、「飲み終わったカップは下げてね」からスタートし、次は「下げたカップは洗っておいて」と頼む。「最初に小さな要求を引き受けると、次にもう少し大きなお願いをされても断りにくい。一度『いいよ』と言った自分の像を壊したくないという、『一貫性の原理』が働くからです。こうした説得方法をフット・イン・ザ・ドアといいます」。
一方、ドア・イン・ザ・フェースという手法もある。こちらは拒否されることを前提に、わざと大きな依頼をして、次に小さな依頼をする。人は依頼を断ると何らかの罪悪感を持つ。その罪悪感を埋めるために引き受ける心理を利用したもの。「これはタイミングが大事で、断られた後、あまり間を置かずに『じゃあこれを』と依頼するのが効果的です」。
A 「ピーク・エンド」の法則。最後が一番印象に残る。
ノーベル経済学賞受賞者で心理学者でもあるダニエル・カーネマンが提唱。冷水に手をつける実験や騒音による不快感の調査などから、最後の体験が全体の印象に影響を与えるとした。
みんなに満足してもらう会にするにはどうしたらいいか、幹事としては悩みどころだ。そこで旅行の思い出や、過去のデートの記憶を振り返ってみよう。「おそらく印象に強く残っているのは、一番盛り上がったとき=ピークと、最後=エンドでしょう。これをピーク・エンドの法則といいます」。
ピークは、人によって何をピークと感じるかコントロールできないとしても、終わりは、幹事ならセッティングしやすい。
例えば飲食店に行ったとき、料理は普通でも、帰り際にシェフや女将が見送りに出てきたら、それだけで店の格や印象がアップする。同様に、食事会でもパーティーでも、なんとなくお開きにするのではなく、感謝の気持ちを込めた最後の挨拶をきちんとする、丁寧に見送るなどの振る舞いや別れ際の印象で、参加者の満足度は高くなる。
A 「フレーミング効果」で見方を変えよう
認知バイアスのひとつで、物事へのスポットの当て方で印象が変わること。「1日たった300円分」とすることで「年間10万9500円」よりも安く感じさせるなど、マーケティングでも使われる。
テストの点数が低くても気にしない、のんきな子どもの態度にイライラを募らせることもあるだろう。しかし、「物事のどこにフレームを当てるかで、見え方は全く違ってきます」。
例えば、大事故に際して、死傷者数と生存者数、どちらを大きく報道するかで、ニュースを聞いたときの心理的な印象は大きく違う。同様に、100点満点なのに20%も間違えたと見るか、8割も正解したと見るか。結果は同じでもポジティブな見方をすることで、親自身の気持ちも、子どもの肯定感も大きく変わってくる。
自分についてのお悩み
A あえて最後の1ページを残す「ツァイガルニク効果」を活用
女性心理学者。同じタスクを課した2グループで、タスクを中断したグループのほうが内容を覚えていたことから、未完了の課題は記憶に残りやすいとする、ツァイガルニク効果を提唱。
在宅ワークで、気持ちの切り替えがしにくいなかで、仕事にサッと取りかかるには、前日の仕事を少し、残しておくのがポイントだ。「仕事はキリのいいところまでやってから終わりにしたいと思いがちですが、人間には、達成できなかったものや中断しているもののほうが気になる心理があります。これを実験で明らかにしたのがツァイガルニクです」。
テレビ番組で、「この後、思わぬ事件が!」などとナレーションを入れてCMをまたがせるのも、同じ効果を狙ったもの。
「目標を達成したり、完結したりすると、緊張感が解消して記憶に残りにくいのですが、やり切ってしまわないことで頭の中に残る。翌日、仕事のスイッチが入りやすく、中断中に新しいアイデも生まれやすくなります」。
A 「コンコルド効果」による認知バイアスから抜け出せ
超音速旅客機コンコルドへの開発投資が巨額になり、途中で採算が取れないという認識があったにもかかわらず、中止することができず、膨大な損失を出したことに由来する。
前払い制のエステや、教材費を払い込んでしまった通信教育など、これまでにかけた金額のうち、回収不可能な費用のことを、経済学では「サンクコスト(埋没費用)」という。
投資や公共事業などで、継続すると損失が大きくなる恐れがあると分かっていても、サンクコストを惜しんで続けてしまうケースがしばしばあるが、これと一緒。「途中でうまくいかない、自分には向かないと思ってもやめられない。費やしたお金や時間の元を取ろうとして、かえって損失を大きくすることを、コンコルド効果、あるいはコンコルドの誤謬(ごびゅう)といいます」。
自分ではこれまでかけた時間とお金を秤(はかり)にかけて、論理的に判断をしているつもりでも、実は、思い込みによる思考のエラーが起きている。認知バイアスに陥っていると思って、踏ん切りをつけよう。
A 「WOOPの法則」で障害を事前に想定した計画を
米国の心理学者ガブリエル・エッティンゲンが体系化した、円滑に目標を達成するためのプロセス。WOOPは、Wish(願望)、Outcome(結果)、Obstacle(障害)、Plan(計画)の頭文字。
フルマラソンを完走したい、英検1級を取りたいと、意気込んで始めても、子どもが熱を出して休まざるを得なくなったり、仕事が立て込んで続けられなくなったりしがちだ。目標を持っているほうが成功の可能性は高まるといわれるが、願っていれば実現するというわけではない。そこで知っておきたいのがWOOPの法則だ。
「ナポレオン・ヒルの成功哲学、『思考は現実化する』がポジティブ思考を重視することへの、反論として登場した理論です」。まず、目標と実現した場合の成果を具体的に考える。その上で、起こり得る障害を事前にすべて書き出して、克服するためにはどうしたらいいか、なぜできないかを考え、自分が実行できるプランを立てたほうが、実現に近づくとしている。

A 「セルフ・ハンディキャッピング」になるより、過程を褒めよう
プライドが傷つかないように、周囲への言い訳や弁解で他者からの評価を保持したり、努力を拒否することで、結果が今ひとつでも仕方がないという形で、自己評価を維持したりする。
学生時代、試験前に限って部屋を片づけたり、「寝ちゃって全然勉強できなかった」と友人に話したりした経験はないだろうか。「人は自尊心が傷つくことを嫌います。だから、試験前に部屋の片づけに時間を使うことで自分自身に対する言い訳や、『寝ちゃった』という周囲に対する言い訳をつくる。あらかじめ自分にハンディキャップを与えておくことで、自己嫌悪や評価の低下を回避する、セルフ・ハンディキャッピングという自己防衛をしているのです」。
スケジュールがいっぱいで企画を十分練る時間がなかった、細部まで検討する余裕がなかったなどの言い訳をすることで、自尊心のダメージは減るが、「挑戦する勇気を阻害するデメリットもあります。努力した過程を褒めることで自尊心を高め、セルフ・ハンディキャッピングから抜け出しましょう」。
A 関心を向けていれば「プライミング」で素早くキャッチ
先行する刺激(プライマー)を処理することで、後続する刺激(ターゲット)の処理が促進されること。逆に、先行の刺激が後続の刺激に抑制的に働く場合はネガティブ・プライミングという。
「みりん」と10回言った後に、「鼻の長い動物は?」と聞かれると、思わず「キリン」と答えてしまう。子どもの頃に、こうした10回ゲームで遊んだことがある人は多いだろう。
「頭の中は意外に単純で、今、動いているもの、考えていることに次のことが影響されます。それまで注意を向けていたものや、関連している刺激には、脳は優先的に反応する、プライミング効果があるのです」
例えば、いつもパッケージデザインのことを考えていると、脳は、街の景色のなかからでも関連が高いものを見つけようとする。他のパッケージデザインに自然と目が行ったり、電車の車体を見ても、スーパーの野菜の陳列を見ても、それが後続刺激となって、新たなパッケージデザインのヒントになったりするのだ。
A 「インポスター症候群」に陥るより、自分を受け入れよう
インポスターは「詐欺師」の意。成功を収めた人が、能力以上に評価されている、周囲をだましている気持ちになり成功を回避する心理状態のこと。特に女性に多いとされる。
「能力を過大評価されている」という思いがあれば、成功していても楽しくない。「実力がないことがいつか見透かされるのでは」と感じていると、人と深く関わることを避けるようになってしまう。
「女性が成功を回避するこうした心理状態は、1970年代のアメリカで指摘され、後にインポスター症候群と名づけられました。もし、自分の成功を肯定できず自信が持てないとしたら、インポスターの心理状態に陥っているのかもしれません」
背景には、男性より劣ると思い込まされてきた社会的環境や、自身の成功よりも組織や周囲との同調を求められる状況がある。「男性も運やヒキで出世しています。それを自分に責任を負わせることはありません。今の自分をそのまま、受け入れることから始めましょう」。
この人に聞きました
立正大学名誉教授。1943年生まれ、早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。カリフォルニア大学留学。専門は対人・社会心理学。日本ビジネス心理学会会長。『図解 心理学用語大全』(誠文堂新光社)、『今日から使える行動心理学』(ナツメ社)ほか、多くの編著書・訳書・監修書がある。
(構成・文 中城邦子)
[日経ウーマン 2021年1月号の記事を再構成]
ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。
※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。















